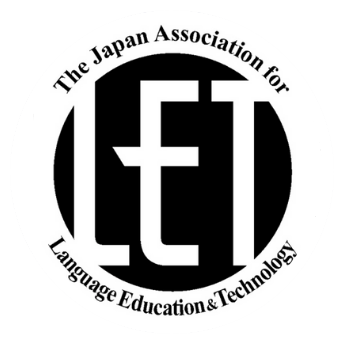大会名
02年度春季研究大会
大会(春・秋・全国)
春季大会
日付
2002年5月26日
会場
同志社女子大学
概要
02年度春季大会は、2002年5月26日(日) に同志社女子大学(京田辺市)で開催されました。学習用Webサイトの構築ツールWebCT の日本語化に取り組まれている梶田先生(名古屋大学情報連携基盤センター) の講演、シンポジアム「大学教授でいる方法:あなたの商品開発、品質管理、CS対策は万全ですか」、研究発表5件、賛助会員展示5社など、充実した内容で、106名の会員諸氏の参加を得ました。この場を借りて、会場校の諸先生方(枝澤康代、若本夏美、佐伯林規江、三根浩各先生)ならびに会員の皆さんのご協力に感謝いたします。プログラムの詳細については下記の報告をご覧下さい。
詳細
講演
「学校教育におけるe-Learning」
梶田将司(名古屋大学情報連携基盤センター助教授)
最近では、コンピュータやインターネット等を利用した学習のことを総称して「e-Learning」などと呼ぶことがある。しかしながら、「e-Learning」のプラットフォームやシステムには多様なものがあり、それらを利用するためには、教師、学習者共にまずその使用方法を学ばなければならないという問題が出てくることも多い。そこで、「e-Learning」による学習・教育のプラットフォームを同じものに統一して利便性を高めるという「標準化」の必要性が叫ばれてきている。今回の講演は、そういった「標準化」の流れに沿った「e-Learning」のシステムの一つであり、北米の大学で50%以上のシェアを持つとされているWebCT(Web Course Tool)についての講演であった。講師の梶田先生は、カナダのUBC(University of British Columbia)で開発されたWebCTを日本語対応にローカライズする作業に携わってこられた方で、日本におけるWebCTの第一人者である。
梶田先生からは、現在WebCTを利用している教育機関は、日本を含めて84カ国2600箇所以上であり、1000万人以上が利用しているといった利用実態が解説され、専門的な知識がそれほど無くても、小テストや掲示板、チャットなどのシステムをWebページ上に構築でき、学習履歴の記録や成績管理も可能、といったWebCTの利点が述べられた。講演の途中では、WebCT利用法の解説ビデオやWebCTの開発者であるUBCのMurray Goldberg氏からの開発の経緯が述べられたメッセージビデオが流されると共に、PowerPointとストリーミングビデオを時間軸の同期を取って提示するシステムのデモンストレーションなども行われ、WebCTというシステムを具体的に理解することができた。梶田先生からは、WebCTのようなコース管理システム導入の利点として、1)教育内容の改善が容易になる(学生の声に基づいた改善)、2)教育内容の公開が容易になる(他の先生との教材やノウハウの共有が可能)、3)教育内容の履歴作りが容易になる(教育実践の客観評価)、4)教育内容の引き継ぎが容易になる、といった点が述べられた。フロアからは、名古屋大学内での利用状況はどのようなものか、教員への利用ガイダンスや支援体制はどうなっているか、他の同類のシステムと比較した場合のWebCTの特徴は何か、といった質問がなされ、多くの関心が寄せられた講演であった。(杉森直樹 大阪電気通信大学)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジウム
「大学教授でいる方法:あなたの商品開発、品質管理、CS対策は万全ですか」
東 淳一(流通科学大学)
青木幹生(関西国際大学・非)
野村和宏(流通科学大学)
本シンポジウムはLET関西支部の大学授業研究部会によって企画されたものである。演題には経営学やマーケティング関係の用語が用いられており、一見「教育」と馴染まないかに見える。しかしパネリストの各提案を通じて、ビジネスにおける考え方が教育実践においても参考になる点が多々あることがわかった。
まず野村氏は、ユーモアを交えながらも大学教員の勤務実態を批判的にながめた上で、「いつ誰に見てもらってもいい」という授業を行うことの必要性を主張され、授業というものは常に公開が前提であり、教師は public speaker としての自覚を持つべきだとの持論を展開された。Public Speaker としても経験豊富な氏は、授業を質的に高めるためには、教師は自らを第三者的にながめる必要があり、そのためには自分の授業をビデオ録画するといった方法が有効であるとの具体的提案を行なわれた。
東氏は、マーケティングの考えを導入して、顧客としての学生のニーズを満たすような授業、すなわちCS(Customer Satisfaction)に応える授業を行うためには、教育目標に沿った教材開発(商品開発)や授業内容の保証(品質管理)といったことが必要だとの主張をされた。この点で大学教育は問題を抱えており、その解決には企業経営におけるknowledge managementという考え方が有効であると述べられた。そして、各教員(あるいは教員集団)の授業に関するノウハウや知識を共有するために、公開授業を積極的に行っていくべきだとの提案を行なわれた。
青木氏は、両者の提案を踏まえて、ビジネス界におけるマネイジメント経験者の立場から授業改善への提言をされた。教育界における教育目標は企業では利潤(数値目標)に相当し、シラバスは事業計画に、そして授業は営業活動に相当すると考えられるが、企業では数値がすべてであるという厳しい側面を紹介された。そして学校教育を請負業務だと考えるなら、しかるべき責任(すなわち教育目標の達成)を果たすべきだと述べられた。なお氏は学校教育が企業のように数値目標の達成を目指すべきだと言っているのでは当然ない。最後に氏は、大学では学生の卒業後を見据えて社会教育を行っていく必要性があるのではないかとの提案をされた。
今回のシンポジウムでは、授業の質を高めて教育目標を達成するには、教員が知識やノウハウを共有することが大切であり、そのためにはそれぞれがさまざまな方法で授業を公開すべきであるという点が確認できた。また、一教員である筆者にとってはしっかりした職業意識を持つことの意味を考えさせられる機会でもあった。(神崎和男 大阪電気通信大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 1-1
“Welcome Back to My Classroom: Self-Assessment, Responsibility and Freedom in Communicative English”
Andrew Obermeier (Kyoto University of Education)
Classroom procedures for communicative English classes for English majors were described in this presentation which included video clips of student interactions. Obermeier uses a 4-5 week teaching cycle: Week 1, diagnostic pre-test and cooperative setting of unit objectives between the students and the teacher; Weeks 2-4, free-talking warm-up session, focused communicative grammar work, highly focused grammar homework, student reflection on the learning process, and teacher reflection on the course activities; Week 5, criterion-referenced oral test based on the objectives agreed upon at the start of the cycle. The course is aimed at having students actively use English among themselves and also at involving them in the learning and assessment process as most intend to become schoolteachers in the future. To help realize these aims, photo sheets are prepared at the beginning of the class with snapshots of the students taken by other students. During the free-talking warm-up session, each student talks with another student and the two sign each other’s photo sheet to keep a record of the interaction. Students must try to chat with every other student by the end of the cycle. The classroom grammar work is taught using photocopiable material to wean the students away from reliance on textbooks. For homework, they use workbooks and supplementary materials. In the reflection portion of the cycle, the students record their reactions to the lesson in learning logs and assign numerical ranking (1 to 5, which is the best grade) to describe how interesting and useful the activities were. This helps make them aware of their own learning process. Obermeier himself, as the teacher, also reflects upon the class activities and tries to describe the critical aspects of the lesson with specific details, analyze his own behavior and then decide upon future action. He uses a teacher trainer rubric to aid this reflection process. The active classroom video clips attested to the success of this approach which involves active student participation in the goal setting and classroom activities to lower the students’affective filter and encourage a positive attitude toward using English with their peers. The teacher’s focused reflection and analysis after each lesson plus student feedback via their learning logs should be very effective for promoting a positive spiral of raising awareness of the learning process and contributing to the language learning itself. (Judy Noguchi Mukogawa Women's University)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 1-2
「英語学習者のストーリーテリングにおける照応表現」
谷村 緑(大阪外国語大学大学院生)
日常の言語活動において、話し手は聞き手の解釈を促すために、既に導入済みの登場人物を後続の談話の中では異なった言語表現(固有名詞/名詞、代名詞、ゼロ代名詞)で指し示すことがある。このような同一の指示対象を指す表現を照応表現と呼ぶが、本研究は日本人英語学習者と英語母語話者(NS)によるストーリーテリングの中で用いられた照応表現の比較と分析を、関心の焦点と談話全体のまとまりのよさ(一貫性)の関係を規定しているセンタリングモデルの手法に基づいて行なったものである。
まず、最初にセンタリングモデルの発話の定義、中心の定義、中心の制約と規則、遷移のパタン(CONTINUE, RETAIN, SMOOTH-SHIFT, ROUGH-SHIFT)等についての説明がなされ、CONTINUEが多いのは一貫性の高い文で、CONTINUEが少ないのは一貫性の低い文であることが例文とともに示された。
被調査者は、昔話「桃太郎」を知っている、日本人英語学習者(初級、中級、上級、各10名)と英語母語話者(英、米、加など10名)から成り、「桃太郎」の絵(15枚)を見てストーリーを語る。研究はこれらのストーリーを録音し、文字化して分析したものである。
結果は、被調査者のグループごとに、それぞれの遷移パタンにおける①照応表現の出現頻度の平均とその割合②照応に関する名詞と(指示)代名詞の分布③照応関係を示す名詞・(指示)代名詞表現の種類と頻出の割合が示され、それぞれのデータごとに詳しい考察がなされた。
結論として、①各グループのストーリー展開における傾向は、全く異なるというのではなく、類似性が見られる。②初級、中級、上級、NSの順で、代名詞の使用が増加し、名詞の使用が減少する。つまり、英語学習者の場合は英語熟達度が高くなるほど、ゼロ代名詞や代名詞の使用が増加し、NSの使用に近づくことが示された。
さらに、センタリングモデルを用いての研究には、同じ英語能力を持つ人の発話を比較して、その中で一貫性の高さ低さを調べるのと異なり、英語のレベルが学習者とNS間、学習者間で異なる場合、発話内容が異なる可能性があることから、数値のみによる比較には限界があることにも言及された。例えば、CONTINUEは、一貫性の高さを示す一要因であるが、初級学習者におけるCONTINUEの多さは、わかりやすいが単調な文であることを示しているので注意が必要である、などである。
センタリングモデルに基づく照応表現の分析の発表は、丁寧に纏められたハンドアウトをもとに、手順よく説明された。今後の外国語学習や指導方法に有効な手がかりを与えるものと考えられる。(古田八恵 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 2-1
「高校オーラルAでの実践報告:プロモーションビデオの作成-プレゼンテーションソフトを利用して」
溝畑保之(大阪府立泉南高等学校)
本発表は、いわゆる困難校での画期的な取り組みを紹介するものであった。学習意欲が低く、生徒指導上の問題が頻発する高校にあって、ともすれば、何も問題が起こらず無難に授業が終わることだけを考えてしまいがちな教師集団の中で、その現状を打破し、悪循環から抜け出すために、長期的な指導計画のもとに実践されたすばらしい実践報告であった。具体的には、平成13年度のオーラルコミュニケーションのまとめの活動として、5名程度の小グループで、大阪を宣伝するビデオを作成するという実践である。対象生徒は英語学習に強い苦手意識を持つ普通高校1年生の40名クラス7学級であり、教室の吊り下げ式スクリーンに背景となる静止画像をプレゼンテーションソフト(PowerPoint)で提示し、生徒がその前で大阪のことを英語で語るというものである。
PowerPointと実践を記録したビデオで非常にわかりやすく発表されたが、この取り組みを通じて、生徒たちが着実に変わっていき、3学期の最後の発表では見事に英語でプレゼンテーションできるまでになる様子が生き生きと伝わってきた。発表を聞いていて、さながら1年間の感動的なドラマを見る思いがしたのは私だけではないであろう。
実践の内容をもう少し詳しく紹介しよう。まず、OCAは次のような年間計画により行われている。
1学期中間(自己紹介・TPR)<個人活動>⇒1学期期末(IRF・ポイント制)<受容的雰囲気の構築>⇒2学期中間(Video Watching)<個人活動>⇒2学期期末(Talk about Osaka)<ペア活動>⇒3学期期末(Promotion Video)<小グループ活動>
今回の実践発表は、この中の3学期の活動に焦点を当てたものであった。次に、3学期約10時間の流れを見てみよう。
モデルビデオ(教師がやってみせる)⇒日本語でのブレーンストーミング(生徒の発想を大切にする)⇒スクリプト・ライティング(アイデアを英語にする)⇒リハーサル(とにかくやらせてみる)⇒本番(自己評価)
さて、英語が嫌いで、苦手な生徒たちをどのようにして以上のような流れに乗せていくかが教師の力量の問われるところだが、溝端先生はそのためにさまざまな工夫を凝らされる。第1は、環境を変えること、即ち、空き教室でメディア機器を活用することである。第2は、内容を変える。即ち、生徒が協力しながら学べる参加型学習に切り替え、生徒の自己評価を取り入れる。さらに、具体的な指導方法として、英語だけで70%の内容理解を目指させる、自己表現・主張を奨励する、努力をほめる。おちこぼれを防ぐなどについてきめ細かい指導が行われる。
この実践を通じて、生徒全員が参加できたこと、生徒の英語学習に対する強い動機付けになったこと、英検受検者が急増したことなど、多くの成果が見られたことが最後に報告された。時間の関係で、質問が2つに限られたが、もっと詳しく聞きたい実践報告であった。(高田哲朗 京都教育大学教育学部附属高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 2-2
「様々な活動を取り入れたライティング指導」
龍池ちさと(大阪教育大学教育学部附属高等学校平野校舎)
教育実践で大切なことの一つは、これまでの実践をきっちり総括し、問題点を踏まえた上で、新たな実践を行うことだろう。このことは、雑用に追われる教育現場にあっては、実行するのはたいへん難しいことであるのは言うまでもない。今回の龍池先生の実践報告は、その困難なことをきっちり実行されており、毎年授業のレベルアップを図っておられることがよくわかる発表であった。たまたまALTとの話の中で、learn Englishとlearn about Englishが話題になり、自分の授業で生徒はlearn about Englishしかしていなかったのではないかという自己反省が出発点となり、それまで何となく自分でも不満を感じていたライティングの授業にメスを入れ、そこから新たな実践を始められたとのことであった。
それまでの授業の総括から浮かび上がってきた授業の問題点を、次のように整理されていた。
1)表現・構文・文法の一方的な説明になっていた。
2)単なる答え合わせの授業。
3)英語の運用面・音声指導の軽視。
4)生徒自身の活動や授業での習得量が少ない。
これらの問題点を少しでも改善するために、定型表現や重要構文を空欄にしたハンドアウトを用意してのペア・ワークや、音読練習の充実、Read & Look-upの実践、英作文の「解き方のテクニック」に焦点を当てたハンドアウト(自主教材)での学習などに取り組まれた。とりわけ、教科書の例文をアレンジして作られたペア・ワーク用のワークシートや、英作演習用のハンドアウトなどは、生徒が興味を持って取り組めるように、i+1の活動を取り入れた工夫されたものであった。ライティングの指導で付き物の添削の仕方については、一度で添削するのではなく、1回目は間違いの箇所だけ指摘し、生徒自身に気づかせるようにして、2回目に教師が添削するやり方をするとうまくいくようになったとの指摘があったが、筆者もcreative writingで同様の方法をとっているので、興味深かった。実際の授業の様子も、ペア・ワークの場面を中心にビデオで紹介された。発表は、高校2年と3年のライティングの両方での実践を報告される予定であったのだが、時間の関係で、3年についての発表は少ししか聞くことができず、発表自体も、途中で終わらねばならず、せっかく用意された報告のすべてを聞くことができなかったのは、非常に残念であった。(高田哲朗 京都教育大学教育学部附属高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 3-1
「児童英語指導に効果的な教材・歌の活用法」
小西千鶴子(同志社女子大学・非)
本発表は、小西氏の民間児童英会話学校での3年にわたる指導経験をもとにした実践報告である。
序論の概要:
1)2002年度からスタートする公立小学校での新しい英語教育環境は、教科としての英語授業導入ではなく、「総合的な学習の時間」に「外国語会話等」という位置付けで英語を取り上げることができる、という環境である。検定教科書やそれに伴うカリキュラムがないための問題も想定される一方、一定の教え方やカリキュラムの進度に制約されずに、児童生徒の特性や進度にあわせて授業を構築できる長所がある。指導者の力量が大きく問われることにもなる。
2)文部科学省の所謂「体験的学習要素を含み音声中心の指導をねらいとした英語活動を行う」にあたり、"Who teaches What and How by using What kind of materials?" が問題となる。
実践の概要:
1)「英語活動」のねらい:
(i) コミュニケーション能力・運用能力重視
(ii) (異文化)体験的学習要素を中心とする活動
(iii) こどもの日常生活に身近な英語を扱う。
2)音声中心:英語の歌、カード、ゲーム、紙芝居、アクションを伴う諸活動を、Play with language の要素を取り入れて行う。
3)TPR を活用し、instruction はすべて英語で行う。文字は教えないが、歌に関連して文字カードを「認識レベル」で導入する。歌の一部の substitution 活動も取り入れる。
4)レッスンプランの一例(1時間分)
クラス:7名(小1-4、小2-3)週1回1時間
1. Warming up (ハローソング)
2. Review :I like/don't like~. Yes, I do./No, I don't.
3. 宿題チェック(自分の声を録音)
4. 本日のテーマ:お話的要素を含むカード⇒Do you like ?
5. カードゲーム・アクションを伴うゲーム、歌
6. A) 言語材料:「好き/嫌い」の言い方や can/can't
B) コミュニケーション:自分の好き嫌い他
7. Wrapping up:学んだことに関連する歌を歌う
8. Good-bye song
上記レッスンのビデオが紹介され、生徒達が生き生きと、元気よく英語活動をしている様子や、先生が活力あふれるインタラクションによってclass dynamicsの創造に成功されている様子が理解できた。歌を、既習事項やその日の学習事項とからめて効果的に活用、同じ歌でも低学年/高学年向きにリサイクルする工夫等示唆に富む実践報告であった。(弓庭喜和子 大阪外国語大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 1
「TPR再評価:中学高校授業への応用」
黒川愛子(宇治市立北宇治中学校)
鈴木寿一(京都教育大学)
まず、鈴木先生によってTPRによる指導理論の説明がなされた。ご自分の高等学校での実践なども踏まえて、一般的に初級用とされているTPRが実は大人に効果があることや、即時反応を確かめながら学習が進むという言語学習の根幹をついた教授法であることをAsherの一連の研究に触れながら説明された。
次に、鈴木先生考案の人工語を使用し、実演者を募り、約10分で実際の指導を行った。最初は指示を出しながら教師が一緒に動作を行い生徒がそれをまねる。できるようになったころを見計らって、教師が動作を遅らせていくなどのコツを実演された。随時、「生徒が間違うのは指導が悪い」や「先を急がない」などの注意をはさみながらデモンステレーションは楽しい雰囲気で進んだ。
その後、黒川先生が、勤務されている中学校での指導法と実験結果を紹介された。アルファベットの指導では、表面にA~Z,裏面が対応するイラストのあるカードを使用した。鋏を使用しCut A Card. とカードを切らせた後、 Write your name on it. Put Card B on the desk. Put Card C next to Card D.などの指示で学習者が動くという指導である。この入門期の約16時間の指導を、従来のテキストに基づいた指導と比較すると、使用単語数や文の数がはるかに多いことが示された。さらに、実験結果としては、実験群と統制群で、listening、written testの両方に効果が確認された。さらに、他学年との比較もされ、listeningにおいては1年が2年に優ることが確認できた上に、written testでも1年間の学習差を越える影響があったことが報告された。
続いて、教室での生徒の様子をビデオで紹介され、アンケートによる生徒の反応としては、塾通いの生徒に最初見られた違和感が、指導が継続されるに従って減少することや、あきらめがちの生徒が授業中に生き生きとデモに参加することも挙げられた。
さらに、鈴木先生から吉岡先生(京都私立西京商業高校)のTPRを利用した語彙と文法の指導とその成果について説明があった。TPRの指導を受けた生徒が予想以上に高度の文法の発見型学習ができた事例も紹介された。
最後には、フロアーを小グループに分け、現在進行形・過去進行形・助動詞などの文法事項やdiagonallyやabbreviateなどの語彙をいかにTPRで指導するかを考案するディスカションを行った。各グループから全体への発表をし、中学高校でのTPRの応用を模索してワークショップを締めくくった。(溝畑保之 泉南高校)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 2
「小学校英語、こんなふうにやってみたら」
直山木綿子(京都市立永松記念教育センター)
事務局から直山先生のワークショップの報告を書くように依頼された時は、正直困った。今こうして書いている間も、やはりお断りした方がよかったのではという思いが心のどこかにある。というのも、先生のお話の面白さを伝える力量は私にはないから。それくらい直山先生の話はいつ聞いてもとにかく面白い。先生は今、永松記念教育センター研究課にいらっしゃる。これは、教育委員会に当たる所とか。ということは、直山先生はすごく偉い方なのだ。でも、その偉さを感じさせないところが直山先生らしいところだと、常日頃から小生は思っている。先生は同女のご出身で、中学校で教鞭を執ること10数年、その後永松に移られたとの由。永松は今年で5年目ということである。
それでは、ワークショップの始まり始まり。直山先生は、Hello, hello, what is your name? と口ずさみつつ、ぬいぐるみ片手に参加者の中へ。ぬいぐるみは生徒の緊張ほぐすため。Suggestopediaにも通ずるこの手法、なかなか心憎い。次は、絵本の読み聞かせ。Brown bear, Brown bear, what do you see? リズムに乗せて話は進む。先生の話を聞きながらこう考えた。リズムは、ことばをひとつにまとめる不思議な力。細かいことは気にしなくても大丈夫。さて、その次は、3つのヒントで答を見つけるスリーヒントクイズに関するお話。子供たちに大人気、FLTも大興奮。でも担任は冷静に、生徒たちの活動に細心の注意を払っている。そこで一言、直山先生。やっぱり担任は、小学校の英語活動に必要不可欠。なるほど同感。次に登場するのは、Bongo。数の代わりに絵を使う、ビンゴもどきの楽しいゲーム。ペアでおはじき5個ずつ持ち、先生の声に合わせて、絵の上におはじき載せて競い合う。どっちが先になくなるか、知らぬ間に大興奮。音と意味とを結びつけ、楽しく学んでしっかり覚える工夫がいい。その後は、生徒たちによる学校紹介のお話。低学年は、FLT相手に学校案内。高学年は、絵に描いた学校の施設を英語で表現。実際の経験に即したこの活動、母語獲得に似ていて面白い。そして最後は合作絵。部分から成る絵を組み合わせ、全体で意味のある絵を創り出す。一枚一枚違う絵が集まって、一枚の絵の出来上がり。このことが、国際理解へ通じる道だと、直山先生。
紙面の関係で割愛させていただいた部分もあるが、小生の印象に残った部分を中心に、ワークショップの再構成を試みた。先生が小学校の英語に期待されていることを一口で表すのは難しい。ただ、お話を伺う中で、ことばの形式よりも機能や意味を大切にされているという印象を強く受けた。このことは、生きたことばとしての英語に触れることが大切という先生からのメッセージではないかと小生は感じている。上記のような活動を基に、京都市内の小学校における英語活動が円滑に行われるよう、直山先生はユニットボックスと呼ばれる教材を作成され、希望される先生方には貸し出されていることを最後に記して、筆を置くことにする。井狩幸男(大阪市立大学)
--------------------------------------------------------------------------------
「会場校を引き受けて」
枝澤康代(同志社女子大学)
2002年度のLET関西支部春季研究大会を同志社女子大学京田辺キャンパスで開催できたことは、大変光栄であり、嬉しいことでした。特に、鮮やかな紅色の五月が一面に咲いた本学の最も美しい季節に、皆様をお迎え出来たことは大きな喜びでした。
本学は京都の最南端にあり、神戸、大阪、京都からも遠い場所にありますので、参加者が少ないのではないかと心配でしたが、基調講演、シンポジウム、2つのワークショップ、5つの研究発表・実践報告という充実したプログラムのお陰で、100名を越す参加者を迎えることができました。
会場校を引き受けて悩むのは、受付と発表会場、業者展示、懇親会場などの割り振りです。部屋数だけは充分にありましたが、来場者の導線を考え、また各部屋の設備を考え、何度も変更しました。最終的には、業者展示と休憩所を中心にして、左右に発表会場を分けましたが、かなりうまく行ったのではないかと思います。吉田晴世事務局長には、事前に下見に来てくださり、いろいろ相談に乗っていただき感謝でした。
展示については、いつもよりも多い9社の申し込みがあり、嬉しい悲鳴でした。電気容量は大丈夫か、コンセントの数は足りるかと、ひやひやしました。できるだけオープンなスペースで、それぞれの展示がなるべく離れない場所を考えましたので、少し狭い感がありましたが、多くの人が集まってくださり、よい情報交換と交わりの場となったのではないかと思います。
さらに、ランチタイムの短時間ではありましたが、本学情報メディア学科の新しいコンセプトによる情報処理教室と情報教育サポートセンターをご案内でき、良かったと思います。担当くださった情報メディア学科の川田隆雄先生に厚く御礼申し上げます。
懇親会にも、多くの方々が残ってくださり、楽しい時を持つことができました。しかし、本学は学内禁酒となっているため、ノンアルコールの懇親会となり、皆様に物足りない思いをさせたことは残念でした。近くのホテルでの開催も考えたのですが、移動時間と費用の点から断念しました。一方では、懇親会費を低料金に押さえることができて、よかったかもしれません。
最後に、会場準備に当たっては、できるだけの準備をしたつもりですが、足りない点も多々ありましたことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。しかし、関西支部事務局の強力な応援と、若本夏美先生、佐伯林規江先生、三根浩先生を始め、本学卒業生であるLET会員の先生方、卒業生と在学生からなるアルバイト、そして本学施設課の一致協力のお陰で、無事に2002年度春季大会を終えることができ心から感謝しています。ありがとうございました。
「学校教育におけるe-Learning」
梶田将司(名古屋大学情報連携基盤センター助教授)
最近では、コンピュータやインターネット等を利用した学習のことを総称して「e-Learning」などと呼ぶことがある。しかしながら、「e-Learning」のプラットフォームやシステムには多様なものがあり、それらを利用するためには、教師、学習者共にまずその使用方法を学ばなければならないという問題が出てくることも多い。そこで、「e-Learning」による学習・教育のプラットフォームを同じものに統一して利便性を高めるという「標準化」の必要性が叫ばれてきている。今回の講演は、そういった「標準化」の流れに沿った「e-Learning」のシステムの一つであり、北米の大学で50%以上のシェアを持つとされているWebCT(Web Course Tool)についての講演であった。講師の梶田先生は、カナダのUBC(University of British Columbia)で開発されたWebCTを日本語対応にローカライズする作業に携わってこられた方で、日本におけるWebCTの第一人者である。
梶田先生からは、現在WebCTを利用している教育機関は、日本を含めて84カ国2600箇所以上であり、1000万人以上が利用しているといった利用実態が解説され、専門的な知識がそれほど無くても、小テストや掲示板、チャットなどのシステムをWebページ上に構築でき、学習履歴の記録や成績管理も可能、といったWebCTの利点が述べられた。講演の途中では、WebCT利用法の解説ビデオやWebCTの開発者であるUBCのMurray Goldberg氏からの開発の経緯が述べられたメッセージビデオが流されると共に、PowerPointとストリーミングビデオを時間軸の同期を取って提示するシステムのデモンストレーションなども行われ、WebCTというシステムを具体的に理解することができた。梶田先生からは、WebCTのようなコース管理システム導入の利点として、1)教育内容の改善が容易になる(学生の声に基づいた改善)、2)教育内容の公開が容易になる(他の先生との教材やノウハウの共有が可能)、3)教育内容の履歴作りが容易になる(教育実践の客観評価)、4)教育内容の引き継ぎが容易になる、といった点が述べられた。フロアからは、名古屋大学内での利用状況はどのようなものか、教員への利用ガイダンスや支援体制はどうなっているか、他の同類のシステムと比較した場合のWebCTの特徴は何か、といった質問がなされ、多くの関心が寄せられた講演であった。(杉森直樹 大阪電気通信大学)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジウム
「大学教授でいる方法:あなたの商品開発、品質管理、CS対策は万全ですか」
東 淳一(流通科学大学)
青木幹生(関西国際大学・非)
野村和宏(流通科学大学)
本シンポジウムはLET関西支部の大学授業研究部会によって企画されたものである。演題には経営学やマーケティング関係の用語が用いられており、一見「教育」と馴染まないかに見える。しかしパネリストの各提案を通じて、ビジネスにおける考え方が教育実践においても参考になる点が多々あることがわかった。
まず野村氏は、ユーモアを交えながらも大学教員の勤務実態を批判的にながめた上で、「いつ誰に見てもらってもいい」という授業を行うことの必要性を主張され、授業というものは常に公開が前提であり、教師は public speaker としての自覚を持つべきだとの持論を展開された。Public Speaker としても経験豊富な氏は、授業を質的に高めるためには、教師は自らを第三者的にながめる必要があり、そのためには自分の授業をビデオ録画するといった方法が有効であるとの具体的提案を行なわれた。
東氏は、マーケティングの考えを導入して、顧客としての学生のニーズを満たすような授業、すなわちCS(Customer Satisfaction)に応える授業を行うためには、教育目標に沿った教材開発(商品開発)や授業内容の保証(品質管理)といったことが必要だとの主張をされた。この点で大学教育は問題を抱えており、その解決には企業経営におけるknowledge managementという考え方が有効であると述べられた。そして、各教員(あるいは教員集団)の授業に関するノウハウや知識を共有するために、公開授業を積極的に行っていくべきだとの提案を行なわれた。
青木氏は、両者の提案を踏まえて、ビジネス界におけるマネイジメント経験者の立場から授業改善への提言をされた。教育界における教育目標は企業では利潤(数値目標)に相当し、シラバスは事業計画に、そして授業は営業活動に相当すると考えられるが、企業では数値がすべてであるという厳しい側面を紹介された。そして学校教育を請負業務だと考えるなら、しかるべき責任(すなわち教育目標の達成)を果たすべきだと述べられた。なお氏は学校教育が企業のように数値目標の達成を目指すべきだと言っているのでは当然ない。最後に氏は、大学では学生の卒業後を見据えて社会教育を行っていく必要性があるのではないかとの提案をされた。
今回のシンポジウムでは、授業の質を高めて教育目標を達成するには、教員が知識やノウハウを共有することが大切であり、そのためにはそれぞれがさまざまな方法で授業を公開すべきであるという点が確認できた。また、一教員である筆者にとってはしっかりした職業意識を持つことの意味を考えさせられる機会でもあった。(神崎和男 大阪電気通信大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 1-1
“Welcome Back to My Classroom: Self-Assessment, Responsibility and Freedom in Communicative English”
Andrew Obermeier (Kyoto University of Education)
Classroom procedures for communicative English classes for English majors were described in this presentation which included video clips of student interactions. Obermeier uses a 4-5 week teaching cycle: Week 1, diagnostic pre-test and cooperative setting of unit objectives between the students and the teacher; Weeks 2-4, free-talking warm-up session, focused communicative grammar work, highly focused grammar homework, student reflection on the learning process, and teacher reflection on the course activities; Week 5, criterion-referenced oral test based on the objectives agreed upon at the start of the cycle. The course is aimed at having students actively use English among themselves and also at involving them in the learning and assessment process as most intend to become schoolteachers in the future. To help realize these aims, photo sheets are prepared at the beginning of the class with snapshots of the students taken by other students. During the free-talking warm-up session, each student talks with another student and the two sign each other’s photo sheet to keep a record of the interaction. Students must try to chat with every other student by the end of the cycle. The classroom grammar work is taught using photocopiable material to wean the students away from reliance on textbooks. For homework, they use workbooks and supplementary materials. In the reflection portion of the cycle, the students record their reactions to the lesson in learning logs and assign numerical ranking (1 to 5, which is the best grade) to describe how interesting and useful the activities were. This helps make them aware of their own learning process. Obermeier himself, as the teacher, also reflects upon the class activities and tries to describe the critical aspects of the lesson with specific details, analyze his own behavior and then decide upon future action. He uses a teacher trainer rubric to aid this reflection process. The active classroom video clips attested to the success of this approach which involves active student participation in the goal setting and classroom activities to lower the students’affective filter and encourage a positive attitude toward using English with their peers. The teacher’s focused reflection and analysis after each lesson plus student feedback via their learning logs should be very effective for promoting a positive spiral of raising awareness of the learning process and contributing to the language learning itself. (Judy Noguchi Mukogawa Women's University)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 1-2
「英語学習者のストーリーテリングにおける照応表現」
谷村 緑(大阪外国語大学大学院生)
日常の言語活動において、話し手は聞き手の解釈を促すために、既に導入済みの登場人物を後続の談話の中では異なった言語表現(固有名詞/名詞、代名詞、ゼロ代名詞)で指し示すことがある。このような同一の指示対象を指す表現を照応表現と呼ぶが、本研究は日本人英語学習者と英語母語話者(NS)によるストーリーテリングの中で用いられた照応表現の比較と分析を、関心の焦点と談話全体のまとまりのよさ(一貫性)の関係を規定しているセンタリングモデルの手法に基づいて行なったものである。
まず、最初にセンタリングモデルの発話の定義、中心の定義、中心の制約と規則、遷移のパタン(CONTINUE, RETAIN, SMOOTH-SHIFT, ROUGH-SHIFT)等についての説明がなされ、CONTINUEが多いのは一貫性の高い文で、CONTINUEが少ないのは一貫性の低い文であることが例文とともに示された。
被調査者は、昔話「桃太郎」を知っている、日本人英語学習者(初級、中級、上級、各10名)と英語母語話者(英、米、加など10名)から成り、「桃太郎」の絵(15枚)を見てストーリーを語る。研究はこれらのストーリーを録音し、文字化して分析したものである。
結果は、被調査者のグループごとに、それぞれの遷移パタンにおける①照応表現の出現頻度の平均とその割合②照応に関する名詞と(指示)代名詞の分布③照応関係を示す名詞・(指示)代名詞表現の種類と頻出の割合が示され、それぞれのデータごとに詳しい考察がなされた。
結論として、①各グループのストーリー展開における傾向は、全く異なるというのではなく、類似性が見られる。②初級、中級、上級、NSの順で、代名詞の使用が増加し、名詞の使用が減少する。つまり、英語学習者の場合は英語熟達度が高くなるほど、ゼロ代名詞や代名詞の使用が増加し、NSの使用に近づくことが示された。
さらに、センタリングモデルを用いての研究には、同じ英語能力を持つ人の発話を比較して、その中で一貫性の高さ低さを調べるのと異なり、英語のレベルが学習者とNS間、学習者間で異なる場合、発話内容が異なる可能性があることから、数値のみによる比較には限界があることにも言及された。例えば、CONTINUEは、一貫性の高さを示す一要因であるが、初級学習者におけるCONTINUEの多さは、わかりやすいが単調な文であることを示しているので注意が必要である、などである。
センタリングモデルに基づく照応表現の分析の発表は、丁寧に纏められたハンドアウトをもとに、手順よく説明された。今後の外国語学習や指導方法に有効な手がかりを与えるものと考えられる。(古田八恵 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 2-1
「高校オーラルAでの実践報告:プロモーションビデオの作成-プレゼンテーションソフトを利用して」
溝畑保之(大阪府立泉南高等学校)
本発表は、いわゆる困難校での画期的な取り組みを紹介するものであった。学習意欲が低く、生徒指導上の問題が頻発する高校にあって、ともすれば、何も問題が起こらず無難に授業が終わることだけを考えてしまいがちな教師集団の中で、その現状を打破し、悪循環から抜け出すために、長期的な指導計画のもとに実践されたすばらしい実践報告であった。具体的には、平成13年度のオーラルコミュニケーションのまとめの活動として、5名程度の小グループで、大阪を宣伝するビデオを作成するという実践である。対象生徒は英語学習に強い苦手意識を持つ普通高校1年生の40名クラス7学級であり、教室の吊り下げ式スクリーンに背景となる静止画像をプレゼンテーションソフト(PowerPoint)で提示し、生徒がその前で大阪のことを英語で語るというものである。
PowerPointと実践を記録したビデオで非常にわかりやすく発表されたが、この取り組みを通じて、生徒たちが着実に変わっていき、3学期の最後の発表では見事に英語でプレゼンテーションできるまでになる様子が生き生きと伝わってきた。発表を聞いていて、さながら1年間の感動的なドラマを見る思いがしたのは私だけではないであろう。
実践の内容をもう少し詳しく紹介しよう。まず、OCAは次のような年間計画により行われている。
1学期中間(自己紹介・TPR)<個人活動>⇒1学期期末(IRF・ポイント制)<受容的雰囲気の構築>⇒2学期中間(Video Watching)<個人活動>⇒2学期期末(Talk about Osaka)<ペア活動>⇒3学期期末(Promotion Video)<小グループ活動>
今回の実践発表は、この中の3学期の活動に焦点を当てたものであった。次に、3学期約10時間の流れを見てみよう。
モデルビデオ(教師がやってみせる)⇒日本語でのブレーンストーミング(生徒の発想を大切にする)⇒スクリプト・ライティング(アイデアを英語にする)⇒リハーサル(とにかくやらせてみる)⇒本番(自己評価)
さて、英語が嫌いで、苦手な生徒たちをどのようにして以上のような流れに乗せていくかが教師の力量の問われるところだが、溝端先生はそのためにさまざまな工夫を凝らされる。第1は、環境を変えること、即ち、空き教室でメディア機器を活用することである。第2は、内容を変える。即ち、生徒が協力しながら学べる参加型学習に切り替え、生徒の自己評価を取り入れる。さらに、具体的な指導方法として、英語だけで70%の内容理解を目指させる、自己表現・主張を奨励する、努力をほめる。おちこぼれを防ぐなどについてきめ細かい指導が行われる。
この実践を通じて、生徒全員が参加できたこと、生徒の英語学習に対する強い動機付けになったこと、英検受検者が急増したことなど、多くの成果が見られたことが最後に報告された。時間の関係で、質問が2つに限られたが、もっと詳しく聞きたい実践報告であった。(高田哲朗 京都教育大学教育学部附属高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 2-2
「様々な活動を取り入れたライティング指導」
龍池ちさと(大阪教育大学教育学部附属高等学校平野校舎)
教育実践で大切なことの一つは、これまでの実践をきっちり総括し、問題点を踏まえた上で、新たな実践を行うことだろう。このことは、雑用に追われる教育現場にあっては、実行するのはたいへん難しいことであるのは言うまでもない。今回の龍池先生の実践報告は、その困難なことをきっちり実行されており、毎年授業のレベルアップを図っておられることがよくわかる発表であった。たまたまALTとの話の中で、learn Englishとlearn about Englishが話題になり、自分の授業で生徒はlearn about Englishしかしていなかったのではないかという自己反省が出発点となり、それまで何となく自分でも不満を感じていたライティングの授業にメスを入れ、そこから新たな実践を始められたとのことであった。
それまでの授業の総括から浮かび上がってきた授業の問題点を、次のように整理されていた。
1)表現・構文・文法の一方的な説明になっていた。
2)単なる答え合わせの授業。
3)英語の運用面・音声指導の軽視。
4)生徒自身の活動や授業での習得量が少ない。
これらの問題点を少しでも改善するために、定型表現や重要構文を空欄にしたハンドアウトを用意してのペア・ワークや、音読練習の充実、Read & Look-upの実践、英作文の「解き方のテクニック」に焦点を当てたハンドアウト(自主教材)での学習などに取り組まれた。とりわけ、教科書の例文をアレンジして作られたペア・ワーク用のワークシートや、英作演習用のハンドアウトなどは、生徒が興味を持って取り組めるように、i+1の活動を取り入れた工夫されたものであった。ライティングの指導で付き物の添削の仕方については、一度で添削するのではなく、1回目は間違いの箇所だけ指摘し、生徒自身に気づかせるようにして、2回目に教師が添削するやり方をするとうまくいくようになったとの指摘があったが、筆者もcreative writingで同様の方法をとっているので、興味深かった。実際の授業の様子も、ペア・ワークの場面を中心にビデオで紹介された。発表は、高校2年と3年のライティングの両方での実践を報告される予定であったのだが、時間の関係で、3年についての発表は少ししか聞くことができず、発表自体も、途中で終わらねばならず、せっかく用意された報告のすべてを聞くことができなかったのは、非常に残念であった。(高田哲朗 京都教育大学教育学部附属高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 3-1
「児童英語指導に効果的な教材・歌の活用法」
小西千鶴子(同志社女子大学・非)
本発表は、小西氏の民間児童英会話学校での3年にわたる指導経験をもとにした実践報告である。
序論の概要:
1)2002年度からスタートする公立小学校での新しい英語教育環境は、教科としての英語授業導入ではなく、「総合的な学習の時間」に「外国語会話等」という位置付けで英語を取り上げることができる、という環境である。検定教科書やそれに伴うカリキュラムがないための問題も想定される一方、一定の教え方やカリキュラムの進度に制約されずに、児童生徒の特性や進度にあわせて授業を構築できる長所がある。指導者の力量が大きく問われることにもなる。
2)文部科学省の所謂「体験的学習要素を含み音声中心の指導をねらいとした英語活動を行う」にあたり、"Who teaches What and How by using What kind of materials?" が問題となる。
実践の概要:
1)「英語活動」のねらい:
(i) コミュニケーション能力・運用能力重視
(ii) (異文化)体験的学習要素を中心とする活動
(iii) こどもの日常生活に身近な英語を扱う。
2)音声中心:英語の歌、カード、ゲーム、紙芝居、アクションを伴う諸活動を、Play with language の要素を取り入れて行う。
3)TPR を活用し、instruction はすべて英語で行う。文字は教えないが、歌に関連して文字カードを「認識レベル」で導入する。歌の一部の substitution 活動も取り入れる。
4)レッスンプランの一例(1時間分)
クラス:7名(小1-4、小2-3)週1回1時間
1. Warming up (ハローソング)
2. Review :I like/don't like~. Yes, I do./No, I don't.
3. 宿題チェック(自分の声を録音)
4. 本日のテーマ:お話的要素を含むカード⇒Do you like ?
5. カードゲーム・アクションを伴うゲーム、歌
6. A) 言語材料:「好き/嫌い」の言い方や can/can't
B) コミュニケーション:自分の好き嫌い他
7. Wrapping up:学んだことに関連する歌を歌う
8. Good-bye song
上記レッスンのビデオが紹介され、生徒達が生き生きと、元気よく英語活動をしている様子や、先生が活力あふれるインタラクションによってclass dynamicsの創造に成功されている様子が理解できた。歌を、既習事項やその日の学習事項とからめて効果的に活用、同じ歌でも低学年/高学年向きにリサイクルする工夫等示唆に富む実践報告であった。(弓庭喜和子 大阪外国語大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 1
「TPR再評価:中学高校授業への応用」
黒川愛子(宇治市立北宇治中学校)
鈴木寿一(京都教育大学)
まず、鈴木先生によってTPRによる指導理論の説明がなされた。ご自分の高等学校での実践なども踏まえて、一般的に初級用とされているTPRが実は大人に効果があることや、即時反応を確かめながら学習が進むという言語学習の根幹をついた教授法であることをAsherの一連の研究に触れながら説明された。
次に、鈴木先生考案の人工語を使用し、実演者を募り、約10分で実際の指導を行った。最初は指示を出しながら教師が一緒に動作を行い生徒がそれをまねる。できるようになったころを見計らって、教師が動作を遅らせていくなどのコツを実演された。随時、「生徒が間違うのは指導が悪い」や「先を急がない」などの注意をはさみながらデモンステレーションは楽しい雰囲気で進んだ。
その後、黒川先生が、勤務されている中学校での指導法と実験結果を紹介された。アルファベットの指導では、表面にA~Z,裏面が対応するイラストのあるカードを使用した。鋏を使用しCut A Card. とカードを切らせた後、 Write your name on it. Put Card B on the desk. Put Card C next to Card D.などの指示で学習者が動くという指導である。この入門期の約16時間の指導を、従来のテキストに基づいた指導と比較すると、使用単語数や文の数がはるかに多いことが示された。さらに、実験結果としては、実験群と統制群で、listening、written testの両方に効果が確認された。さらに、他学年との比較もされ、listeningにおいては1年が2年に優ることが確認できた上に、written testでも1年間の学習差を越える影響があったことが報告された。
続いて、教室での生徒の様子をビデオで紹介され、アンケートによる生徒の反応としては、塾通いの生徒に最初見られた違和感が、指導が継続されるに従って減少することや、あきらめがちの生徒が授業中に生き生きとデモに参加することも挙げられた。
さらに、鈴木先生から吉岡先生(京都私立西京商業高校)のTPRを利用した語彙と文法の指導とその成果について説明があった。TPRの指導を受けた生徒が予想以上に高度の文法の発見型学習ができた事例も紹介された。
最後には、フロアーを小グループに分け、現在進行形・過去進行形・助動詞などの文法事項やdiagonallyやabbreviateなどの語彙をいかにTPRで指導するかを考案するディスカションを行った。各グループから全体への発表をし、中学高校でのTPRの応用を模索してワークショップを締めくくった。(溝畑保之 泉南高校)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 2
「小学校英語、こんなふうにやってみたら」
直山木綿子(京都市立永松記念教育センター)
事務局から直山先生のワークショップの報告を書くように依頼された時は、正直困った。今こうして書いている間も、やはりお断りした方がよかったのではという思いが心のどこかにある。というのも、先生のお話の面白さを伝える力量は私にはないから。それくらい直山先生の話はいつ聞いてもとにかく面白い。先生は今、永松記念教育センター研究課にいらっしゃる。これは、教育委員会に当たる所とか。ということは、直山先生はすごく偉い方なのだ。でも、その偉さを感じさせないところが直山先生らしいところだと、常日頃から小生は思っている。先生は同女のご出身で、中学校で教鞭を執ること10数年、その後永松に移られたとの由。永松は今年で5年目ということである。
それでは、ワークショップの始まり始まり。直山先生は、Hello, hello, what is your name? と口ずさみつつ、ぬいぐるみ片手に参加者の中へ。ぬいぐるみは生徒の緊張ほぐすため。Suggestopediaにも通ずるこの手法、なかなか心憎い。次は、絵本の読み聞かせ。Brown bear, Brown bear, what do you see? リズムに乗せて話は進む。先生の話を聞きながらこう考えた。リズムは、ことばをひとつにまとめる不思議な力。細かいことは気にしなくても大丈夫。さて、その次は、3つのヒントで答を見つけるスリーヒントクイズに関するお話。子供たちに大人気、FLTも大興奮。でも担任は冷静に、生徒たちの活動に細心の注意を払っている。そこで一言、直山先生。やっぱり担任は、小学校の英語活動に必要不可欠。なるほど同感。次に登場するのは、Bongo。数の代わりに絵を使う、ビンゴもどきの楽しいゲーム。ペアでおはじき5個ずつ持ち、先生の声に合わせて、絵の上におはじき載せて競い合う。どっちが先になくなるか、知らぬ間に大興奮。音と意味とを結びつけ、楽しく学んでしっかり覚える工夫がいい。その後は、生徒たちによる学校紹介のお話。低学年は、FLT相手に学校案内。高学年は、絵に描いた学校の施設を英語で表現。実際の経験に即したこの活動、母語獲得に似ていて面白い。そして最後は合作絵。部分から成る絵を組み合わせ、全体で意味のある絵を創り出す。一枚一枚違う絵が集まって、一枚の絵の出来上がり。このことが、国際理解へ通じる道だと、直山先生。
紙面の関係で割愛させていただいた部分もあるが、小生の印象に残った部分を中心に、ワークショップの再構成を試みた。先生が小学校の英語に期待されていることを一口で表すのは難しい。ただ、お話を伺う中で、ことばの形式よりも機能や意味を大切にされているという印象を強く受けた。このことは、生きたことばとしての英語に触れることが大切という先生からのメッセージではないかと小生は感じている。上記のような活動を基に、京都市内の小学校における英語活動が円滑に行われるよう、直山先生はユニットボックスと呼ばれる教材を作成され、希望される先生方には貸し出されていることを最後に記して、筆を置くことにする。井狩幸男(大阪市立大学)
--------------------------------------------------------------------------------
「会場校を引き受けて」
枝澤康代(同志社女子大学)
2002年度のLET関西支部春季研究大会を同志社女子大学京田辺キャンパスで開催できたことは、大変光栄であり、嬉しいことでした。特に、鮮やかな紅色の五月が一面に咲いた本学の最も美しい季節に、皆様をお迎え出来たことは大きな喜びでした。
本学は京都の最南端にあり、神戸、大阪、京都からも遠い場所にありますので、参加者が少ないのではないかと心配でしたが、基調講演、シンポジウム、2つのワークショップ、5つの研究発表・実践報告という充実したプログラムのお陰で、100名を越す参加者を迎えることができました。
会場校を引き受けて悩むのは、受付と発表会場、業者展示、懇親会場などの割り振りです。部屋数だけは充分にありましたが、来場者の導線を考え、また各部屋の設備を考え、何度も変更しました。最終的には、業者展示と休憩所を中心にして、左右に発表会場を分けましたが、かなりうまく行ったのではないかと思います。吉田晴世事務局長には、事前に下見に来てくださり、いろいろ相談に乗っていただき感謝でした。
展示については、いつもよりも多い9社の申し込みがあり、嬉しい悲鳴でした。電気容量は大丈夫か、コンセントの数は足りるかと、ひやひやしました。できるだけオープンなスペースで、それぞれの展示がなるべく離れない場所を考えましたので、少し狭い感がありましたが、多くの人が集まってくださり、よい情報交換と交わりの場となったのではないかと思います。
さらに、ランチタイムの短時間ではありましたが、本学情報メディア学科の新しいコンセプトによる情報処理教室と情報教育サポートセンターをご案内でき、良かったと思います。担当くださった情報メディア学科の川田隆雄先生に厚く御礼申し上げます。
懇親会にも、多くの方々が残ってくださり、楽しい時を持つことができました。しかし、本学は学内禁酒となっているため、ノンアルコールの懇親会となり、皆様に物足りない思いをさせたことは残念でした。近くのホテルでの開催も考えたのですが、移動時間と費用の点から断念しました。一方では、懇親会費を低料金に押さえることができて、よかったかもしれません。
最後に、会場準備に当たっては、できるだけの準備をしたつもりですが、足りない点も多々ありましたことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。しかし、関西支部事務局の強力な応援と、若本夏美先生、佐伯林規江先生、三根浩先生を始め、本学卒業生であるLET会員の先生方、卒業生と在学生からなるアルバイト、そして本学施設課の一致協力のお陰で、無事に2002年度春季大会を終えることができ心から感謝しています。ありがとうございました。