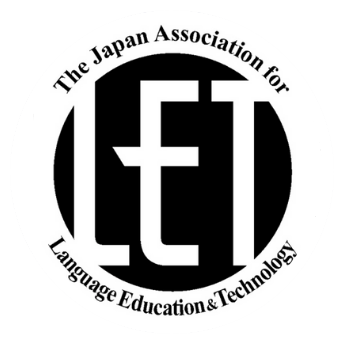大会名
00年度春季研究大会
大会(春・秋・全国)
春季大会
日付
2000年5月27日
会場
大阪市立大学
概要
00年度春季大会は、2000年5月27日(土) 09:30よりに大阪市立大学学術情報総合センター(大阪市住吉区杉本)でおこなわれました。講演では、先頃、京都教育大学を退官された斉藤栄一先生(平安女学院大学)を迎え、「今の英語教育に欠けているもの:実践的コミュニケ-ションをめざして」と題してお話頂きました。さらに、Internetと外国語教育の分野で著名なRobb, T.先生(京都産業大学)には、Click and Read? Using the Internet for reading practiceと題したレクチャーを、また、オーストリア留学から帰国された運営委員の東淳一先生(流通科学大学)には「先進メディアは「知識処理」時代の教育に貢献できるか」のタイトルで帰朝報告をしていただきました。これ以外にも、実践報告、研究発表3件および懇親会がおこなわれました。詳細は下記の報告をご覧ください。なお、この日には合わせて支部総会も開催され、支部長、副支部長、理事、運営委員の選出、予算の報告、決算の報告などがなされました。
詳細
帰朝報告
「先進メディアは『知識処理』時代の教育に貢献できるか」
東 淳一(流通科学大学)
東先生は1998年秋から約1年間オーストリアのグラーツ工科大学に客員研究員として赴任され、今回は当地での研究成果の一端として、先進メディアと教育について報告された。難解なインターネット用語が多く出てきたので 消化不良のところもあるが、パワーポイントで作成した様々な図表を駆使して教育に関する多くの情報と示唆を与えて頂いた。以下に簡単に内容を紹介したい。
今日、WWWは様々な教育現場で利用されており、Webに関連した技術も大きく進化し、多彩なオーサリングと情報配信が可能になってきた。しかし、Webの専門家ではない教育者が、魅力あるWebサイトを管理・運営していくのは至難のわざである。オーサリングの多様性の問題も含め、Webそのものは多くの問題を抱えている。コンテンツとナビゲーション用インタフェースの混同の問題、検索の困難性の問題、ハイパーリンクの一方向性の問題、URL指定におけるオブジェクト名と場所の混同の問題、ハイパーテクストのナビゲーションと内容理解度に関する問題などを挙げることができる。
データは情報の断片で あり、通常意味は付与されないが、情報はデータの集積であり、意味や価値が付与される。また、知識とは経験、認識、判断力、あるいは推理力、熟練した技術など、人間内部に存在するものであり、簡単に明示化されるとは限らず、不安定で管理しにくいものである。 現在、世界中の無数のコンピュータがネットワークで結びついているが、生産性が劇的に向上したとは思えない。その理由は単純な情報が内包されたファイルの共有が行われているだけで、その効果は、業務の効率化にとどまり、新しい創造がなされているわけではないからであろう。インターネットはファイルではなく、知識に近い「超高質の情報」として整理されるべきである。
教育とは知識の伝達であると言われるが、知識の直接的移転は不可能である。しかし、私たちはそれを「明示的かつ安定した情報」の伝達によって実現しなければならない。これには内容を含むていねいな教授プランと詳細なメディアプラニングが必要である。メディアは「何となく学習者が喜びそうだから」使うのではなく、学習者の新知識構築を最大化、最適化すべく用いなければならない。教員の教授方法、学習方略などの暗黙の知識を明示的に示してWebで共有することができればFDやカリキュラム編成も能率的にすることができ、今後の教育の質の向上に大きく貢献できることであろう。そのためには、(1)自分が行っている教育の目的、内容、教授プロセスなどをネット上で見せる(2)ネットワークなど先進メディアの特質の研究 が必要である。以上のようにメディアを用いて授業をする者にとっては大変興味深い、先進メディアと教育について従来とは異なる視点からの分析と提案がなされた。(古田八恵 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
講演1
“Click and Read? Using the Internet for Reading Practice”
Thomas Robb(京都産業大学)
インターネットのサイトを活用する最新の指導法について、非常に興味深いレクチャーを受けた。Robb氏は、印刷媒体を利用した従来型リーディング指導法との相違点を12項目に分けて分類の上、オンラインリーディングの特徴を綿密に分析された。その大きな利点の一つは、学生が各自の英語能力、興味に応じたリーディング教材を、あらかじめ用意されたウェッブサイトの中から選ぶことが出きるので、学習意欲・興味の持続に役立つ点である。また、nonfiction中心ではあるが200種類ものextensive reading用のサイトから、authenticな教材が選べるのも大きな魅力である。学生は各自の空き時間に、毎週、最低1時間コンピュータを利用して学習をすれば、必ずしも授業の出席は義務付けられていないなど、従来型の指導法と異なるところも多い。成績などを含めて学習者の学習状況がすべてモニターできるのも大きな特徴である。
実際、Robb氏がオンラインリーディングの指導をされた経験から、その弱点としては次のような点を指摘された。必ずしも全ての学生がコンピュータを好きとは限らない。またクラスへの出席義務がないため全体でのディスカッションができない。フロアーからの質問の中にもあったが、準備に時間と手間がかかるなど、やや問題点もある。指導者側にかなりのコンピュータリテラシーを要求される授業形態でもある。印刷媒体利用型の授業とオンラインリーディング型とで、その学習効果について行われた実験の結果報告がなされた。単語と教材の意味内容の記憶保持に関して、教授法の違いによる成績の統計上の有意差は検出されなかった。また、“Extensive Reading on the Web”の授業を履修した学生を対象に実施された興味深いアンケートが紹介された。「PCは目が疲れるので印刷物の方が読みやすい」「紙の無駄遣いするよりコンピュータ画面の方がよい」など、学生の意見は賛否両論であった。
発想の転換をすることで、学習者中心の授業形態を実現できるなど、新鮮な発見を数多く含む見事なレクチャーであった。私自身も早速、“Extensive Reading Site”を「お気に入り」フォルダーに入れ速読用のサイトを活用させてもらっている。(山根 繁 甲南女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
実践報告
「授業中における多読指導の実践報告」
福地美奈子(金光大阪高等学校)
教科書以外の英文を読む機会を与え、読解力を高めて英文を読む楽しみを与える目的で行われた多読指導の実践について報告された。平成9年の4月下旬より平成10年の2月までの期間にも、朝のショートホームルーム(SHR)を利用して多読指導を行ったが、時間が短く生徒の読書量が少なかった。今回は、平成10年4月下旬より平成11年の2月に英語リーディングの授業を利用して行った多読指導実践について報告された。
被験者は高校2年生30名(男子25名、女子5名)で、そのうち19名は前年度の朝のSHRを利用した多読指導を受けた生徒である。多読指導は一週間に1回から2回(各20分)計約48回(総時間約16時間)行われた。生徒に中2レベル(1頁あたり330語)の物語集から好きな読み物を選ばせ、タスクを与えずに時間内に読ませた。教師は机間巡視をして生徒の質問に答えたり読書を促したりといった指導をし、学期末には各自の読書量を棒グラフにして教室に掲示した。 今回の実践の成果としては、教科書以外の英文を読む機会を与えられたことと、生徒の読解力を高められたことが挙げられる。内容理解テスト[Reading Power(読解力強化のための問題集)より採用、それぞれ400語から成る8つの内容理解問題で、4択形式]と、クローズテスト(多読の教材と同じレベルの読み物を使用、文中穴埋め50問)の事前事後の実施では、成績上位者よりも下位者に、また1年目の者よりも2年目の者に、著しい伸びが見られた。またこれらのテストの結果から、多読指導の継続は読解力を高めることに効果的であることがわかった。
しかし、読書量と生徒の意識の変化に関しては期待したほどの効果が現れなかった。読書量が伸びなかったことについては、速読の指示や指導を行わなかったことが一つの原因ではないかと考えられる。また、授業中に行ったためか生徒は読まされている、という意識を持っていたようで、事前事後のアンケート結果からは生徒の意識の変化はあまり見られなかった。そして、本発表の最後に、生徒の意識を「英文を読むのが楽しい」という意識に変えていくことは、今後の大きな課題であると述べられた。(小松純子 大阪市立大学大学院)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1
「リスニングの単語認知における文脈効果について:単語認知モデルによるディクテーションの分析」
池村大一郎(京都府立朱雀高校)
音声による単語認知のプロセスは、音声入力が心内辞書(mental lexicon)にアクセスし、辞書の中から音声入力に対応する語彙項目を取り出すことにより起こるとされていますが、そのときに、2つの段階があると考えられています。まず、音声入力によりいくつかの語彙候補が活性化されるactivation phase、そして次の段階の、活性化された候補の中から適切なものが一つ選ばれるselection phaseです。本研究の目的は、文脈効果は語彙候補が一つに決定する前に起こるという立場から、文脈効果がactivation phaseとselection phaseのどちらで起こっているのかを実験により明らかにすることです。
実験方法と結果について述べる前に、2つの代表的な単語認知モデルを紹介します。その一つはロゴジェン・モデル(Logogen Model)で、音声入力と文脈の両方が語彙候補を活性化するというもので、これはactivation phaseでの文脈効果を仮定したモデルです。もう一つはコーホート・モデル(Cohort Model)で、文脈は語彙候補の活性化にはかかわらないと考えるもので、selection phaseでの文脈効果を仮定しています。
実験方法は、大学生を被験者としたディクテーションで、Part 1では実験群、統制群ともに10のtarget wordsを聞かせ、スペリングと意味を書き取らせました(語単独の認知)。Part 2では、Part 1と同じtarget wordsを含む文を聞かせ、書き取らせました(言語文脈―target words の前後の単語―での認知)。Part 2では、1st trial と2nd trial を設け、2nd trial では 1st trial の訂正をさせました。その際実験群には各文の発話された場面を日本語で説明し(場面文脈での認知)、統制群にはそのような場面文脈は与えられませんでした。
結果は、Part 1と Part 2の 1st trial における単語認知率には有意差はなく、Part 2の 1st trial と 2nd trial を比較すると、2nd trial で飛躍的に単語認知率が向上していることから、言語文脈ではなく場面文脈が単語認知に大きな効果を持つと結論しています。また、実験結果は、コーホート・モデルとは矛盾しますが、ロゴジェン・モデルではうまく説明できることから、文脈効果はactivation phase で起こっていると結論しています。このことは、リスニング指導において、場面や話題の情報を学習者に与えることで、聞き取り困難な語でも聞き取りが容易になることを示唆しています。(合田由希子 大阪市立大学大学院)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2
“Virtual Reality Application and Language Learning”
Mark Peterson(北陸先端科学技術大学院大学)
近年、コンピュータを媒介としたコミュニケーション技術が目覚ましく発達し、ますます利用しやすくなってきている。このような、言語学習を容易にする仮想現実空間の出現は、CALLの発達と相まって新しく重要な段階を呈するに至っている。そのため、多くの言語指導者が、すでにMOOと呼ばれる、ネットワークを媒介にした、多数の学習者がリアルタイムにやり取りのできる仮想の言語環境を提供している。この仮想言語環境システムMOOの最近の発達には目をみはるものがあり、様々な言語のために利用されている。このような仮想現実空間の中で、(1)SLA(Second Language Acquisition)に貢献しているとされる主な要因について、(2)言語学習のための、MOOを土台とした仮想現実空間の将来的な研究領域の可能性について、報告がなされた。
言語教育にとってMOOの発達は、指導者に学習者の言語能力を向上させる新しい機会を与えているといえる。この研究はまだ初期の段階ではあるが、MOOを基礎に据える言語学習に関する論文は、CALLにおいてMOOを使用する理論的根拠を幾つか提示している。
(1)MOOに基づく学習は誰にでも利用できるので、学習においての伝統的な制約は取り除かれ、積極的な学習成果が期待できる。
(2)MOOは相互作用に基づいた言語環境を提供しているので、SLAへのアプローチの必要性を満たしている。
(3)MOOの中で学習者は自分の発した言葉を見ることができるため、メタ認知的な学習戦略を育成する機会を与えているといえる。
(4)MOOの中での作業を通して、学習者は異文化に対する認識や知識を改善する可能性がある。
(5)仮想現実空間を基にした学習は、様々な学習様式と矛盾することはなく、内気な学習者にも積極的な機会を与える可能性がある。
(6)インターネットの平等な性質によって、MOOは学習者の自主性を促したり、学習者と指導者の間に新しい関係を作りだす可能性がある。
(7)インターネット上でのやり取りは、学習者がコミュニケーション能力を改善する、お互いに訂正し会う機会を生み出す可能性がある。
このようなわずか数例からも、MOOの有効性、可能性、そして SLAへの多大なる貢献度を窺い知ることができる。
MOOをベースとした言語学習環境の利用は、幾つかの新しい研究領域の可能性を切り開いている。まず、仮想領域における学習者の談話の調査、社会言語学的な研究、そして学習者の姿勢と異文化に対する認識の研究などが挙げられる。次に、指導者の役割や、指導者と学習者の間の関係も再検討する必要がある。最後に、インターフェースの構築や知識の表現法もまた将来的に重要な研究領域になるとしている。CALLにおける、仮想現実を基にした技術の利用はまだまだ始まったばかりだが、結論的には、MOOをベースにした学習は、新しい学習機会を提供する力強くダイナミックな教室、このデジタル時代に教育と学習の再検討を指導者たちに迫るような教室作りをもたらすと、氏は予想している。(山添秀剛 大阪市立大学大学院)
--------------------------------------------------------------------------------
講演2
「今の英語教育に欠けているもの:実践的コミュニケーションをめざして」
斎藤 栄二(平安女学院大学)
最初に、現在の英語教育においてスポットを浴びているものとして、「実践的コミュニケーション」があるが、それ以前の問題として、その「底に横たわるもの」について考えることが英語教育の問題であり、特に問題にすべきは900万人が学んでいる中学、高校の英語教育であるという提案がなされた。また「底に横たわるもの」として「冠詞がわからない」「前置詞がわからない」「数がわからない」「時制がわからない」「日本語の発想から抜けられない」の5つを説明していただいた。そして、今回の講演はその中でも特に中高での冠詞指導に重点を置いてなされることになった。
まず、日本人学習者がいかに冠詞に弱いかを例を挙げながら説明がなされた。中学生から大学生に至るまで、日本人学習者の誤りの第1位は冠詞であること、冠詞は、学習経験が長くなっても、日本語のinterferenceによる脱落による誤りが目立つこと等が示された。
次に、冠詞の指導が英語を学び始める中学校1年以来の授業の中で、系統的に位置付けられず、場当たり的になっているのではないかという指摘があった。そこで、中学の教科書を具体的に分析され、不定冠詞のaが実際には何を指すか具体的に指すものが決まっていない場合、すなわちどれを指すか決まっていない場合に用いられることが多いが、中学の現場では「一つの、一冊の、一人の」等の意味で使用されていることが多いという指摘をされた。そして、定冠詞のtheは、不定冠詞(どれを指すか不定であるもの)に対するものとして、何を指すか、その場の様子からわかっている場合に用いられるという基本を押さえることの重要性が強調された。最後に、具体的な文章の中でaとtheの穴埋め問題を各自で解き、答え合わせを行った。英語母語話者も参加されていたが、彼にも難しい問題があり、冠詞使用の困難さが再認識された。
筆者が約15年前英語教師になりたての頃、授業に困り、書店の英語教育のコーナーに行った際、どの本も難しそうに思えたが、一冊だけわかりやすそうな本があり買って帰った。斎藤栄二先生の「英語を好きにさせる授業」であった。それ以後、縁があって何度もお話を伺う機会があったが、常に明日の授業への活力を与えられてきた。今回の講演も得るものの多いものであった。(安木真一 鳥取県立八頭高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
会場校代表
「会場校を引き受けて」
井狩 幸男(大阪市立大学)
2000年5月27日(土)に、大阪市立大学学術情報総合センターにて、学会名が変更されて初めての支部大会が開催されました。当日は、あいにくの雨でしたが、足下の悪い中、約80名の方が参加されました。また、懇親会には35名の出席がありました。
会場となった通称「学情センター」は、図書館と電算センターの機能を兼ね備えた一種のインテリジェントビルで、4年前の秋にオープンしました。最近は、多種多様な学会や研究会に利用されています。今回使用した10階の会議室Lは、国際会議に利用できるように設計されていますので、参加された方々に快適にご利用いただけたのではないかと思います。また、外側の廊下の部分については、比較的広く、コンセントも十分確保されていますので、展示業者の方々にも使い勝手は悪くなかったのではと推察いたします。それから、懇親会に関しては、学情センター1階にあるレストラン「ウィステリア」を利用しましたので、移動の面でご不便をかけずにすんだのではと思っています。
他方、昨年12月に前事務局長の神崎先生から市大を会場校にというお話があった時に、FLEAT-IVでどれほど忙しくなるのかを余り深く考えないままお引き受けしたため、結果的には行き届かないことが多く、参加された皆様にご不便をおかけしたのではと懸念しております。例えば、案内の表示が少なく、会場までの道順が分かり難かったのではないでしょうか。昼食の場所についても、ご案内が不十分でした。それから、学情センター5階のCALL 教室(LL実験室)を多くの先生方に見ていただこうと考えていたのですが、その機会を逃してしまいました。これらの点でご迷惑、ご不便をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
最後になりましたが、本大会を開催するに当たり、多くの方にお世話になりました。非常にお忙しい中、会場校挨拶をお引き受けくださいました山野正彦文学部長、受付等の事務と研究発表・実践報告の要旨の執筆をしていただいた市大大学院後期博士課程2回の合田さん、同じく前期博士課程2回の山添君と小松さん、そして、準備の段階からお世話くださった関西支部事務局の神崎先生と杉森直樹先生に、この場をお借りしてお礼申し上げます。
「先進メディアは『知識処理』時代の教育に貢献できるか」
東 淳一(流通科学大学)
東先生は1998年秋から約1年間オーストリアのグラーツ工科大学に客員研究員として赴任され、今回は当地での研究成果の一端として、先進メディアと教育について報告された。難解なインターネット用語が多く出てきたので 消化不良のところもあるが、パワーポイントで作成した様々な図表を駆使して教育に関する多くの情報と示唆を与えて頂いた。以下に簡単に内容を紹介したい。
今日、WWWは様々な教育現場で利用されており、Webに関連した技術も大きく進化し、多彩なオーサリングと情報配信が可能になってきた。しかし、Webの専門家ではない教育者が、魅力あるWebサイトを管理・運営していくのは至難のわざである。オーサリングの多様性の問題も含め、Webそのものは多くの問題を抱えている。コンテンツとナビゲーション用インタフェースの混同の問題、検索の困難性の問題、ハイパーリンクの一方向性の問題、URL指定におけるオブジェクト名と場所の混同の問題、ハイパーテクストのナビゲーションと内容理解度に関する問題などを挙げることができる。
データは情報の断片で あり、通常意味は付与されないが、情報はデータの集積であり、意味や価値が付与される。また、知識とは経験、認識、判断力、あるいは推理力、熟練した技術など、人間内部に存在するものであり、簡単に明示化されるとは限らず、不安定で管理しにくいものである。 現在、世界中の無数のコンピュータがネットワークで結びついているが、生産性が劇的に向上したとは思えない。その理由は単純な情報が内包されたファイルの共有が行われているだけで、その効果は、業務の効率化にとどまり、新しい創造がなされているわけではないからであろう。インターネットはファイルではなく、知識に近い「超高質の情報」として整理されるべきである。
教育とは知識の伝達であると言われるが、知識の直接的移転は不可能である。しかし、私たちはそれを「明示的かつ安定した情報」の伝達によって実現しなければならない。これには内容を含むていねいな教授プランと詳細なメディアプラニングが必要である。メディアは「何となく学習者が喜びそうだから」使うのではなく、学習者の新知識構築を最大化、最適化すべく用いなければならない。教員の教授方法、学習方略などの暗黙の知識を明示的に示してWebで共有することができればFDやカリキュラム編成も能率的にすることができ、今後の教育の質の向上に大きく貢献できることであろう。そのためには、(1)自分が行っている教育の目的、内容、教授プロセスなどをネット上で見せる(2)ネットワークなど先進メディアの特質の研究 が必要である。以上のようにメディアを用いて授業をする者にとっては大変興味深い、先進メディアと教育について従来とは異なる視点からの分析と提案がなされた。(古田八恵 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
講演1
“Click and Read? Using the Internet for Reading Practice”
Thomas Robb(京都産業大学)
インターネットのサイトを活用する最新の指導法について、非常に興味深いレクチャーを受けた。Robb氏は、印刷媒体を利用した従来型リーディング指導法との相違点を12項目に分けて分類の上、オンラインリーディングの特徴を綿密に分析された。その大きな利点の一つは、学生が各自の英語能力、興味に応じたリーディング教材を、あらかじめ用意されたウェッブサイトの中から選ぶことが出きるので、学習意欲・興味の持続に役立つ点である。また、nonfiction中心ではあるが200種類ものextensive reading用のサイトから、authenticな教材が選べるのも大きな魅力である。学生は各自の空き時間に、毎週、最低1時間コンピュータを利用して学習をすれば、必ずしも授業の出席は義務付けられていないなど、従来型の指導法と異なるところも多い。成績などを含めて学習者の学習状況がすべてモニターできるのも大きな特徴である。
実際、Robb氏がオンラインリーディングの指導をされた経験から、その弱点としては次のような点を指摘された。必ずしも全ての学生がコンピュータを好きとは限らない。またクラスへの出席義務がないため全体でのディスカッションができない。フロアーからの質問の中にもあったが、準備に時間と手間がかかるなど、やや問題点もある。指導者側にかなりのコンピュータリテラシーを要求される授業形態でもある。印刷媒体利用型の授業とオンラインリーディング型とで、その学習効果について行われた実験の結果報告がなされた。単語と教材の意味内容の記憶保持に関して、教授法の違いによる成績の統計上の有意差は検出されなかった。また、“Extensive Reading on the Web”の授業を履修した学生を対象に実施された興味深いアンケートが紹介された。「PCは目が疲れるので印刷物の方が読みやすい」「紙の無駄遣いするよりコンピュータ画面の方がよい」など、学生の意見は賛否両論であった。
発想の転換をすることで、学習者中心の授業形態を実現できるなど、新鮮な発見を数多く含む見事なレクチャーであった。私自身も早速、“Extensive Reading Site”を「お気に入り」フォルダーに入れ速読用のサイトを活用させてもらっている。(山根 繁 甲南女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
実践報告
「授業中における多読指導の実践報告」
福地美奈子(金光大阪高等学校)
教科書以外の英文を読む機会を与え、読解力を高めて英文を読む楽しみを与える目的で行われた多読指導の実践について報告された。平成9年の4月下旬より平成10年の2月までの期間にも、朝のショートホームルーム(SHR)を利用して多読指導を行ったが、時間が短く生徒の読書量が少なかった。今回は、平成10年4月下旬より平成11年の2月に英語リーディングの授業を利用して行った多読指導実践について報告された。
被験者は高校2年生30名(男子25名、女子5名)で、そのうち19名は前年度の朝のSHRを利用した多読指導を受けた生徒である。多読指導は一週間に1回から2回(各20分)計約48回(総時間約16時間)行われた。生徒に中2レベル(1頁あたり330語)の物語集から好きな読み物を選ばせ、タスクを与えずに時間内に読ませた。教師は机間巡視をして生徒の質問に答えたり読書を促したりといった指導をし、学期末には各自の読書量を棒グラフにして教室に掲示した。 今回の実践の成果としては、教科書以外の英文を読む機会を与えられたことと、生徒の読解力を高められたことが挙げられる。内容理解テスト[Reading Power(読解力強化のための問題集)より採用、それぞれ400語から成る8つの内容理解問題で、4択形式]と、クローズテスト(多読の教材と同じレベルの読み物を使用、文中穴埋め50問)の事前事後の実施では、成績上位者よりも下位者に、また1年目の者よりも2年目の者に、著しい伸びが見られた。またこれらのテストの結果から、多読指導の継続は読解力を高めることに効果的であることがわかった。
しかし、読書量と生徒の意識の変化に関しては期待したほどの効果が現れなかった。読書量が伸びなかったことについては、速読の指示や指導を行わなかったことが一つの原因ではないかと考えられる。また、授業中に行ったためか生徒は読まされている、という意識を持っていたようで、事前事後のアンケート結果からは生徒の意識の変化はあまり見られなかった。そして、本発表の最後に、生徒の意識を「英文を読むのが楽しい」という意識に変えていくことは、今後の大きな課題であると述べられた。(小松純子 大阪市立大学大学院)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1
「リスニングの単語認知における文脈効果について:単語認知モデルによるディクテーションの分析」
池村大一郎(京都府立朱雀高校)
音声による単語認知のプロセスは、音声入力が心内辞書(mental lexicon)にアクセスし、辞書の中から音声入力に対応する語彙項目を取り出すことにより起こるとされていますが、そのときに、2つの段階があると考えられています。まず、音声入力によりいくつかの語彙候補が活性化されるactivation phase、そして次の段階の、活性化された候補の中から適切なものが一つ選ばれるselection phaseです。本研究の目的は、文脈効果は語彙候補が一つに決定する前に起こるという立場から、文脈効果がactivation phaseとselection phaseのどちらで起こっているのかを実験により明らかにすることです。
実験方法と結果について述べる前に、2つの代表的な単語認知モデルを紹介します。その一つはロゴジェン・モデル(Logogen Model)で、音声入力と文脈の両方が語彙候補を活性化するというもので、これはactivation phaseでの文脈効果を仮定したモデルです。もう一つはコーホート・モデル(Cohort Model)で、文脈は語彙候補の活性化にはかかわらないと考えるもので、selection phaseでの文脈効果を仮定しています。
実験方法は、大学生を被験者としたディクテーションで、Part 1では実験群、統制群ともに10のtarget wordsを聞かせ、スペリングと意味を書き取らせました(語単独の認知)。Part 2では、Part 1と同じtarget wordsを含む文を聞かせ、書き取らせました(言語文脈―target words の前後の単語―での認知)。Part 2では、1st trial と2nd trial を設け、2nd trial では 1st trial の訂正をさせました。その際実験群には各文の発話された場面を日本語で説明し(場面文脈での認知)、統制群にはそのような場面文脈は与えられませんでした。
結果は、Part 1と Part 2の 1st trial における単語認知率には有意差はなく、Part 2の 1st trial と 2nd trial を比較すると、2nd trial で飛躍的に単語認知率が向上していることから、言語文脈ではなく場面文脈が単語認知に大きな効果を持つと結論しています。また、実験結果は、コーホート・モデルとは矛盾しますが、ロゴジェン・モデルではうまく説明できることから、文脈効果はactivation phase で起こっていると結論しています。このことは、リスニング指導において、場面や話題の情報を学習者に与えることで、聞き取り困難な語でも聞き取りが容易になることを示唆しています。(合田由希子 大阪市立大学大学院)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2
“Virtual Reality Application and Language Learning”
Mark Peterson(北陸先端科学技術大学院大学)
近年、コンピュータを媒介としたコミュニケーション技術が目覚ましく発達し、ますます利用しやすくなってきている。このような、言語学習を容易にする仮想現実空間の出現は、CALLの発達と相まって新しく重要な段階を呈するに至っている。そのため、多くの言語指導者が、すでにMOOと呼ばれる、ネットワークを媒介にした、多数の学習者がリアルタイムにやり取りのできる仮想の言語環境を提供している。この仮想言語環境システムMOOの最近の発達には目をみはるものがあり、様々な言語のために利用されている。このような仮想現実空間の中で、(1)SLA(Second Language Acquisition)に貢献しているとされる主な要因について、(2)言語学習のための、MOOを土台とした仮想現実空間の将来的な研究領域の可能性について、報告がなされた。
言語教育にとってMOOの発達は、指導者に学習者の言語能力を向上させる新しい機会を与えているといえる。この研究はまだ初期の段階ではあるが、MOOを基礎に据える言語学習に関する論文は、CALLにおいてMOOを使用する理論的根拠を幾つか提示している。
(1)MOOに基づく学習は誰にでも利用できるので、学習においての伝統的な制約は取り除かれ、積極的な学習成果が期待できる。
(2)MOOは相互作用に基づいた言語環境を提供しているので、SLAへのアプローチの必要性を満たしている。
(3)MOOの中で学習者は自分の発した言葉を見ることができるため、メタ認知的な学習戦略を育成する機会を与えているといえる。
(4)MOOの中での作業を通して、学習者は異文化に対する認識や知識を改善する可能性がある。
(5)仮想現実空間を基にした学習は、様々な学習様式と矛盾することはなく、内気な学習者にも積極的な機会を与える可能性がある。
(6)インターネットの平等な性質によって、MOOは学習者の自主性を促したり、学習者と指導者の間に新しい関係を作りだす可能性がある。
(7)インターネット上でのやり取りは、学習者がコミュニケーション能力を改善する、お互いに訂正し会う機会を生み出す可能性がある。
このようなわずか数例からも、MOOの有効性、可能性、そして SLAへの多大なる貢献度を窺い知ることができる。
MOOをベースとした言語学習環境の利用は、幾つかの新しい研究領域の可能性を切り開いている。まず、仮想領域における学習者の談話の調査、社会言語学的な研究、そして学習者の姿勢と異文化に対する認識の研究などが挙げられる。次に、指導者の役割や、指導者と学習者の間の関係も再検討する必要がある。最後に、インターフェースの構築や知識の表現法もまた将来的に重要な研究領域になるとしている。CALLにおける、仮想現実を基にした技術の利用はまだまだ始まったばかりだが、結論的には、MOOをベースにした学習は、新しい学習機会を提供する力強くダイナミックな教室、このデジタル時代に教育と学習の再検討を指導者たちに迫るような教室作りをもたらすと、氏は予想している。(山添秀剛 大阪市立大学大学院)
--------------------------------------------------------------------------------
講演2
「今の英語教育に欠けているもの:実践的コミュニケーションをめざして」
斎藤 栄二(平安女学院大学)
最初に、現在の英語教育においてスポットを浴びているものとして、「実践的コミュニケーション」があるが、それ以前の問題として、その「底に横たわるもの」について考えることが英語教育の問題であり、特に問題にすべきは900万人が学んでいる中学、高校の英語教育であるという提案がなされた。また「底に横たわるもの」として「冠詞がわからない」「前置詞がわからない」「数がわからない」「時制がわからない」「日本語の発想から抜けられない」の5つを説明していただいた。そして、今回の講演はその中でも特に中高での冠詞指導に重点を置いてなされることになった。
まず、日本人学習者がいかに冠詞に弱いかを例を挙げながら説明がなされた。中学生から大学生に至るまで、日本人学習者の誤りの第1位は冠詞であること、冠詞は、学習経験が長くなっても、日本語のinterferenceによる脱落による誤りが目立つこと等が示された。
次に、冠詞の指導が英語を学び始める中学校1年以来の授業の中で、系統的に位置付けられず、場当たり的になっているのではないかという指摘があった。そこで、中学の教科書を具体的に分析され、不定冠詞のaが実際には何を指すか具体的に指すものが決まっていない場合、すなわちどれを指すか決まっていない場合に用いられることが多いが、中学の現場では「一つの、一冊の、一人の」等の意味で使用されていることが多いという指摘をされた。そして、定冠詞のtheは、不定冠詞(どれを指すか不定であるもの)に対するものとして、何を指すか、その場の様子からわかっている場合に用いられるという基本を押さえることの重要性が強調された。最後に、具体的な文章の中でaとtheの穴埋め問題を各自で解き、答え合わせを行った。英語母語話者も参加されていたが、彼にも難しい問題があり、冠詞使用の困難さが再認識された。
筆者が約15年前英語教師になりたての頃、授業に困り、書店の英語教育のコーナーに行った際、どの本も難しそうに思えたが、一冊だけわかりやすそうな本があり買って帰った。斎藤栄二先生の「英語を好きにさせる授業」であった。それ以後、縁があって何度もお話を伺う機会があったが、常に明日の授業への活力を与えられてきた。今回の講演も得るものの多いものであった。(安木真一 鳥取県立八頭高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
会場校代表
「会場校を引き受けて」
井狩 幸男(大阪市立大学)
2000年5月27日(土)に、大阪市立大学学術情報総合センターにて、学会名が変更されて初めての支部大会が開催されました。当日は、あいにくの雨でしたが、足下の悪い中、約80名の方が参加されました。また、懇親会には35名の出席がありました。
会場となった通称「学情センター」は、図書館と電算センターの機能を兼ね備えた一種のインテリジェントビルで、4年前の秋にオープンしました。最近は、多種多様な学会や研究会に利用されています。今回使用した10階の会議室Lは、国際会議に利用できるように設計されていますので、参加された方々に快適にご利用いただけたのではないかと思います。また、外側の廊下の部分については、比較的広く、コンセントも十分確保されていますので、展示業者の方々にも使い勝手は悪くなかったのではと推察いたします。それから、懇親会に関しては、学情センター1階にあるレストラン「ウィステリア」を利用しましたので、移動の面でご不便をかけずにすんだのではと思っています。
他方、昨年12月に前事務局長の神崎先生から市大を会場校にというお話があった時に、FLEAT-IVでどれほど忙しくなるのかを余り深く考えないままお引き受けしたため、結果的には行き届かないことが多く、参加された皆様にご不便をおかけしたのではと懸念しております。例えば、案内の表示が少なく、会場までの道順が分かり難かったのではないでしょうか。昼食の場所についても、ご案内が不十分でした。それから、学情センター5階のCALL 教室(LL実験室)を多くの先生方に見ていただこうと考えていたのですが、その機会を逃してしまいました。これらの点でご迷惑、ご不便をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。
最後になりましたが、本大会を開催するに当たり、多くの方にお世話になりました。非常にお忙しい中、会場校挨拶をお引き受けくださいました山野正彦文学部長、受付等の事務と研究発表・実践報告の要旨の執筆をしていただいた市大大学院後期博士課程2回の合田さん、同じく前期博士課程2回の山添君と小松さん、そして、準備の段階からお世話くださった関西支部事務局の神崎先生と杉森直樹先生に、この場をお借りしてお礼申し上げます。