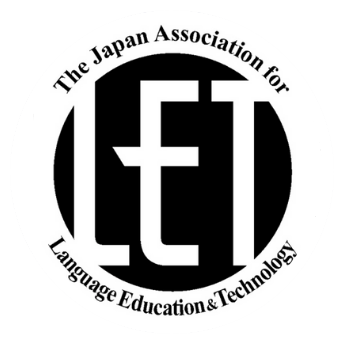大会名
99年度春季研究大会
大会(春・秋・全国)
春季大会
日付
1999年5月30日
会場
京都府立大学
概要
春季大会は5月30日(日)に京都府立大学(京都北山)にて行われました。日曜日にもかかわらず約60名のご参加をいただき、充実した会となりました。会場として受け入れにご協力いただきました京都府立大学の皆さんに感謝いたします。シンポジアムの議論はとくに盛り上がり、教育への意欲が感じられるものとなりました。詳しくは、下記の報告をご覧ください。
詳細
授業研究
「ティームティーチングとコンピュータを用いたライティング授業」
高田 哲朗(京都教育大学付属高等学校)
京都教育大学付属高等学校では2年生のWritingの授業にALT(Assistant Language Teacher)とJTE(Japanese English Teacher)のTeam-Teachingによる授業を行っている。今回は普通教室でのTeam-Teachingによる授業を2時限、コンピュータ室での自由作文のTeam-Teachingを1時限、ビデオで紹介された。
普通教室による授業では教科書とワークブックを使用し、教科書にそって進めていくというもので、Dialogue、Key Expression、Drills、Speed Compositionという内容であった。Key Expressionでは、教科書に載っている表現の他どのような表現があるか、ALTとJTEでこんな表現があると出し合いながら進められた。Drillsでは生徒の解答を黒板に書かせ、二人の教師により答え合わせが進められていたが、ここでも生徒の表現について議論をしながらの答え合わせが進められていた。ALTとJTEの二人の教師がそれぞれ、他の表現の提案をしながら進めるため、時には二人の意見の食い違う場面も見られた。
コンピュータ室での授業では、Topic Writingを生徒は自由にコンピュータを使って作文をおこないフロッピーディスクに保存するという形で進められていた。その際、ALTがコンピュータに比較的詳しい人であったため、生徒の手助けもおこなっていた。
今回、特に興味深かったのは、ALTとJETがそれぞれ他の表現を出し合い、議論し、進めていくことで、生徒に教科書や一人の先生だけの解答だけではなく、答えが多数あることや、一つ一つの表現の微妙な違いを教えることになっているのではないかということであった。その現れか、発表者によると授業後に「こんな表現はできないか?」という生徒の質問の列ができ「嬉しい悲鳴」をあげているとのことである。
今後、生徒がこれほどまでに動機づけられたその要因を明らかにし、「嬉しい悲鳴」がどこの学校でもあがることを願う。(佐藤省吾 関西大学大学院総合情報学研究科)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-1
「高校生の短期海外研修における異文化理解について」
福地美奈子(金光大阪高等学校)
夏休みを利用した高校生の海外語学研修は今や珍しいものではなく、本発表の福地先生の勤務されている高等学校(および併設の中学校)でも毎年夏に希望者にオーストラリアで研修を受けさせている。福地先生はこの研修の引率をされ、1996年度にも実践報告をされたが、今回は参加した生徒の日記(日本語による)の内容を、英語学習、コミュニケーション、オーストラリア人など項目別に分類し、意識の傾向を探ったものである。各項目はさらに内容別に分類、数値化され井澤、対馬氏の理論に基づき分析された。その結果、この研修は異文化適応能力を培う上で有意義であることがわかった。
期間は2週間、参加した人数は24名と限られてはいるが、それぞれの項目で生徒のほほえましい、または思いがけない感想もあり、興味深かった。今後もこの生徒の日記の分析を継続して資料を蓄積させていくとまた新たな発見もあるのではと思われた。会場からも活発な質問が相次いだ。それにしても中学生、高校生の時に海外に語学研修に行かせてもらえるとはうらやましいかぎりである。(伊庭 緑 甲南大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-2
「形成的成績評価とフィードバックの教育的効果」
野村 和宏(流通科学大学)
野村先生の授業の密度は濃く、工夫度は高い。先生が授業を「90分のショータイム」と表現されていたのを以前伺ったことがあるが、今回ショータイムはまたバージョン・アップされたようである。学生に対する小テストやレポートをきちんと管理して、学習の過程を重視した学生の形成評価ができればどんなにいいだろうとは、私を含めて教える立場にある人ならだれしも思うことではないだろうか。ただ意気込みはあっても現実問題として時間がかかりすぎるなど、実行するのは難しい。
そこで登場するのが成績管理ソフトである。野村先生は以前に自ら成績管理ソフトを設計されたこともあるが、昨年からはOrbis Software社による“Easy Grade Pro”を授業に全面的に取り入れている。このソフトは同類のソフト25種を検討した中でも学生管理、成績管理、成績報告、操作性などあらゆる面で優れているそうである。
具体的には授業中に教室のモニターに上位成績者を提示したり、学期の途中に数回、中間成績表を学生に配布したり、毎時間新しい座席表で着席させたりする。これに対する学生のアンケート結果は、どの項目もひじょうに肯定的で、たとえばこのような成績のフィードバックが従来の方法よりも優れていると思う学生の比率は132名中120名、今後も継続して欲しいと答えたのは117名にのぼった。
このソフトは現在Macintosh対応のみだがもうすぐWindows対応のものも発売される予定である。(伊庭 緑 甲南大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-1
「教材作成プログラムの編集機能についての考察」
村磯 優子(株ワールドウォッチ)
市販の様々な音声、映像(カセットテープ、ビデオ、CD、DVD等)の素材を活用して短時間に、しかも容易な操作で英語学習用教材を編集、生成することを目的に開発されたMacintosh用アプリケーションの発表が行われた。
音声、映像素材に編集データ(素材を必要な映像、音声単位に分割し、リピート等コントロールを容易にするためのデータ)とText、Referenceを付加し、リンクすることで語学学習用教材としての利用価値を高め、素材の選択や利用方法の自由度の幅を広げるツールとして、自習やClassでの活用が可能である。
すでに昨年のLLA全国大会(福岡)にて発表され、好評を博したソフトウエアであるが、その後の研究で、さらに利便性を高めるべく、テキスト編集機能の強化がなされている。
具体的にはTextの入力機能としてTyping、Closed-caption data、音声認識によるtext変換機能を備え、容易なtext入力を実現している。また、近い将来にはこれらの編集作業の自動化も研究中であるとの報告も付け加えられた。
特に今後増加が予想されるCDやDVDなどのdisc mediaを利用するとき、直接、素材を加工せず、編集データだけを生成することで教材の利用が可能なため、著作権処理が回避できる点は今後の音声、映像素材の利用の一つの方法として注目できる手法であろう。本ソフトウエアはfreewareであるため、次のサイトからdownloadして入手できる。近日中に国内にもサイトが展開予定であり、更に入手が容易になるであろう。なお、Dataのsizeが大きいため、downloadする際には注意が必要であることを付記しておく。http://www.world-watch.com(草野厚生 松下通信工業株式会社)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-2
「ネットワーク環境での英単語学習システムの構築」
杉森 直樹(大阪電気通信大学)
日本人英語学習者の口語英語における語彙不足の課題に対して、発表者はコーパスを利用した頻出語彙の調査と日本人英語学習者を対象としたテスト結果に基づいて600語の頻出語彙の選定を行い、それらを効率的に習得するためのコンピュータを利用した英単語学習システムを開発、その実践報告がなされた。
実際の操作画面をビデオ収録し、提示しながらの発表が行われたため、操作環境や各学習stepの展開が確認でき、その機能とあいまって参加者の興味を喚起した。
本学習システムは基本的にWeb-basedであるため、WebServerとイントラネット/インターネットの環境があればいつでもどこからでもアクセスが可能であるという特長を有し、このため、広域ネットワークを利用すれば、家庭学習や遠隔学習への展開も可能となる。学習結果のフィードバックもCGIプログラムによる自動採点機能で瞬時に行われ、その履歴や成績のデータもサーバーに残されるため、教師の運用面での負担の軽減も考慮されている。また、メVocabuilderモ(shareware for DOS/V PC)との組合わせにより、複数のstepでターゲットとなる語彙を繰り返し反復して学習でき、その定着が図られる工夫がなされている。
語彙の習得は、ともすれば単調な作業の繰り返しになりがちであるため、本システムのようにInteractiveな道具の利用は有効な手段の一つであると思われるが、さらに楽しく効果的な学習システムへと発展させるためには、発表者が課題として上げた通り、映像/音声情報の取り込みや、実際のコミュニケーション活動との有機的な組合わせ等の工夫や改良が望まれよう。今後の本システムの更なる研究と改良を期待したい。
なお、本システムのSecond-stepで利用されているメVocabuilderモは既にsharewareとして入手が可能である。パーソナルコンピュータ利用のアプリケーションとしてすぐにでも利用ができるので、ご希望の会員は以下のsiteにaccessして、downloadされることをお勧めする。 http://www.vector.co.jp/(草野厚生 松下通信工業株式会社)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジアム
「実践的コミュニケーション能力の育成:中・高・大の架け橋を求めて」
コーデイネーター:弓庭 喜和子(関西外国語大学短期大学部)
パネリスト: 川井 泉(神戸市立桜の宮中学校)
白井雅裕(同志社女子中・高等学校)
斎藤泰成(岡山県立玉野光南高等学校)
鈴木寿一(京都教育大学)
安田雅美(関西学院大学)
弓庭喜和子(関西外国語大学短期大学部)
まず最初にコーデイネーターからテーマの趣旨として、「本年3月1日に公表された高校新学習指導要領案で謳われている『実践的コミュニケーション能力の育成』の重視は現行学習指導要領の『オーラルコミュニケーション』重視の流れの発展と考えられるが、本シンポジウムでは新学習指導要領そのものについての論議は別の機会に譲ることとし、実践的コミュニケーション能力育成の成果を挙げるために、現在日本の英語教育界は中・高・大のそれぞれにおいて何をしなければならないか、どのようにお互いに橋を架け合って目標の実現に取り組んで行くことができるか、を探りたい」との説明があった。
続いて、各パネリストからそれぞれ10分程度で問題提起と提案が行われた。白井氏は、『実践的コミュニケーション能力』とは何かについて先行的研究を引用しての理論的考察の後、Savignon の理論的枠組みを縦軸に、ある場面でメッセージの「両面通行」を可能にするために何をいかに言うべきかという視点を横軸に、中・高・大の各学習段階で育成されるべきコミュニケーション能力(what ×how)とは何か、final product としての実践的コミュニケーション能力(WHAT×HOW)とは何かについて明確にする必要を提起された。
斎藤氏からは、小・中・高・大の連携がなかなか進まず授業や教材・教え方等についての情報や理解がお互いに不十分な現実を改善し、円軌道での連携、人事交流や職場交流によって今後相互理解を深めることが提案された。英語科教員の英語能力を高めるためのin-service training としての海外留学の有効性、教員養成制度の改革で教育実習期間が2週間から4週間になることの高校現場に与える深刻な影響についての大学側の認識等についても切実な問題提起と提案が行われ、お互いにそれぞれの悩みや問題を本音で語り合うことが解決や前進につながると結ばれた。
安田氏は、実践的コミュニケーション能力の習得を妨げる要因として、社会的な要因や教育界等での要因を挙げ、その改善に向けては、大学側の中・高の現状についての認識が不十分であるとかカリキュラム編成制度その他の面で依然として旧体制のままである等の場合の大学側の責任も認めた上で、今後は学会も中・高・大のより一層の相互理解を促進する方向でより活発な活動を提案された。安田氏が実践されている e-mail を用いた「発信型」英語作文の指導 (inter-languageの学習過程を理解できるESL用作文指導)の紹介も行われた。
川井氏からは、中学校における問題点として、コミュニケーション能力の育成等を重視した新しい学力観と「意欲・関心・態度」を前面に押し出した観点別評価が点数化の難しさや客観性の面から実現困難である現状や、ALTの急増に対応する教員や学校側の受け入れ態勢が不十分である等が指摘された。神戸市の中学校間では地区別研究会での研究授業や意見交換等の交流が盛んである一方で、中・高の連携では大きな働きかけは見られない。実践例として、学校の野外活動や「トライやる・ウイーク」( Trial Week )等の生徒の実践的教育活動を生きた教材として「ALT への手紙」という形で英作文指導に活用されている川井氏の試みが報告された。
鈴木氏は、高校の「受験対策指導」の現状を分析し、いわゆる「英語嫌い」の増加/減少の要因を探る興味深いデータを提示しつつ、「コミュニケーション能力育成を目指す指導」は和訳力・内容把握力・総合力において大学入試に対応できる学力を養成する点で有効であるという提言を行われると同時に、高校側は大学側に対し入試問題の適正化を要望するとともに、長い目で見た「生徒のためになる英語教育」を実践するために、高校側みずからその指導法・教材・評価法の再検討を敢行することを提案された。
弓庭は、実践的コミュニケーション活動を疎外する要因として、生徒のpoor command of grammar / structure、従来型の教授法:teaching about English rather than teaching English、Japanese collectivist culture; a desire to preserve faceを指摘し、その解決法としてgrammar の運用機会を増やし単なる知識に終わらせない、楽しく有意義な多量の英語に触れさせる、他教科でも発信型授業形態を導入する等を提案した。授業モデルとして、上述の疎外要因をクリアーし、step-by-step方式で映画ビデオをLL総合教材として活用する方法を紹介、dialogue practice; role-playing; academic debate を編集収録した4分余の授業ビデオを提示した。
6人のパネリストの発表の後、フロアーから活発な質問や意見が出され、パネリストとの熱心なやり取りが展開された。パネリスト側ではビデオやさらに詳しいデータ等用意されていたにも拘わらず、時間の都合で十分活用していただくことができなかったのが残念であった。 最後にフロアーから、本四架橋が達成された今は、もはや「架け橋を求めて」の時代ではなく、架け橋はもう架かっている時代であるとの認識で、中・高・大間の相互乗り入れ等更に一層積極的な交流を図って行こう、という提案が行われ大きな拍手で迎えられるなか、本シンポジウムは幕を閉じた。(弓庭 喜和子 関西外国語大学短期大学部)
「ティームティーチングとコンピュータを用いたライティング授業」
高田 哲朗(京都教育大学付属高等学校)
京都教育大学付属高等学校では2年生のWritingの授業にALT(Assistant Language Teacher)とJTE(Japanese English Teacher)のTeam-Teachingによる授業を行っている。今回は普通教室でのTeam-Teachingによる授業を2時限、コンピュータ室での自由作文のTeam-Teachingを1時限、ビデオで紹介された。
普通教室による授業では教科書とワークブックを使用し、教科書にそって進めていくというもので、Dialogue、Key Expression、Drills、Speed Compositionという内容であった。Key Expressionでは、教科書に載っている表現の他どのような表現があるか、ALTとJTEでこんな表現があると出し合いながら進められた。Drillsでは生徒の解答を黒板に書かせ、二人の教師により答え合わせが進められていたが、ここでも生徒の表現について議論をしながらの答え合わせが進められていた。ALTとJTEの二人の教師がそれぞれ、他の表現の提案をしながら進めるため、時には二人の意見の食い違う場面も見られた。
コンピュータ室での授業では、Topic Writingを生徒は自由にコンピュータを使って作文をおこないフロッピーディスクに保存するという形で進められていた。その際、ALTがコンピュータに比較的詳しい人であったため、生徒の手助けもおこなっていた。
今回、特に興味深かったのは、ALTとJETがそれぞれ他の表現を出し合い、議論し、進めていくことで、生徒に教科書や一人の先生だけの解答だけではなく、答えが多数あることや、一つ一つの表現の微妙な違いを教えることになっているのではないかということであった。その現れか、発表者によると授業後に「こんな表現はできないか?」という生徒の質問の列ができ「嬉しい悲鳴」をあげているとのことである。
今後、生徒がこれほどまでに動機づけられたその要因を明らかにし、「嬉しい悲鳴」がどこの学校でもあがることを願う。(佐藤省吾 関西大学大学院総合情報学研究科)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-1
「高校生の短期海外研修における異文化理解について」
福地美奈子(金光大阪高等学校)
夏休みを利用した高校生の海外語学研修は今や珍しいものではなく、本発表の福地先生の勤務されている高等学校(および併設の中学校)でも毎年夏に希望者にオーストラリアで研修を受けさせている。福地先生はこの研修の引率をされ、1996年度にも実践報告をされたが、今回は参加した生徒の日記(日本語による)の内容を、英語学習、コミュニケーション、オーストラリア人など項目別に分類し、意識の傾向を探ったものである。各項目はさらに内容別に分類、数値化され井澤、対馬氏の理論に基づき分析された。その結果、この研修は異文化適応能力を培う上で有意義であることがわかった。
期間は2週間、参加した人数は24名と限られてはいるが、それぞれの項目で生徒のほほえましい、または思いがけない感想もあり、興味深かった。今後もこの生徒の日記の分析を継続して資料を蓄積させていくとまた新たな発見もあるのではと思われた。会場からも活発な質問が相次いだ。それにしても中学生、高校生の時に海外に語学研修に行かせてもらえるとはうらやましいかぎりである。(伊庭 緑 甲南大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-2
「形成的成績評価とフィードバックの教育的効果」
野村 和宏(流通科学大学)
野村先生の授業の密度は濃く、工夫度は高い。先生が授業を「90分のショータイム」と表現されていたのを以前伺ったことがあるが、今回ショータイムはまたバージョン・アップされたようである。学生に対する小テストやレポートをきちんと管理して、学習の過程を重視した学生の形成評価ができればどんなにいいだろうとは、私を含めて教える立場にある人ならだれしも思うことではないだろうか。ただ意気込みはあっても現実問題として時間がかかりすぎるなど、実行するのは難しい。
そこで登場するのが成績管理ソフトである。野村先生は以前に自ら成績管理ソフトを設計されたこともあるが、昨年からはOrbis Software社による“Easy Grade Pro”を授業に全面的に取り入れている。このソフトは同類のソフト25種を検討した中でも学生管理、成績管理、成績報告、操作性などあらゆる面で優れているそうである。
具体的には授業中に教室のモニターに上位成績者を提示したり、学期の途中に数回、中間成績表を学生に配布したり、毎時間新しい座席表で着席させたりする。これに対する学生のアンケート結果は、どの項目もひじょうに肯定的で、たとえばこのような成績のフィードバックが従来の方法よりも優れていると思う学生の比率は132名中120名、今後も継続して欲しいと答えたのは117名にのぼった。
このソフトは現在Macintosh対応のみだがもうすぐWindows対応のものも発売される予定である。(伊庭 緑 甲南大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-1
「教材作成プログラムの編集機能についての考察」
村磯 優子(株ワールドウォッチ)
市販の様々な音声、映像(カセットテープ、ビデオ、CD、DVD等)の素材を活用して短時間に、しかも容易な操作で英語学習用教材を編集、生成することを目的に開発されたMacintosh用アプリケーションの発表が行われた。
音声、映像素材に編集データ(素材を必要な映像、音声単位に分割し、リピート等コントロールを容易にするためのデータ)とText、Referenceを付加し、リンクすることで語学学習用教材としての利用価値を高め、素材の選択や利用方法の自由度の幅を広げるツールとして、自習やClassでの活用が可能である。
すでに昨年のLLA全国大会(福岡)にて発表され、好評を博したソフトウエアであるが、その後の研究で、さらに利便性を高めるべく、テキスト編集機能の強化がなされている。
具体的にはTextの入力機能としてTyping、Closed-caption data、音声認識によるtext変換機能を備え、容易なtext入力を実現している。また、近い将来にはこれらの編集作業の自動化も研究中であるとの報告も付け加えられた。
特に今後増加が予想されるCDやDVDなどのdisc mediaを利用するとき、直接、素材を加工せず、編集データだけを生成することで教材の利用が可能なため、著作権処理が回避できる点は今後の音声、映像素材の利用の一つの方法として注目できる手法であろう。本ソフトウエアはfreewareであるため、次のサイトからdownloadして入手できる。近日中に国内にもサイトが展開予定であり、更に入手が容易になるであろう。なお、Dataのsizeが大きいため、downloadする際には注意が必要であることを付記しておく。http://www.world-watch.com(草野厚生 松下通信工業株式会社)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-2
「ネットワーク環境での英単語学習システムの構築」
杉森 直樹(大阪電気通信大学)
日本人英語学習者の口語英語における語彙不足の課題に対して、発表者はコーパスを利用した頻出語彙の調査と日本人英語学習者を対象としたテスト結果に基づいて600語の頻出語彙の選定を行い、それらを効率的に習得するためのコンピュータを利用した英単語学習システムを開発、その実践報告がなされた。
実際の操作画面をビデオ収録し、提示しながらの発表が行われたため、操作環境や各学習stepの展開が確認でき、その機能とあいまって参加者の興味を喚起した。
本学習システムは基本的にWeb-basedであるため、WebServerとイントラネット/インターネットの環境があればいつでもどこからでもアクセスが可能であるという特長を有し、このため、広域ネットワークを利用すれば、家庭学習や遠隔学習への展開も可能となる。学習結果のフィードバックもCGIプログラムによる自動採点機能で瞬時に行われ、その履歴や成績のデータもサーバーに残されるため、教師の運用面での負担の軽減も考慮されている。また、メVocabuilderモ(shareware for DOS/V PC)との組合わせにより、複数のstepでターゲットとなる語彙を繰り返し反復して学習でき、その定着が図られる工夫がなされている。
語彙の習得は、ともすれば単調な作業の繰り返しになりがちであるため、本システムのようにInteractiveな道具の利用は有効な手段の一つであると思われるが、さらに楽しく効果的な学習システムへと発展させるためには、発表者が課題として上げた通り、映像/音声情報の取り込みや、実際のコミュニケーション活動との有機的な組合わせ等の工夫や改良が望まれよう。今後の本システムの更なる研究と改良を期待したい。
なお、本システムのSecond-stepで利用されているメVocabuilderモは既にsharewareとして入手が可能である。パーソナルコンピュータ利用のアプリケーションとしてすぐにでも利用ができるので、ご希望の会員は以下のsiteにaccessして、downloadされることをお勧めする。 http://www.vector.co.jp/(草野厚生 松下通信工業株式会社)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジアム
「実践的コミュニケーション能力の育成:中・高・大の架け橋を求めて」
コーデイネーター:弓庭 喜和子(関西外国語大学短期大学部)
パネリスト: 川井 泉(神戸市立桜の宮中学校)
白井雅裕(同志社女子中・高等学校)
斎藤泰成(岡山県立玉野光南高等学校)
鈴木寿一(京都教育大学)
安田雅美(関西学院大学)
弓庭喜和子(関西外国語大学短期大学部)
まず最初にコーデイネーターからテーマの趣旨として、「本年3月1日に公表された高校新学習指導要領案で謳われている『実践的コミュニケーション能力の育成』の重視は現行学習指導要領の『オーラルコミュニケーション』重視の流れの発展と考えられるが、本シンポジウムでは新学習指導要領そのものについての論議は別の機会に譲ることとし、実践的コミュニケーション能力育成の成果を挙げるために、現在日本の英語教育界は中・高・大のそれぞれにおいて何をしなければならないか、どのようにお互いに橋を架け合って目標の実現に取り組んで行くことができるか、を探りたい」との説明があった。
続いて、各パネリストからそれぞれ10分程度で問題提起と提案が行われた。白井氏は、『実践的コミュニケーション能力』とは何かについて先行的研究を引用しての理論的考察の後、Savignon の理論的枠組みを縦軸に、ある場面でメッセージの「両面通行」を可能にするために何をいかに言うべきかという視点を横軸に、中・高・大の各学習段階で育成されるべきコミュニケーション能力(what ×how)とは何か、final product としての実践的コミュニケーション能力(WHAT×HOW)とは何かについて明確にする必要を提起された。
斎藤氏からは、小・中・高・大の連携がなかなか進まず授業や教材・教え方等についての情報や理解がお互いに不十分な現実を改善し、円軌道での連携、人事交流や職場交流によって今後相互理解を深めることが提案された。英語科教員の英語能力を高めるためのin-service training としての海外留学の有効性、教員養成制度の改革で教育実習期間が2週間から4週間になることの高校現場に与える深刻な影響についての大学側の認識等についても切実な問題提起と提案が行われ、お互いにそれぞれの悩みや問題を本音で語り合うことが解決や前進につながると結ばれた。
安田氏は、実践的コミュニケーション能力の習得を妨げる要因として、社会的な要因や教育界等での要因を挙げ、その改善に向けては、大学側の中・高の現状についての認識が不十分であるとかカリキュラム編成制度その他の面で依然として旧体制のままである等の場合の大学側の責任も認めた上で、今後は学会も中・高・大のより一層の相互理解を促進する方向でより活発な活動を提案された。安田氏が実践されている e-mail を用いた「発信型」英語作文の指導 (inter-languageの学習過程を理解できるESL用作文指導)の紹介も行われた。
川井氏からは、中学校における問題点として、コミュニケーション能力の育成等を重視した新しい学力観と「意欲・関心・態度」を前面に押し出した観点別評価が点数化の難しさや客観性の面から実現困難である現状や、ALTの急増に対応する教員や学校側の受け入れ態勢が不十分である等が指摘された。神戸市の中学校間では地区別研究会での研究授業や意見交換等の交流が盛んである一方で、中・高の連携では大きな働きかけは見られない。実践例として、学校の野外活動や「トライやる・ウイーク」( Trial Week )等の生徒の実践的教育活動を生きた教材として「ALT への手紙」という形で英作文指導に活用されている川井氏の試みが報告された。
鈴木氏は、高校の「受験対策指導」の現状を分析し、いわゆる「英語嫌い」の増加/減少の要因を探る興味深いデータを提示しつつ、「コミュニケーション能力育成を目指す指導」は和訳力・内容把握力・総合力において大学入試に対応できる学力を養成する点で有効であるという提言を行われると同時に、高校側は大学側に対し入試問題の適正化を要望するとともに、長い目で見た「生徒のためになる英語教育」を実践するために、高校側みずからその指導法・教材・評価法の再検討を敢行することを提案された。
弓庭は、実践的コミュニケーション活動を疎外する要因として、生徒のpoor command of grammar / structure、従来型の教授法:teaching about English rather than teaching English、Japanese collectivist culture; a desire to preserve faceを指摘し、その解決法としてgrammar の運用機会を増やし単なる知識に終わらせない、楽しく有意義な多量の英語に触れさせる、他教科でも発信型授業形態を導入する等を提案した。授業モデルとして、上述の疎外要因をクリアーし、step-by-step方式で映画ビデオをLL総合教材として活用する方法を紹介、dialogue practice; role-playing; academic debate を編集収録した4分余の授業ビデオを提示した。
6人のパネリストの発表の後、フロアーから活発な質問や意見が出され、パネリストとの熱心なやり取りが展開された。パネリスト側ではビデオやさらに詳しいデータ等用意されていたにも拘わらず、時間の都合で十分活用していただくことができなかったのが残念であった。 最後にフロアーから、本四架橋が達成された今は、もはや「架け橋を求めて」の時代ではなく、架け橋はもう架かっている時代であるとの認識で、中・高・大間の相互乗り入れ等更に一層積極的な交流を図って行こう、という提案が行われ大きな拍手で迎えられるなか、本シンポジウムは幕を閉じた。(弓庭 喜和子 関西外国語大学短期大学部)