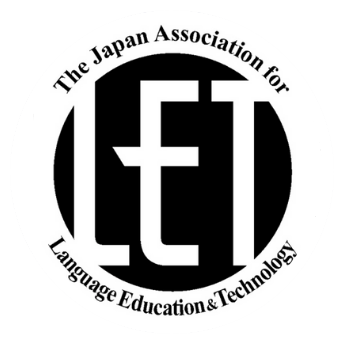大会名
98年度秋季研究大会
大会(春・秋・全国)
秋季大会
日付
1998年10月31日
会場
山陽学園大学
概要
秋季大会は10月31日(土)に山陽学園大学(岡山市)で行われ、約70名の参加を得て、充実した会となりました。会場校として受けいれに協力いただきました山陽学園大学の皆さんに心より感謝いたします。また、刺激的な講演をいただきました坂元昴先生(メディア教育開発センター所長)にも深くお礼申し上げます。臨時支部総会では新しい理事、支部役員などが承認されました。内容に関しましては、以下の報告をご覧ください。
詳細
授業研究
『テレビ会話システムの英語教育への応用:山陽学園大学の試み』
能登原 昭夫(山陽学園大学)
初めに、山陽学園大学の歴史と理念に基づいた21世紀英語教育へのvanguardとして、最先端に挑戦していく決意が述べられた。具体的には、1.組織+カリキュラム(ALPS)-CAI+DEEP/機器と教材、2.Tele-conference/video-conference/TV会議システム/遠隔教育についての説明があり、次いで、それに基づいた2つの実験概要の中間報告がなされた。
これらの実験は、単なる4技能ではなく、totalでintegrateされたcommunicativeなcontentに力を注ぎ、学生のautonomy(self-deirected learning)を最終目標とするものである。1年次はremedial stageとし、2年次ではLL開発によるspeed reading program(1分間に読める語数を150,200,300と増やしていく)に従い、学生各自が楽しみをもって学習し、学年末には85%以上の学生が合格点に達した。
3年次、4年次では、E-mailが瞬間に読めるようになることを目標とした。tele-conference/video conference programでは、英検準1級一次試験を合格した4人の4年次学生が選ばれ、Berlitz Okayamaと協同しての会話実験がビデオで紹介された。 最後に、今後の課題として、1.1人だけの教育(autonomy)、2.super-maniaにならなくてよい、3.英作文にE-mailをとり入れる、4.テレビを通してのDistance English Education Program(DEEP)での仕上げ、があげられた。(小田幸信:関西外国語大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業研究
『環境問題自主教材作成のこつ:インターネットの有効利用』
溝畑 保之(大阪府立泉南高等学校)
今年度高校1年生英語1とOral Aで扱った環境問題「ダイオキシン」を取り上げた授業がビデオで紹介された。この授業では、特に次の5つの点があげられた。1.大きな共通のスキーマをつくる(日本語での読書、videoを通して)、2.リーディングを核に話題の導入:a 導入の工夫(文字+attention pointerとしての写真、イラストのあるworksheet)、s 現在の知識、d 新しい知識 f 読解worksheetにフレーズごとにslashを入れる、g 語彙の整理、3.下書きから清書へと段階を追ったライティング、4.インタビュー(モデルを提示し、ALT対生徒2人で行ない、残りの生徒は評価者)、5.ホームページ作りへ。
英語1を限りなくOralに近いものに、Oral AをOralを越えた内容のあるものにするという、非常に示唆に富んだ発表であった。(小田幸信:関西外国語大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業研究
『早期英語教育の視聴覚教材開発について』
高森 省三(ELK英語王国代表)
幼児または小学生に対する英語教育に的を絞って「英語ペラペラ教育」を成功させるために次の3点が強調された。1.「音声教育」と「文字教育」を車の両輪として、話せる教育を強力に推進する。2.その信念に基づき、会話や読み書きが習える教材の開発を進めていく。そのために指マークのついた幼児でも読める英語の絵本や、フラッシュカードなどを考案する。3.教室だけではなく、市町村や家庭を結びつけ、文法にこだわらないで楽しいムード作りができる発表の場を作る(町民英語劇、カラオケ大会など)。
発表最後の部分で、山陽学園大学の学生数名を幼児に見立て、指マークをつかって英語絵本やフラッシュカードを用いる「表現中心」の効果的な指導法が実演された。次に紹介されたdynamicでspeedyな英語のみによるELK英語王国の幼児と高森先生の会話のビデオに我々参加者は思わず引き込まれていった。(小田幸信:関西外国語大学)
--------------------------------------------------------------------------------
講演
『高度情報社会における情報メディアの教育利用』
坂元 昂(文部省メディア教育開発センター所長)
標記のタイトルでの文部省メディア教育開発センター所長坂元昂氏の講演は、詳細なレジュメに基づく、壮大なスケールのものであった。講演は以下の大きな5つの項目を軸に展開した。a 最近の教育における情報技術活用に関する政策の展開、s 情報通信技術の教育利用の現状、d 大学改革、f スペース・コラボレーション・システムによる遠隔教育、そして g 宇宙からの大学改革、である。
a は、1998年4月以降、文部省関係の審議会懇談会等から発表された、情報技術とメディア教育の分野における教育改革への提言の概観であった。各提言をここで紹介することは不可能だが、それらすべてを総括して坂元氏は、「『受ける学び』から『選ぶ学び』『造る学び』への変革が提言されている」と述べられた。
s では、初期には教師が教え込む機能を拡大したものとしてCAIが多かったコンピュータの教育利用が、この数年95年に始まった「100校プロジェクト」、96年に始まり1014校をインターネットとテレビ会議システムで結んでいる「こねっとプラン」等、より幅広い機能を持つ道具として急速に活用されるようになってきた現状が紹介された。
d f g は、情報通信技術を活用した、現在すでに始まり、また将来に向けて構想される、大学・大学院教育改革に関わる一連の動きの紹介である。これらの改革の基盤にあるのがスペース・コラボレーション・システム(SCS)、つまり全国110の高等教育機関に設置されている133のVSAT局を通信衛星で結び、どこの大学からでも同時にいくつもの大学と授業を交換できるシステムである。このシステムはすでに大学院教育において活用されているということで、実例として、平成9年度のSCS大学間遠隔共同講義「大学院・教育工学特別講義」が紹介された。このような遠隔講義が増え、単位互換の上限枠がはずれれば、ひとつの大学院に所属しながら別の大学院の講義だけで全単位を取得することも可能になり、特定の大学院に入学、終了の意味が薄れる。「日本遠隔連合大学院」に入学、修了した、という表現が適切になる時がきそうだと坂元氏は予測する。
学生、院生が、自分の欲しい情報を日本じゅうの大学から選択的に手に入れる時代になれば日本全国から情報をもとめられる大学は評価を高め、そうでない大学は影がうすくなり、さらに、インターネット経由で修士号の取得が可能になる海外の大学が増えるにつれ、日本の大学が、日本在住の学生をめぐって世界中の大学と競合する可能性も示唆された。「まさに、宇宙からの大学改革が始まっている」との力づよい言葉で講演は締めくくられ、「うかうかしてはいられない」と感じた聴衆も多かったのではないだろうか。(静 哲人:関西大学)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジアム
『岡山情報ハイウエイをめぐって』
平成10年10月31日、山陽学園大学において開催された研究大会のシンポジウムについて報告する。テーマは「岡山情報ハイウエイをめぐって」と題し、シンポジストの新免國夫氏(岡山県振興部情報政策課長)、山北次郎氏(岡山県立大学情報工学部 教授)、小寺裕之氏(岡山県立総社南高等学校 教諭)の3氏と司会の北村 裕氏(関西大学教授)によって行われた。
「岡山情報ハイウエイ」とは、光ファイバーで岡山県庁を基幹に各地方振興局を結び、CATV・公衆回線を利用し、インターネットによって家庭、学校、病院、企業等に接続する情報ネットワークのことである。
新免氏はこのプロジェクトの政策責任者の立場から、山北氏は技術開発責任者の立場から、小寺氏は高校現場における利用者の立場から、それぞれ発表された。
新免氏は、行政目的として a 地域の情報間格差の是正と解消、s 県民生活の利便性の向上、d 地域の活性化と諸問題の解決、以上3点を行政の大きな責任と捉え、また情報インフラに民間ではなく県自らがかかわることに意義があると主張された。特に、本年10月13日に県立諸学校の全生徒・全教員にパスワードが支給され、インターネットが利用できるようになり、さらに市町立の小・中学校にも拡大していく予定であることを強調された。
山北氏は、光伝送情報工学を専門とし、技術的側面より発表され、今後は単なるデータ通信だけではなくマルチメヂアに対応した情報伝送技術の向上と蓄積に努力していきたい、これはユーザからは目に見えないものではあるが県主導で行っていくことに意義があり、ユーザーは無料で利用できることが重要と述べられた。しかし伝送速度の技術的問題から現在のところテレビ会議においては問題が起こる可能性があり、この点においては今後のインフラ整備が急がれるところである。しかし各地域のケーブルテレビ局が積極的に県の幹線に参加していることは喜ばしいことであり、今後の技術的向上が期待されると締めくくられた。
小寺氏は高校現場の授業におけるインターネット、並びにEメール利用の実践例、またベネッセとの産学協同事業の1つであるテレビ会議システムを利用しての遠隔英会話授業の実験校として、その授業内容と生徒の反応についての発表をされた。生徒の評価はどちらも高いものではあるが、インターネットの利用においては1つ問題があり、それはいわゆるフィルタリングの問題で現在のところ県が掛けているものが厳しすぎ、見たいもの・見せたいものが生徒に提供できない、例えば、美術館にアクセスしてもその中に裸婦の絵画があればフィルターが利いて見ることができない状態であり、教育現場におけるフィルタリングについてのコンセプトが今後の大きな問題点であると述べられた。
以上3氏の発表を受け、フロアーからつぎのような質問があった。a Eメールを利用する場合のネチケットの問題、トラブルが発生した場合の対処の仕方、s 公立高校が産学協同の名の元に企業と手を組むのはいかがなものか、d 持てるものと待たざるもの、rich or poor informationを生み出す可能性が大きくなるのではないか、また司会の北村氏よりインターネットを利用することのメリットとデメリットはどのようなものか、Eメールによる授業展開はうまく行っているかとの諮問が出された。
a についてはリスクの問題であり、新免氏はインターネット・Eメールは基本的には個人にかかわるものであり自由に使わせ、インターネットのすばらしさを実感させたい、しかしネチケット教育は大事であり、フィルターにも配慮している、情報リテラシーを上げることが重要であると答えられ、北村氏はインターネットも電話と同じであると考えれば多少のリスクも覚悟しなければないかと答えられた。s について、新免氏からモデル事業の1つの試みであり問題はない、ただ僻地にある学校で1人の外国人に出会うこともないような地域ではこの遠隔英会話授業は利用価値があるのではないか、小寺氏は今後いかに充実させ生かしていくかが課題であると答えられた。d については新免氏は重要な問題であり、配慮しなければならない今後の課題であると回答された。北村氏の質問に対し、山北氏がネットワーク管理・サーバー管理を誰が行うのかの問題になる、また小寺氏よりメールを送る相手の問題もあり一概にうまくいっているとは言えないと答えられた。
最後に、司会の北村氏より国の施策を県が先取りし、県単位でこのようなネットワークを最初に立ち上げ、持つことは非常に大きな意義があり、今後全国のモデル事業として注目されることになるであろうとのまとめをもって、このシンポジウムは締めくくられた。(齊藤泰成:岡山県立瀬戸高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
会場校からの声
『会場校を引き受けて』
会場校を引き受けて 能登原 昭夫(山陽学園大学)
1998年10月31日(土)、LLA関西支部秋季研究大会が岡山市の山陽学園大学で開催されました。中国路での大会ということもあって、多数のご参加をいただきありがとうございました。なにぶんローカルの小規模大学のやることですから、何につけてもチマチマ、モタモタしまして皆さんの意にかなうことはできませんでしたが、もう二度と引き受けることはあるまいと思って、思う存分やりたいことをさせてもらいました。河野支部長、神崎事務局長をはじめ、役員諸先生方のご指導、ご協力そして寛容さに改めて感謝する次第です。
プログラムを構成するに先立って、考えたことが2つあります。①マルチメディア/情報通信をテーマとしたい。②岡山県の特色を出したい、ということでした。①についてはLLAが外国語教育メディア学会と名称変更になることから、従来のLLAを超えた何かを指向してみたい。②については、好都合なことに岡山県が行政として「岡山情報ハイウエイ構想」を進めていたのでプログラムの全体構想は比較的簡単に得られたものの、講演、講師、シンポジウムとシンポジスト、と段取りを進めていくにつれて難渋することも多くなりました。最後は独断と偏見で交渉しましたが、坂本昂先生が講演をO.K.してくださったときは、正直にいってホッとしました。しかも講演のテーマがどんぴしゃりでした。
シンポジウムのほうも、皆さん多忙なお方ばかりで、何度も足を運んでお頼みしました。お蔭で岡山はここまで進んでいるという事実を伝えることができました。その分だけ、研究発表が軽くなりましたが「メディアの有効利用と教材開発」という観点から絞りました。「メディアと人間」というサブテーマを持っていたのですが今回は見送りました。私のCAI教室も多数の方に参観していただき光栄でした。2月中には機器をヴァージョンアップして新学期から「情報英語」という講座を立ち上げます。TV会議システムの利用も、新プロゼクトを組んで続行します。
夕方からの懇親会も大勢残ってくださり、もりあがりました。備前の銘酒「雄町(おまち)」が好評で足らなくなり、追加を買いに走ったことを報告しておきます。
『テレビ会話システムの英語教育への応用:山陽学園大学の試み』
能登原 昭夫(山陽学園大学)
初めに、山陽学園大学の歴史と理念に基づいた21世紀英語教育へのvanguardとして、最先端に挑戦していく決意が述べられた。具体的には、1.組織+カリキュラム(ALPS)-CAI+DEEP/機器と教材、2.Tele-conference/video-conference/TV会議システム/遠隔教育についての説明があり、次いで、それに基づいた2つの実験概要の中間報告がなされた。
これらの実験は、単なる4技能ではなく、totalでintegrateされたcommunicativeなcontentに力を注ぎ、学生のautonomy(self-deirected learning)を最終目標とするものである。1年次はremedial stageとし、2年次ではLL開発によるspeed reading program(1分間に読める語数を150,200,300と増やしていく)に従い、学生各自が楽しみをもって学習し、学年末には85%以上の学生が合格点に達した。
3年次、4年次では、E-mailが瞬間に読めるようになることを目標とした。tele-conference/video conference programでは、英検準1級一次試験を合格した4人の4年次学生が選ばれ、Berlitz Okayamaと協同しての会話実験がビデオで紹介された。 最後に、今後の課題として、1.1人だけの教育(autonomy)、2.super-maniaにならなくてよい、3.英作文にE-mailをとり入れる、4.テレビを通してのDistance English Education Program(DEEP)での仕上げ、があげられた。(小田幸信:関西外国語大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業研究
『環境問題自主教材作成のこつ:インターネットの有効利用』
溝畑 保之(大阪府立泉南高等学校)
今年度高校1年生英語1とOral Aで扱った環境問題「ダイオキシン」を取り上げた授業がビデオで紹介された。この授業では、特に次の5つの点があげられた。1.大きな共通のスキーマをつくる(日本語での読書、videoを通して)、2.リーディングを核に話題の導入:a 導入の工夫(文字+attention pointerとしての写真、イラストのあるworksheet)、s 現在の知識、d 新しい知識 f 読解worksheetにフレーズごとにslashを入れる、g 語彙の整理、3.下書きから清書へと段階を追ったライティング、4.インタビュー(モデルを提示し、ALT対生徒2人で行ない、残りの生徒は評価者)、5.ホームページ作りへ。
英語1を限りなくOralに近いものに、Oral AをOralを越えた内容のあるものにするという、非常に示唆に富んだ発表であった。(小田幸信:関西外国語大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業研究
『早期英語教育の視聴覚教材開発について』
高森 省三(ELK英語王国代表)
幼児または小学生に対する英語教育に的を絞って「英語ペラペラ教育」を成功させるために次の3点が強調された。1.「音声教育」と「文字教育」を車の両輪として、話せる教育を強力に推進する。2.その信念に基づき、会話や読み書きが習える教材の開発を進めていく。そのために指マークのついた幼児でも読める英語の絵本や、フラッシュカードなどを考案する。3.教室だけではなく、市町村や家庭を結びつけ、文法にこだわらないで楽しいムード作りができる発表の場を作る(町民英語劇、カラオケ大会など)。
発表最後の部分で、山陽学園大学の学生数名を幼児に見立て、指マークをつかって英語絵本やフラッシュカードを用いる「表現中心」の効果的な指導法が実演された。次に紹介されたdynamicでspeedyな英語のみによるELK英語王国の幼児と高森先生の会話のビデオに我々参加者は思わず引き込まれていった。(小田幸信:関西外国語大学)
--------------------------------------------------------------------------------
講演
『高度情報社会における情報メディアの教育利用』
坂元 昂(文部省メディア教育開発センター所長)
標記のタイトルでの文部省メディア教育開発センター所長坂元昂氏の講演は、詳細なレジュメに基づく、壮大なスケールのものであった。講演は以下の大きな5つの項目を軸に展開した。a 最近の教育における情報技術活用に関する政策の展開、s 情報通信技術の教育利用の現状、d 大学改革、f スペース・コラボレーション・システムによる遠隔教育、そして g 宇宙からの大学改革、である。
a は、1998年4月以降、文部省関係の審議会懇談会等から発表された、情報技術とメディア教育の分野における教育改革への提言の概観であった。各提言をここで紹介することは不可能だが、それらすべてを総括して坂元氏は、「『受ける学び』から『選ぶ学び』『造る学び』への変革が提言されている」と述べられた。
s では、初期には教師が教え込む機能を拡大したものとしてCAIが多かったコンピュータの教育利用が、この数年95年に始まった「100校プロジェクト」、96年に始まり1014校をインターネットとテレビ会議システムで結んでいる「こねっとプラン」等、より幅広い機能を持つ道具として急速に活用されるようになってきた現状が紹介された。
d f g は、情報通信技術を活用した、現在すでに始まり、また将来に向けて構想される、大学・大学院教育改革に関わる一連の動きの紹介である。これらの改革の基盤にあるのがスペース・コラボレーション・システム(SCS)、つまり全国110の高等教育機関に設置されている133のVSAT局を通信衛星で結び、どこの大学からでも同時にいくつもの大学と授業を交換できるシステムである。このシステムはすでに大学院教育において活用されているということで、実例として、平成9年度のSCS大学間遠隔共同講義「大学院・教育工学特別講義」が紹介された。このような遠隔講義が増え、単位互換の上限枠がはずれれば、ひとつの大学院に所属しながら別の大学院の講義だけで全単位を取得することも可能になり、特定の大学院に入学、終了の意味が薄れる。「日本遠隔連合大学院」に入学、修了した、という表現が適切になる時がきそうだと坂元氏は予測する。
学生、院生が、自分の欲しい情報を日本じゅうの大学から選択的に手に入れる時代になれば日本全国から情報をもとめられる大学は評価を高め、そうでない大学は影がうすくなり、さらに、インターネット経由で修士号の取得が可能になる海外の大学が増えるにつれ、日本の大学が、日本在住の学生をめぐって世界中の大学と競合する可能性も示唆された。「まさに、宇宙からの大学改革が始まっている」との力づよい言葉で講演は締めくくられ、「うかうかしてはいられない」と感じた聴衆も多かったのではないだろうか。(静 哲人:関西大学)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジアム
『岡山情報ハイウエイをめぐって』
平成10年10月31日、山陽学園大学において開催された研究大会のシンポジウムについて報告する。テーマは「岡山情報ハイウエイをめぐって」と題し、シンポジストの新免國夫氏(岡山県振興部情報政策課長)、山北次郎氏(岡山県立大学情報工学部 教授)、小寺裕之氏(岡山県立総社南高等学校 教諭)の3氏と司会の北村 裕氏(関西大学教授)によって行われた。
「岡山情報ハイウエイ」とは、光ファイバーで岡山県庁を基幹に各地方振興局を結び、CATV・公衆回線を利用し、インターネットによって家庭、学校、病院、企業等に接続する情報ネットワークのことである。
新免氏はこのプロジェクトの政策責任者の立場から、山北氏は技術開発責任者の立場から、小寺氏は高校現場における利用者の立場から、それぞれ発表された。
新免氏は、行政目的として a 地域の情報間格差の是正と解消、s 県民生活の利便性の向上、d 地域の活性化と諸問題の解決、以上3点を行政の大きな責任と捉え、また情報インフラに民間ではなく県自らがかかわることに意義があると主張された。特に、本年10月13日に県立諸学校の全生徒・全教員にパスワードが支給され、インターネットが利用できるようになり、さらに市町立の小・中学校にも拡大していく予定であることを強調された。
山北氏は、光伝送情報工学を専門とし、技術的側面より発表され、今後は単なるデータ通信だけではなくマルチメヂアに対応した情報伝送技術の向上と蓄積に努力していきたい、これはユーザからは目に見えないものではあるが県主導で行っていくことに意義があり、ユーザーは無料で利用できることが重要と述べられた。しかし伝送速度の技術的問題から現在のところテレビ会議においては問題が起こる可能性があり、この点においては今後のインフラ整備が急がれるところである。しかし各地域のケーブルテレビ局が積極的に県の幹線に参加していることは喜ばしいことであり、今後の技術的向上が期待されると締めくくられた。
小寺氏は高校現場の授業におけるインターネット、並びにEメール利用の実践例、またベネッセとの産学協同事業の1つであるテレビ会議システムを利用しての遠隔英会話授業の実験校として、その授業内容と生徒の反応についての発表をされた。生徒の評価はどちらも高いものではあるが、インターネットの利用においては1つ問題があり、それはいわゆるフィルタリングの問題で現在のところ県が掛けているものが厳しすぎ、見たいもの・見せたいものが生徒に提供できない、例えば、美術館にアクセスしてもその中に裸婦の絵画があればフィルターが利いて見ることができない状態であり、教育現場におけるフィルタリングについてのコンセプトが今後の大きな問題点であると述べられた。
以上3氏の発表を受け、フロアーからつぎのような質問があった。a Eメールを利用する場合のネチケットの問題、トラブルが発生した場合の対処の仕方、s 公立高校が産学協同の名の元に企業と手を組むのはいかがなものか、d 持てるものと待たざるもの、rich or poor informationを生み出す可能性が大きくなるのではないか、また司会の北村氏よりインターネットを利用することのメリットとデメリットはどのようなものか、Eメールによる授業展開はうまく行っているかとの諮問が出された。
a についてはリスクの問題であり、新免氏はインターネット・Eメールは基本的には個人にかかわるものであり自由に使わせ、インターネットのすばらしさを実感させたい、しかしネチケット教育は大事であり、フィルターにも配慮している、情報リテラシーを上げることが重要であると答えられ、北村氏はインターネットも電話と同じであると考えれば多少のリスクも覚悟しなければないかと答えられた。s について、新免氏からモデル事業の1つの試みであり問題はない、ただ僻地にある学校で1人の外国人に出会うこともないような地域ではこの遠隔英会話授業は利用価値があるのではないか、小寺氏は今後いかに充実させ生かしていくかが課題であると答えられた。d については新免氏は重要な問題であり、配慮しなければならない今後の課題であると回答された。北村氏の質問に対し、山北氏がネットワーク管理・サーバー管理を誰が行うのかの問題になる、また小寺氏よりメールを送る相手の問題もあり一概にうまくいっているとは言えないと答えられた。
最後に、司会の北村氏より国の施策を県が先取りし、県単位でこのようなネットワークを最初に立ち上げ、持つことは非常に大きな意義があり、今後全国のモデル事業として注目されることになるであろうとのまとめをもって、このシンポジウムは締めくくられた。(齊藤泰成:岡山県立瀬戸高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
会場校からの声
『会場校を引き受けて』
会場校を引き受けて 能登原 昭夫(山陽学園大学)
1998年10月31日(土)、LLA関西支部秋季研究大会が岡山市の山陽学園大学で開催されました。中国路での大会ということもあって、多数のご参加をいただきありがとうございました。なにぶんローカルの小規模大学のやることですから、何につけてもチマチマ、モタモタしまして皆さんの意にかなうことはできませんでしたが、もう二度と引き受けることはあるまいと思って、思う存分やりたいことをさせてもらいました。河野支部長、神崎事務局長をはじめ、役員諸先生方のご指導、ご協力そして寛容さに改めて感謝する次第です。
プログラムを構成するに先立って、考えたことが2つあります。①マルチメディア/情報通信をテーマとしたい。②岡山県の特色を出したい、ということでした。①についてはLLAが外国語教育メディア学会と名称変更になることから、従来のLLAを超えた何かを指向してみたい。②については、好都合なことに岡山県が行政として「岡山情報ハイウエイ構想」を進めていたのでプログラムの全体構想は比較的簡単に得られたものの、講演、講師、シンポジウムとシンポジスト、と段取りを進めていくにつれて難渋することも多くなりました。最後は独断と偏見で交渉しましたが、坂本昂先生が講演をO.K.してくださったときは、正直にいってホッとしました。しかも講演のテーマがどんぴしゃりでした。
シンポジウムのほうも、皆さん多忙なお方ばかりで、何度も足を運んでお頼みしました。お蔭で岡山はここまで進んでいるという事実を伝えることができました。その分だけ、研究発表が軽くなりましたが「メディアの有効利用と教材開発」という観点から絞りました。「メディアと人間」というサブテーマを持っていたのですが今回は見送りました。私のCAI教室も多数の方に参観していただき光栄でした。2月中には機器をヴァージョンアップして新学期から「情報英語」という講座を立ち上げます。TV会議システムの利用も、新プロゼクトを組んで続行します。
夕方からの懇親会も大勢残ってくださり、もりあがりました。備前の銘酒「雄町(おまち)」が好評で足らなくなり、追加を買いに走ったことを報告しておきます。