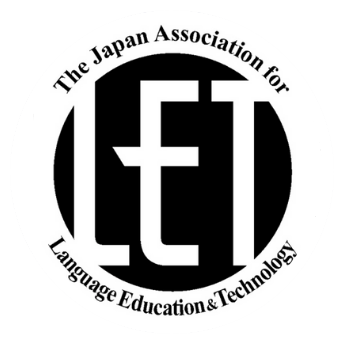大会名
01年度秋季研究大会
大会(春・秋・全国)
秋季大会
日付
2001年10月20日
会場
四国大学
概要
01年度秋季大会は、2001年10月20日(土) に四国大学で開催されました。コーパス研究の第一人者である中村純作先生(徳島大学)の「コーパスからどのような情報が得られるのか:LOB Corpus の語彙の銀河」と題する講演、古田八重先生(四国大学)の「英語教師のためのやさしいコーパス:実践編」ワークショップ、Kevin Miller 先生(四国大学)による 'Hot Potatoes' (Web-based Software) 利用に関するワークショップを始めとして、研究発表4件の盛りだくさんの内容でした。当日は天気にも恵まれ、西は広島から、東は滋賀、奈良まで関西支部全域から54名の会員諸氏の参加を得ました。皆さんのご協力に感謝いたします。詳細は下記をご覧下さい。
詳細
講演
「コーパスからどのような情報が得られるのか:LOB Corpus の語彙の銀河」
中村純作(徳島大学総合科学部教授)
中村先生とは小生は1977年からのおつきあいで、特に先生が20数年間、大型コンピュータの時代から、研究ツールから始まり、メタ言語、統計理論の学習、学内外の予算獲得・環境整備などのご苦労を一番共感しているものと思い、今回事務局長から講演要旨作成依頼を快諾した次第です。先生が「コーパス言語学」をライフワークにされた動機は、講演でも紹介があったが、「変形文法」を学習するにあたり、“native speakers’intuition”が文法性判断の拠り所となる点では、英語を第二言語とする日本人には研究の「限界」があるとし、コーパス研究に邁進されたという。先生はこの分野の屈指の研究者で、1993年4月に発足の英語コーパス学会(Japan Association for English Corpus Studies、会員数現在200名)の設立のいわば生みの親的先駆者でもあり、現在は同学会の運営委員、事務局担当として活躍されています。
講演を通じて特に感銘を受けた点は、参加者大部分がコーパス言語学については「素人」であることを前提に、統計分析方法を説得性のあるシミュレーションを駆使しながらの、パワーポイントによるプリゼンテーションされたことと、ご自身の研究テーマに対する熱情が随所に見られたことでした。
まず、講演はコーパス言語学・英語学の歴史と概要の説明に始まり、ご自身のライフワークとしての挑戦、コーパス資料入手・苦心談を織りまぜながら聴衆をリラックスさせる導入でしたが、すでに参加者は18頁にも及ぶ資料の重厚さに圧倒されつつありました。
先生によれば、コーパス研究が学問分野として確立するのは1980年代に入ってからで、ノルウェイのベルゲン大学に設置されているICAME (International Computer Archive of Modern and Medieval English)を中心とした学会活動に負うところが大きく、それも、「質的」からの「量的」研究への飛躍であったという。
講演の第2部では、その「量的」研究として、「林数量化理論」による実データの解析方法を詳説された。30分程度の講演では難解の感があったが、シミュレーションと解析行列表とカテゴリーの分布図による数々のスライド提示はリアルな説得性に富み、参加者の林数量化理論、コーパス研究への興味を倍増したに違いない。
そして、本題の「LOB Corpusの語彙の銀河」へと続いた。それは、LOBコーパスの15のジャンルにわたる英語単語(動詞・名詞、形容詞)の頻度と出現ジャンルの対応解析で、「探求型データ解析」の研究発表であった。統計手法には対応分析を用い、単語の頻度(量的データ)に、ジャンル(質的データ、カテゴリー)との連関に関するノンパラメトリック多変量解析で、例えば、「どの動詞がどのジャンルに偏って分布しているのか」、あるいは、「どの動詞がすべてのジャンルに均等に使用される一般的なものであるのか」などを「発見」することが目的とされた。データはコーパスから抽出、形態素分析加工を経て、例えば動詞では約4,000に限定され、その解析をコーパスのジャンル上での相対頻度との対応傾向を表す数種の散布図に提示された。そこでは、単語の各ジャンルでの相対頻度の座標点が順次コンピュータ画面に描き出され、いわば星雲を形成する様が、講演のタイトルの「語彙の銀河」につながるという「感傷的」な言及があった。それは、20年前のテレタイプ・ラインプリンターでは味わい得ない、グラッフィック画面の技で、それもパソコンでの実現に感嘆したのは小生だけではなかったはずである。ちなみに、この「銀河」という語呂あわせは、英文タイトル、“Semantic Galaxy of the LOB Corpus”として、ICAME第19回大会(於:北アイルランドのベルファスト)での先生の特別講演・発表が元であったようである。(徳大広報 No. 94)
「コーパスを使って数量的な分析を行うと、英文学や、英語学の分野での新しい事実がいろいろ発見される」という、ロマン溢れるコーパス研究の実証解析研究の熱演講演であった。
本大会では、この講演に先立ち、午前には、古田八重先生(四国大学)の「英語教師のためのやさしいコーパス:実践編」の講習があり、まさに徳島コーパス言語学の研究成果・エネルギーの息吹を淡路海峡の渦潮のごとく満喫(目を回した?)できたといえよう。その意味でも本大会は成功裏に終わったといえ、企画、開催の準備をして下さった関係諸氏に感謝の意を表するものである。(安田雅美 関西学院大学)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 1
「英語教師のためのやさしいコーパス実践編:WordSmith Tools(V.3.0)を使って」
古田八恵(四国大学)
10月20日10時半からのコーパスを用いた講習は、50台のコンピュータ室がほぼ満室になるほどの盛況であった。講習は最初の10分間はコーパスの英語教育への利用として、ことばにはcollocationのみならず、語彙と構文、語彙と意味の相互依存を意味するcolligationやsemantic prosodyの特徴を備えていること, できるだけ多くの実際に用いられている言語に接すること、そのためにはコンピュータ・コンコーダンスを利用することが望ましいとの説明がなされた。
続いて市販されているコーパスICAME Collection of English Language Corporaの中にあるBrown Corpusを対象に分析ソフトWordSmith Toolsを用いて、実際に検索をし、コンコーダンスラインの見方、ソートの仕方、ソートしたコンコーダンスから何を見るかなどの基本的な説明がなされた。WordSmith Toolsにはcollocation、patterns、clusters、plotなどの機能があり、それぞれの解説を聞きながら一つずつ実際に操作することができた。次に同じICAME Collectionの中にあるWellington Corpusを加えてBrown CorpusとWellington CorpusのWordListを作成した。WordListではABC順、頻度順、テキストの文体の特徴を統計数値としてまとめてあるSummary and Statisticsの3種類のリストを作成することができた。最後にBrown Corpusに対するWellington CorpusのKeyWordsを作成した。Key Wordsはmost unusually frequent wordsを表示するもので、特定のテキストまたはジャンルの語彙の特徴を知るのに役立つものである。
すべての作業は丁寧に作成されたハンドアウトに詳しくまとめられており、さらにPowerPointで作成された操作手順をモニター画面に写し出しての講習であったため、初心者にも大変わかりやすいワークショップであったと思われる。このワークショップを機会にコーパスに関心を持ち、英語教育に利用しようとするLETの会員が増えたのではないかと思う。初心者には大変有意義なコーパスワークショップであった。古田先生には第2弾を期待したいものだ。(岡田和子 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 2
“Introduction to“Hot PotatoesTM”, a Web-based Software for Creating Language Exercises”
Kevin Miller (四国大学)
The“Hot Potatoes”presentation was a short introduction to an easily available shareware that can help CALL teachers author their own interactive language activities.“Hot PotatoesTM”is a product of Half-baked Software, and was developed by Stewart Arneil and Martin Holmes of the University of Victoria in British Columbia, Canada. The software is available by download from the Internet and permits language educators to create six kinds of interactive exercises: multiple-choice, short answer, jumbled sentences, crossword puzzle, matching, and gap-fill (cloze). After the teacher creates the exercises, the students access them from their classroom's server computer, display them on their net browser, and work on the exercises independently. The exercises can also be linked to websites for access by any computer. The advantage of using“Hot PotatoesTM”compared to commercially produced CALL learning materials is that the teacher can custom-make exercises that activate the language the teacher wishes to use. With a little practice, teachers can quickly make original browser-based exercises, including drag and drop versions, that have the look and feel of commercially produced computer media software.
The Hot Potatoes presentation included:
1)A demonstration of several types of activities created with“Hot Potatoes Version 5”
2)Time for participants to try all six types of Hot Potatoes activities themselves
3)A demonstration on how to create original matching activities, English-English, Japanese-English, and Pictures-English, using“Hot Potatoes Version 5”
4)A handout of the“Hot Potatoes”website: http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
Hot Potatoes may be a useful authoring tool for some, but perhaps not all, CALL teachers. Advantages to using the software are that it's easy to download from the Internet, and it's easy to understand the procedure for making activities. It's also a“free”shareware, if the users agree to post their Hot Potatoes activities on websites for access by the general public. There are a few negatives, however. One of the most serious problems is the lack of a means to monitor a student's output. There is currently no function that records how much of an activity a student has completed, nor is there any way to record grades. The software seems to be designed for free-access sites where students use the activities at their own pace, for their own study purposes. A second, minor inconvenience is the necessity to use the Unicode function when inputting Japanese. Doing so makes the Japanese characters unreadable at the authoring stage, and they only become visible after the activities have been saved as html files. This is especially inconvenient if the author has made a kanji input mistake, as one has to go back to the original document, edit, and save it again as html. Finally, completed activities have a rather simple, homogenous look, that is not very visually attractive, compared to currently available animated websites. Users can change the colors of the pages, but the overall look remains rather simple by prevailing website standards. It should also be noted that the drag-and-drop functions will not work on some of the older versions of Netscape Navigator. Still, Hot Potatoes can be a useful tool for those who wish to author their own browser-based interactive activities, but lack the time or desire to do their own programming.(Kevin Miller 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第1室
「自営のWWWサイトを活用した英語授業運営」
Michael Shawback(立命館大学)、荒瀬美佐子(立命館大学)
立命館大学理工学部には英語の必修科目が10科目設けられ、全て統一教材、統一シラバス、統一評価法で運営されている。しかも10科目中8科目が教員による科学技術英語の自主開発教材である。それにより科目間の連携が強く保たれ、理工学部の学生に合ったオーダーメードの教材となっている。
対象学生は1学年1500人で合計3000人で、それぞれの科目が習熟度別に3レベルに分けられており、専任・常勤・非常勤の総勢約50名が「自営の英語サイト:English Expeditions [http://www. ee.ritsumei.ac.jp/]」により足並みを揃えて授業を進行している。
このサイトには次のメニューが用意されている。
<COURSES>3レベルのコースがあり、それぞれのコース内の開講科目について受講生は概要、評価基準、授業日程、履修上の注意が随時参照できる。教員は、各回の授業での学生の作業の成績をOn-line Grading Systemで管理でき、それらを集積して学期末の評価とすることができる。
<GRADES>教員は自動座席作成・成績記入システムを用いて自由に座席表を作成でき、出席回数も管理できる。成績管理では、クラス統計棒グラフで、現時点での各学生の100点満点換算(%)の成績表示ができる。また、教員は、ある担当科目の全クラスの平均(教員のみ閲覧)と自分のクラスとを比較することで授業の自己評価ができ、教員間の成績評価についての打合せの必要がない。これに対して、学生は自分の成績とクラスの平均点を開講期間中随時閲覧でき、例えば50点なら「もう少しがんばろう!」とのメッセージが出る。
<EMAIL GUIDE>担当者がリレー方式でe-mailのガイドラインをもとにライティングを指導しており、合計24回学生に提出させる。提出課題は担当者によって評価され、集中管理システムによるクラスの成績一覧表が作成される。さらにfeedback reportでcommon errors(8から10件)が受講生に直接メールで送信され、同時に英語科へも誤答データとして送信・蓄積される。
<RESOURCES>Communication Linksでは、テキスト関連サイトについて担当者のサイトリヴュー入の紹介がされ、Science Sitesでは、学生による自分の専攻の関連サイトの紹介がされている。<DISCUSSIONS>理工学部の中だけで英語によるフォーラムに参加することができ、その方法はCALLクラスで指導されている。(吉田信介 摂南大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第1室
「ネットワークを利用した自習用英語教材の開発:中級編」
片山真理(関西国際大学)、野澤 健(関西国際大学)、佐々木緑(関西国際大学)、有本 純(関西国際大学)
本研究は、既に発表された「初級編」に続くネットワーク自習用教材開発の研究である。「初級編」が辞書の使い方、基本語彙、文法基礎の3つのセクションから構成されていたのに対し、「中級編」は リスニング、リーデイング、文法、ライテイングの4つのセクションから成り立つ。両者ともに、新入生全員がノートパソコンを購入、情報処理授業必修という同学の環境下で、学生が学内外から自由な時間にアクセスできることを目指している。 リスニング編は基礎力の向上を目的とし、導入、解説・練習問題、補足問題の3つから構成される。まず、日本語と英語の音声上の相違を認識させるための外来語と英語の比較から始まり、次いで、音の連結、脱落、同化等の主要な音声変化に焦点を絞って、具体例(クリックすれば音声が聞こえる)を用いた平易な解説の後、練習問題へと進む。最後に、聞き取りから意味理解へ繋げるための補足問題が提示される。
リーデイング編は、長い文章の読解を苦手とする学生対象の、オンライン上でのパラグラフリーデイングである。文章の提示とその解説、2種の練習問題から成る。Exercise I は Topic Sentenceから段落の趣旨を予測しその文を Topic Sentence とする段落を探す問題で、Exercise II は、内要理解チェック問題である。 文法編は、中級学習者の英作文に見られる文法の誤りを中心に扱い、既習の文法知識を実際の言語使用に繋げることを目的とする。メニュー選択画面上の13のレッスンから学習する画面を選び、導入問題 → 解答・解説 → 確認問題(QUIZ → ヒント → 解答)へと進む。答えを解答欄にタイプし終わると直接、解答画面へ進むことも、またヒントを参照した後、答えをタイプし、解答画面へ進むこともできる。解答画面から、もう一度QUIZ画面へ戻ることもできるし、次の問題へ進むこともできる。
ライテイング編は、高等学校学習指導要領に示された言語機能の中から8つを選び、和文英訳でない、場面に適した英語表現能力の養成を目指す。メニュー画面から学習したい表現を選び、その機能項目画面に入ると、写真入りの「語彙と表現の画面」が提示される。この基本学習が終わると、与えられた状況に適した英語表現の練習問題を行う。解答は、文法編と同じく、英文をキーボードから入力して行う。ヒント、解答・解説画面についても文法編の場合と同じである。
本研究はパソコンのセルフスタデイ機能を活用した非常に意欲的な試みである。難しい/重要な事柄を、学生のニーズに合致するようネットワーク上で親しみやすく/学習しやすく噛み砕き、以て学習意欲を高め、総合的な英語力の補強を実現したいという熱意と苦心の程がうかがわれる。近年、大学生全般の学力低下が指摘され、何らかの適切な対応の必要性が強調されている中で、このような自主教材の開発は注目に値する。今後、この「中級編」が学生たちにどのように活用されるか、アクセス状況や活用の成果等、実践上の中間報告に接する機会が与えられれば、本発表の視聴者のみならず多くの語学教育関係者は貴重な指針を与えられることになる。(弓庭喜和子 大阪外国語大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第2室
「Terminologyから入る動機付け英語授業の実践報告」
青木幹生(関西国際大学非常勤)
英語に対する苦手意識を持ち、学習動機の低い大学生を対象とした総合英語授業の実践が報告された。青木先生は、彼らに必要なこと(つまり授業の目的)が、「自信を回復すること」と「英語を学習し直すきっかけを与えること」と考えられ、この2つを確実に授業で提供するために工夫された点を紹介された。
まずは、使用する教材。英語能力の低い学生ではあるが、中学生用の文法教材などを使用するのではなく、天気予報・求人報告など英字新聞よりの切り抜きや、企業の決算報告、航空会社の機内放送などを教材とされている。学生の英語能力のみではなく、知的レベルに合わせた教材選びがなされている。つまり、実社会で使用されている現実的なテーマを扱うことにより、学生の身近に英語が存在することを実感させた上で、文法などの基礎的な情報を補足的に解説するのである。
次に授業の進め方。1時間に1テーマを学習し終えるのではなく、1時間に複数のテーマを導入し、各テーマは数回の授業にかけて継続して学習する。言い換えると、授業内では約15分経過すると次の学習テーマへと移行する。子どもでなくとも、苦手なものには集中力が持続しにくい学生への配慮である。また、新しく学習する内容は、学生が消化できるまで反復して練習される。
そして最後に学期末テスト。平均点が(100点満点中)98点と、難易度の比較的低いテストであるが、既習事項をきちんと復習すれば得点できる(=やればできる)ようにと、意図的に作成されたとのこと。これも、授業目的の1つである「学生の自信を回復すること」の実現に大いに貢献していることになる。授業の目的が達成されていることは、「授業で取り扱うテーマを増やしてほしい」など、学生側から意欲的に授業への要望が示されるようになったとの報告からも明らかなようである。(池田真生子 摂南大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第2室
「Low proficiency学習者のための効果的な英語読解指導法を考える」
福地美奈子(金光大阪高等学校)
英語能力の低い高校生を対象に読解を指導する場合には、内容理解を中心とするよりも、従来から行われている文法訳読を中心とした指導の方が効果的ではないかという福地先生の仮説のもとに、この2つの読解指導法の効果が検証された。被験者は高校3年生2クラス(計61人)。4月の新学期から12月まで、週3回の授業において実施された。内容理解を中心とした指導では、タイトルやイラスト、トピックセンテンス、キーワードなどをもとに本文の内容を理解するように指導された。文法訳読を中心とした指導では、SVOCなどの文型理解と逐語訳が行われた。この2つの指導方法の効果を検討するにあたり、指導の前後に語彙力(Nation, 1990)と内容理解力(自主作成)を測定するためのテストが実施された。t検定の結果、内容理解を中心とした指導を受けたグループは内容理解テストのみにおいて得点が有意に上昇する傾向が見られた。一方、文法訳読を中心とした指導を受けたグループは、語彙力テストのみにおいて同様の傾向が見られた。
このような結果より、文法訳読中心の指導は、内容理解力の即時向上には結びつかないまでも、英文読解の基礎となる語彙力の向上には、より適している可能性が示唆された。語彙力の向上は、とりわけ今回の対象者であった英語能力の低い学習者にとっては、読解力を強化するために重要な点の1つであるだけに、興味深い結果であった。発表の締めくくりには、指導効果の測定方法や指導内容など、今後も改善・検討の必要な事項も報告された。(池田真生子 摂南大学非常勤)
「コーパスからどのような情報が得られるのか:LOB Corpus の語彙の銀河」
中村純作(徳島大学総合科学部教授)
中村先生とは小生は1977年からのおつきあいで、特に先生が20数年間、大型コンピュータの時代から、研究ツールから始まり、メタ言語、統計理論の学習、学内外の予算獲得・環境整備などのご苦労を一番共感しているものと思い、今回事務局長から講演要旨作成依頼を快諾した次第です。先生が「コーパス言語学」をライフワークにされた動機は、講演でも紹介があったが、「変形文法」を学習するにあたり、“native speakers’intuition”が文法性判断の拠り所となる点では、英語を第二言語とする日本人には研究の「限界」があるとし、コーパス研究に邁進されたという。先生はこの分野の屈指の研究者で、1993年4月に発足の英語コーパス学会(Japan Association for English Corpus Studies、会員数現在200名)の設立のいわば生みの親的先駆者でもあり、現在は同学会の運営委員、事務局担当として活躍されています。
講演を通じて特に感銘を受けた点は、参加者大部分がコーパス言語学については「素人」であることを前提に、統計分析方法を説得性のあるシミュレーションを駆使しながらの、パワーポイントによるプリゼンテーションされたことと、ご自身の研究テーマに対する熱情が随所に見られたことでした。
まず、講演はコーパス言語学・英語学の歴史と概要の説明に始まり、ご自身のライフワークとしての挑戦、コーパス資料入手・苦心談を織りまぜながら聴衆をリラックスさせる導入でしたが、すでに参加者は18頁にも及ぶ資料の重厚さに圧倒されつつありました。
先生によれば、コーパス研究が学問分野として確立するのは1980年代に入ってからで、ノルウェイのベルゲン大学に設置されているICAME (International Computer Archive of Modern and Medieval English)を中心とした学会活動に負うところが大きく、それも、「質的」からの「量的」研究への飛躍であったという。
講演の第2部では、その「量的」研究として、「林数量化理論」による実データの解析方法を詳説された。30分程度の講演では難解の感があったが、シミュレーションと解析行列表とカテゴリーの分布図による数々のスライド提示はリアルな説得性に富み、参加者の林数量化理論、コーパス研究への興味を倍増したに違いない。
そして、本題の「LOB Corpusの語彙の銀河」へと続いた。それは、LOBコーパスの15のジャンルにわたる英語単語(動詞・名詞、形容詞)の頻度と出現ジャンルの対応解析で、「探求型データ解析」の研究発表であった。統計手法には対応分析を用い、単語の頻度(量的データ)に、ジャンル(質的データ、カテゴリー)との連関に関するノンパラメトリック多変量解析で、例えば、「どの動詞がどのジャンルに偏って分布しているのか」、あるいは、「どの動詞がすべてのジャンルに均等に使用される一般的なものであるのか」などを「発見」することが目的とされた。データはコーパスから抽出、形態素分析加工を経て、例えば動詞では約4,000に限定され、その解析をコーパスのジャンル上での相対頻度との対応傾向を表す数種の散布図に提示された。そこでは、単語の各ジャンルでの相対頻度の座標点が順次コンピュータ画面に描き出され、いわば星雲を形成する様が、講演のタイトルの「語彙の銀河」につながるという「感傷的」な言及があった。それは、20年前のテレタイプ・ラインプリンターでは味わい得ない、グラッフィック画面の技で、それもパソコンでの実現に感嘆したのは小生だけではなかったはずである。ちなみに、この「銀河」という語呂あわせは、英文タイトル、“Semantic Galaxy of the LOB Corpus”として、ICAME第19回大会(於:北アイルランドのベルファスト)での先生の特別講演・発表が元であったようである。(徳大広報 No. 94)
「コーパスを使って数量的な分析を行うと、英文学や、英語学の分野での新しい事実がいろいろ発見される」という、ロマン溢れるコーパス研究の実証解析研究の熱演講演であった。
本大会では、この講演に先立ち、午前には、古田八重先生(四国大学)の「英語教師のためのやさしいコーパス:実践編」の講習があり、まさに徳島コーパス言語学の研究成果・エネルギーの息吹を淡路海峡の渦潮のごとく満喫(目を回した?)できたといえよう。その意味でも本大会は成功裏に終わったといえ、企画、開催の準備をして下さった関係諸氏に感謝の意を表するものである。(安田雅美 関西学院大学)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 1
「英語教師のためのやさしいコーパス実践編:WordSmith Tools(V.3.0)を使って」
古田八恵(四国大学)
10月20日10時半からのコーパスを用いた講習は、50台のコンピュータ室がほぼ満室になるほどの盛況であった。講習は最初の10分間はコーパスの英語教育への利用として、ことばにはcollocationのみならず、語彙と構文、語彙と意味の相互依存を意味するcolligationやsemantic prosodyの特徴を備えていること, できるだけ多くの実際に用いられている言語に接すること、そのためにはコンピュータ・コンコーダンスを利用することが望ましいとの説明がなされた。
続いて市販されているコーパスICAME Collection of English Language Corporaの中にあるBrown Corpusを対象に分析ソフトWordSmith Toolsを用いて、実際に検索をし、コンコーダンスラインの見方、ソートの仕方、ソートしたコンコーダンスから何を見るかなどの基本的な説明がなされた。WordSmith Toolsにはcollocation、patterns、clusters、plotなどの機能があり、それぞれの解説を聞きながら一つずつ実際に操作することができた。次に同じICAME Collectionの中にあるWellington Corpusを加えてBrown CorpusとWellington CorpusのWordListを作成した。WordListではABC順、頻度順、テキストの文体の特徴を統計数値としてまとめてあるSummary and Statisticsの3種類のリストを作成することができた。最後にBrown Corpusに対するWellington CorpusのKeyWordsを作成した。Key Wordsはmost unusually frequent wordsを表示するもので、特定のテキストまたはジャンルの語彙の特徴を知るのに役立つものである。
すべての作業は丁寧に作成されたハンドアウトに詳しくまとめられており、さらにPowerPointで作成された操作手順をモニター画面に写し出しての講習であったため、初心者にも大変わかりやすいワークショップであったと思われる。このワークショップを機会にコーパスに関心を持ち、英語教育に利用しようとするLETの会員が増えたのではないかと思う。初心者には大変有意義なコーパスワークショップであった。古田先生には第2弾を期待したいものだ。(岡田和子 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ 2
“Introduction to“Hot PotatoesTM”, a Web-based Software for Creating Language Exercises”
Kevin Miller (四国大学)
The“Hot Potatoes”presentation was a short introduction to an easily available shareware that can help CALL teachers author their own interactive language activities.“Hot PotatoesTM”is a product of Half-baked Software, and was developed by Stewart Arneil and Martin Holmes of the University of Victoria in British Columbia, Canada. The software is available by download from the Internet and permits language educators to create six kinds of interactive exercises: multiple-choice, short answer, jumbled sentences, crossword puzzle, matching, and gap-fill (cloze). After the teacher creates the exercises, the students access them from their classroom's server computer, display them on their net browser, and work on the exercises independently. The exercises can also be linked to websites for access by any computer. The advantage of using“Hot PotatoesTM”compared to commercially produced CALL learning materials is that the teacher can custom-make exercises that activate the language the teacher wishes to use. With a little practice, teachers can quickly make original browser-based exercises, including drag and drop versions, that have the look and feel of commercially produced computer media software.
The Hot Potatoes presentation included:
1)A demonstration of several types of activities created with“Hot Potatoes Version 5”
2)Time for participants to try all six types of Hot Potatoes activities themselves
3)A demonstration on how to create original matching activities, English-English, Japanese-English, and Pictures-English, using“Hot Potatoes Version 5”
4)A handout of the“Hot Potatoes”website: http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
Hot Potatoes may be a useful authoring tool for some, but perhaps not all, CALL teachers. Advantages to using the software are that it's easy to download from the Internet, and it's easy to understand the procedure for making activities. It's also a“free”shareware, if the users agree to post their Hot Potatoes activities on websites for access by the general public. There are a few negatives, however. One of the most serious problems is the lack of a means to monitor a student's output. There is currently no function that records how much of an activity a student has completed, nor is there any way to record grades. The software seems to be designed for free-access sites where students use the activities at their own pace, for their own study purposes. A second, minor inconvenience is the necessity to use the Unicode function when inputting Japanese. Doing so makes the Japanese characters unreadable at the authoring stage, and they only become visible after the activities have been saved as html files. This is especially inconvenient if the author has made a kanji input mistake, as one has to go back to the original document, edit, and save it again as html. Finally, completed activities have a rather simple, homogenous look, that is not very visually attractive, compared to currently available animated websites. Users can change the colors of the pages, but the overall look remains rather simple by prevailing website standards. It should also be noted that the drag-and-drop functions will not work on some of the older versions of Netscape Navigator. Still, Hot Potatoes can be a useful tool for those who wish to author their own browser-based interactive activities, but lack the time or desire to do their own programming.(Kevin Miller 四国大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第1室
「自営のWWWサイトを活用した英語授業運営」
Michael Shawback(立命館大学)、荒瀬美佐子(立命館大学)
立命館大学理工学部には英語の必修科目が10科目設けられ、全て統一教材、統一シラバス、統一評価法で運営されている。しかも10科目中8科目が教員による科学技術英語の自主開発教材である。それにより科目間の連携が強く保たれ、理工学部の学生に合ったオーダーメードの教材となっている。
対象学生は1学年1500人で合計3000人で、それぞれの科目が習熟度別に3レベルに分けられており、専任・常勤・非常勤の総勢約50名が「自営の英語サイト:English Expeditions [http://www. ee.ritsumei.ac.jp/]」により足並みを揃えて授業を進行している。
このサイトには次のメニューが用意されている。
<COURSES>3レベルのコースがあり、それぞれのコース内の開講科目について受講生は概要、評価基準、授業日程、履修上の注意が随時参照できる。教員は、各回の授業での学生の作業の成績をOn-line Grading Systemで管理でき、それらを集積して学期末の評価とすることができる。
<GRADES>教員は自動座席作成・成績記入システムを用いて自由に座席表を作成でき、出席回数も管理できる。成績管理では、クラス統計棒グラフで、現時点での各学生の100点満点換算(%)の成績表示ができる。また、教員は、ある担当科目の全クラスの平均(教員のみ閲覧)と自分のクラスとを比較することで授業の自己評価ができ、教員間の成績評価についての打合せの必要がない。これに対して、学生は自分の成績とクラスの平均点を開講期間中随時閲覧でき、例えば50点なら「もう少しがんばろう!」とのメッセージが出る。
<EMAIL GUIDE>担当者がリレー方式でe-mailのガイドラインをもとにライティングを指導しており、合計24回学生に提出させる。提出課題は担当者によって評価され、集中管理システムによるクラスの成績一覧表が作成される。さらにfeedback reportでcommon errors(8から10件)が受講生に直接メールで送信され、同時に英語科へも誤答データとして送信・蓄積される。
<RESOURCES>Communication Linksでは、テキスト関連サイトについて担当者のサイトリヴュー入の紹介がされ、Science Sitesでは、学生による自分の専攻の関連サイトの紹介がされている。<DISCUSSIONS>理工学部の中だけで英語によるフォーラムに参加することができ、その方法はCALLクラスで指導されている。(吉田信介 摂南大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第1室
「ネットワークを利用した自習用英語教材の開発:中級編」
片山真理(関西国際大学)、野澤 健(関西国際大学)、佐々木緑(関西国際大学)、有本 純(関西国際大学)
本研究は、既に発表された「初級編」に続くネットワーク自習用教材開発の研究である。「初級編」が辞書の使い方、基本語彙、文法基礎の3つのセクションから構成されていたのに対し、「中級編」は リスニング、リーデイング、文法、ライテイングの4つのセクションから成り立つ。両者ともに、新入生全員がノートパソコンを購入、情報処理授業必修という同学の環境下で、学生が学内外から自由な時間にアクセスできることを目指している。 リスニング編は基礎力の向上を目的とし、導入、解説・練習問題、補足問題の3つから構成される。まず、日本語と英語の音声上の相違を認識させるための外来語と英語の比較から始まり、次いで、音の連結、脱落、同化等の主要な音声変化に焦点を絞って、具体例(クリックすれば音声が聞こえる)を用いた平易な解説の後、練習問題へと進む。最後に、聞き取りから意味理解へ繋げるための補足問題が提示される。
リーデイング編は、長い文章の読解を苦手とする学生対象の、オンライン上でのパラグラフリーデイングである。文章の提示とその解説、2種の練習問題から成る。Exercise I は Topic Sentenceから段落の趣旨を予測しその文を Topic Sentence とする段落を探す問題で、Exercise II は、内要理解チェック問題である。 文法編は、中級学習者の英作文に見られる文法の誤りを中心に扱い、既習の文法知識を実際の言語使用に繋げることを目的とする。メニュー選択画面上の13のレッスンから学習する画面を選び、導入問題 → 解答・解説 → 確認問題(QUIZ → ヒント → 解答)へと進む。答えを解答欄にタイプし終わると直接、解答画面へ進むことも、またヒントを参照した後、答えをタイプし、解答画面へ進むこともできる。解答画面から、もう一度QUIZ画面へ戻ることもできるし、次の問題へ進むこともできる。
ライテイング編は、高等学校学習指導要領に示された言語機能の中から8つを選び、和文英訳でない、場面に適した英語表現能力の養成を目指す。メニュー画面から学習したい表現を選び、その機能項目画面に入ると、写真入りの「語彙と表現の画面」が提示される。この基本学習が終わると、与えられた状況に適した英語表現の練習問題を行う。解答は、文法編と同じく、英文をキーボードから入力して行う。ヒント、解答・解説画面についても文法編の場合と同じである。
本研究はパソコンのセルフスタデイ機能を活用した非常に意欲的な試みである。難しい/重要な事柄を、学生のニーズに合致するようネットワーク上で親しみやすく/学習しやすく噛み砕き、以て学習意欲を高め、総合的な英語力の補強を実現したいという熱意と苦心の程がうかがわれる。近年、大学生全般の学力低下が指摘され、何らかの適切な対応の必要性が強調されている中で、このような自主教材の開発は注目に値する。今後、この「中級編」が学生たちにどのように活用されるか、アクセス状況や活用の成果等、実践上の中間報告に接する機会が与えられれば、本発表の視聴者のみならず多くの語学教育関係者は貴重な指針を与えられることになる。(弓庭喜和子 大阪外国語大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第2室
「Terminologyから入る動機付け英語授業の実践報告」
青木幹生(関西国際大学非常勤)
英語に対する苦手意識を持ち、学習動機の低い大学生を対象とした総合英語授業の実践が報告された。青木先生は、彼らに必要なこと(つまり授業の目的)が、「自信を回復すること」と「英語を学習し直すきっかけを与えること」と考えられ、この2つを確実に授業で提供するために工夫された点を紹介された。
まずは、使用する教材。英語能力の低い学生ではあるが、中学生用の文法教材などを使用するのではなく、天気予報・求人報告など英字新聞よりの切り抜きや、企業の決算報告、航空会社の機内放送などを教材とされている。学生の英語能力のみではなく、知的レベルに合わせた教材選びがなされている。つまり、実社会で使用されている現実的なテーマを扱うことにより、学生の身近に英語が存在することを実感させた上で、文法などの基礎的な情報を補足的に解説するのである。
次に授業の進め方。1時間に1テーマを学習し終えるのではなく、1時間に複数のテーマを導入し、各テーマは数回の授業にかけて継続して学習する。言い換えると、授業内では約15分経過すると次の学習テーマへと移行する。子どもでなくとも、苦手なものには集中力が持続しにくい学生への配慮である。また、新しく学習する内容は、学生が消化できるまで反復して練習される。
そして最後に学期末テスト。平均点が(100点満点中)98点と、難易度の比較的低いテストであるが、既習事項をきちんと復習すれば得点できる(=やればできる)ようにと、意図的に作成されたとのこと。これも、授業目的の1つである「学生の自信を回復すること」の実現に大いに貢献していることになる。授業の目的が達成されていることは、「授業で取り扱うテーマを増やしてほしい」など、学生側から意欲的に授業への要望が示されるようになったとの報告からも明らかなようである。(池田真生子 摂南大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告 第2室
「Low proficiency学習者のための効果的な英語読解指導法を考える」
福地美奈子(金光大阪高等学校)
英語能力の低い高校生を対象に読解を指導する場合には、内容理解を中心とするよりも、従来から行われている文法訳読を中心とした指導の方が効果的ではないかという福地先生の仮説のもとに、この2つの読解指導法の効果が検証された。被験者は高校3年生2クラス(計61人)。4月の新学期から12月まで、週3回の授業において実施された。内容理解を中心とした指導では、タイトルやイラスト、トピックセンテンス、キーワードなどをもとに本文の内容を理解するように指導された。文法訳読を中心とした指導では、SVOCなどの文型理解と逐語訳が行われた。この2つの指導方法の効果を検討するにあたり、指導の前後に語彙力(Nation, 1990)と内容理解力(自主作成)を測定するためのテストが実施された。t検定の結果、内容理解を中心とした指導を受けたグループは内容理解テストのみにおいて得点が有意に上昇する傾向が見られた。一方、文法訳読を中心とした指導を受けたグループは、語彙力テストのみにおいて同様の傾向が見られた。
このような結果より、文法訳読中心の指導は、内容理解力の即時向上には結びつかないまでも、英文読解の基礎となる語彙力の向上には、より適している可能性が示唆された。語彙力の向上は、とりわけ今回の対象者であった英語能力の低い学習者にとっては、読解力を強化するために重要な点の1つであるだけに、興味深い結果であった。発表の締めくくりには、指導効果の測定方法や指導内容など、今後も改善・検討の必要な事項も報告された。(池田真生子 摂南大学非常勤)