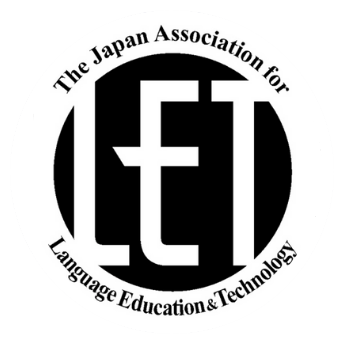大会名
98年度春季研究大会
大会(春・秋・全国)
春季大会
日付
1998年5月30日
会場
甲南大学
概要
5月30日に行われた支部春季大会は80名の参加者を集め成功裏に終わりました。会場校として受けいれに協力いただきました甲南大学の皆さんに心より感謝いたします。内容に関しましては、以下の報告をご覧ください。
詳細
授業研究(10:30より)
『甲南大学上級英語の試み:Content-based Process Writing for Oral Presentation』
中村耕二(甲南大学)
本授業研究は、プロセスライティングとスピーチコミュニケーションの統合というタイトルで、甲南大学国際言語文化センターで提供されている上級英語のクラスを実践報告という形で、授業の様子をビデオを使用しながら、質疑応答を含め全て英語でなされた。紹介された授業は、センテンス・レベルから脱却した自己表現を英作文とオーラルの両面を統合したものであった。なお、同センターの上級クラスは通年4単位で提供されており、1クラスの履修者の上限は25名である。
中村氏が報告した授業の流れは、要約すると以下のようになる。(1)パラグラフの書き方及びスピーチの仕方等の講義を行う。(2)トピック(グローバルな社会問題)に関わる書きものを受講生に読ませる。(3)トピックに関するビデオを教室で見せる。(4)受講生は自らが書くそして話す話題を絞り込むために、他の受講生にインタビューをしたり、あるいは一緒にブレーン・ストーミングを行う。(5)受講生はインターネットあるいは図書館等でさらに情報を収集する。(6)英語でペーパー(1~3枚)を書く。(7)添削を受ける(教師のコメントは全て英語)。(8)書き直す。(9)ここで述べた7と8を繰り返す。(10)受講生はスピーチを行う。なお、発表者は原稿をそのまま読むのではなく、他の受講背にに語りかけることが求められていた。また、黒板を使用しながらの発表も容認されていた。(11)最終版の作文を提出する。
スピーチの際には、発表者が一方的に話すのではなく、他の受講生達も積極的に英語で意見が出し、発表者と双方向のやり取りを行っている様子を授業中に録画されたビデオから伺うことができた。また、本研究大会当日に中村氏が配布した資料の6ページにも述べられているように、中村氏は自分が全面に出るのではなく、受講生にイニシアティブをできるだけ取らせ、受講生が教室においても自己表現を行う環境を提供していた。
中村氏の報告で感銘を受けた参加者は多かったと思う。筆者もまた英語教育の原点について改めて考えさせられた。中村氏の授業の目標ははっきりとしていた。また、シラバスも大変よく練られていた。授業の準備あるいは添削等のことを思うと、中村氏の負担は計り知れないものがある。中村氏は誠心誠意、全力で受講生にぶつかっており、その教育熱心さには深い感銘を受けた。(中迫俊逸:中央大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-1(13:55より):『日本人の英語学習における言語学習ストラテジーの使用と読解能力の関係についての一研究』(池田真生子:摂南大学)
この研究は日本人学生22名の英国への留学生を対象に、滞在が一ヶ月を経過した時点で、英語学習におけるこの学生の言語学習ストラテジーが新しい環境では、どのように変化したかを報告者自身が調査したもの。
英文読解力はReadaing Test (FCE of Cambridge Exam) 40問で計り、先行研究にもとづき報告者が独自に作成したアンケート調査と個人面接により得た結果を分析、考察している。
報告では、留学先で英語を学習する学生達は、単語を「分類して暗記する」「繰り返して覚える」の項目で上位群優位の傾向が見られるほか、英文を「積極的に読む」態度、「英英辞典の使用」が増えるという、新しい環境に刺激を受けた結果が観察される一方で、「予習をする」ことが減少しているが、これは授業形態が異なるため予習の方法が無いからだとしている。
対象となった学生が少ないこと、また調査の時期など、今後の研究の課題になろう。(小畠雅敏:天理大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-2(14:30より):The Effect of Modified Speech Input (石田久実子:立命館大学、杉下恵子:Georgetown Univ.)
第2外国語として英語を学ぶ受講生は、英語を理解しようとするとき、どういうことに留意するのか。どんなことがためになるのか。報告者の関心はこういうことである。学生が英語を理解するとき、普通のスピード(一分間に189語程度)で読むより、少し手を加えた(一分間に129語程度)方が聴き取りやすい、としてPicture identification task などにより実験した。結果は有意差がないものの、むしろ逆の傾向が見られたという。
先行のHae-Young Kim(1995) の研究を立命館大学の学生42名に試みたもので、同じような結果を得たが、実験計画などに改善の余地があるという。
外国語を担当するものならば一度は考慮するスピードの問題だけに、さらなる研究が望まれる。(小畠雅敏:天理大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-1(13:55より):『新しい学習環境としてのサイバーラーニングは今なぜ必要なのか』(倉本充子:関西外国語大学)
「サイバースペースでの学習環境は英語学習に必要とされる良好な動機付けとなり、能力向上にプラス要因となる」という発表者の仮説を、実際にe-mail、インターネットを利用して教育を進めている学校群ネットワーク事例を例にとって検証し、教育分野での電子メデイア利用が社会的にどのような意味を持つかを、1970~80年代からサンタフェ研究所を中心に盛んになってきている複雑系科学、アフォーダンスの視点から観察することを狙いとした発表である。更に、インターネットを利用した英語教育の有為性を示す根拠として、高校生を対象とした「インターネット利用なし」の6カ月の統制期間とその後に続く「インターネット利用あり」の6カ月の実験期間の学習効果の差を測定し統計分析した英検各級の過去問題テスト結果が提示された。
結論として、情報操作のインタラクテイブ性(誰もが随意に情報の発信者となれる可能性)を正しく評価した、時間的空間的制約を越えた電子メデイア利用学習、すなわち新しい学習環境としてのサイバ^ラーニングが、教師と生徒・学生等の相互協力を伴う創造的な外国語学習に、今必要であるという発表要旨であった。
仮説の説明や内外の事例紹介等いずれも時間を要する内容であったため、統計分析結果の説明に十分な時間を割くことが出来なかったことが惜しまれる。非常に興味深い今日的な研究課題であるので、今後の発展的研究が大いに期待される。(弓庭喜和子:関西外国語大学短期大学部)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-2(14:30より):『理工系学生のための教材とその効果』(新田香織:近畿大学)
生物理工学部専門科目の教員が学生に求める英語力と英語教員が必要と考える英語力の接点、及び学生の現実の英語力を考慮して行われた、限られた授業時間内で効果をあげる英語教材開発とその授業効果に関する研究発表である。 語彙不足や英文構造の理解不足等理工系学生の問題点をふまえ、科学英語と一般教養英語との橋渡しになると同時に、学生が新鮮な気持ちで取り組める総合教材(ロボット、人工心臓、臓器移植、喫煙等のトピック)を開発し、一定の授業手順により1年間の授業を行った結果、97年4月のプリテストの成績をもとに分けた上位群・中位群・下位群について、7月の前期テスト、12月のポストテスト、翌年1月の後期テストのそれぞれの結果を各群毎に比較分析したところ、上位群の「読解」を除くすべての点でポストテストの結果がプリテストの結果を上回り、「リスニング」と「読解」では下位群の、「文法」では中位群の伸びが著しく、全体として授業効果があがっていること、また今後の課題として、基礎的な英語の指導に重点を置いたため、上位群の学習意欲の低下が認められるので、能力に応じて読み進めるコンピュータソフトの開発等も必要であることが報告された。
現実に、学生や社会のニーズが多様化しており、それに対応できる高等英語教育の拡充が望まれる時代であるので、これは示唆に富む研究である。今後、English for Specific Purposesの研究としてさらに推進されることを期待している。(弓庭喜和子:関西外国語大学短期大学部)
--------------------------------------------------------------------------------
講演(15:15より)『外国語教育におけるWeb-Server の導入と活用:Hyperwave Information server の魅力』(東淳一:流通科学大学、Hermann Mauerer:グラーツ工科大学)
最近では、コンピュータを利用した教育システムは、スタンドアロン型からネットワーク型へと移行しつつあるが、今回の講演は、そのような流れを反映したもので、外国語教育の分野でのWebサーバの利用をテーマとし、その具体的な方法についての解説がなされた。
講演に先立ち、司会の北村裕先生(関西大学)から、発表者の東先生と指定討論者の安田雅美先生(関西学院大学)の紹介がなされた。東先生は、インターネットを授業で利用する場合においても、これからは、他人が作成したWWW(World Wide Web: 通称Web)上のリソースを利用するだけでなく、教師も自らWeb上で教材を開発して利用していくべきであるとの意見を述べられ、そのための具体的なWebサーバの運用方法などを解説された。先生の場合は、Windows 95 + Microsoft Front Page 98 + Personal Web Serverの3つのソフトウェアを利用してWebサーバを運用されているとのことであり、先生が作成されたWeb教材の紹介なども行われた。先生の場合は、商学部の学生が対象であるということもあり、授業において、インターネットを利用して擬似的に株式の運用をさせる試みなどもさせておられるとのことであった。
次に、Hyperwave Information Serverの紹介が行われた。このサーバソフトは、グラーツ工科大学のHermann Maurer教授らのチームが開発した「第2世代のWebサーバ」とされるもので、その特徴的な機能としては、Webページ上の個々のオブジェクトに対してアクセス権の設定が行えることや、Dynamicなリンク機能を持っていること、ユーザー毎にカスタマイズしたWebページを提示できる機能など、従来のWebサーバとは異なったものを持っているとされる。これらの機能について東先生からデモンストレーションを交えて解説がなされ、共同発表者であるHermann Maurer先生からのビデオメッセージも紹介された。
指定討論者の安田先生からは、システム開発に関しては、その教育面・学習者モデル・学習モデル等を考慮して開発すべきであるとの意見が述べられ、また、教師がシステム開発を行うべきかどうかについても、問題提起がなされた。
今回の講演は内容的に専門性の高いものであったが、最先端の技術に関するものとあって、参加者の熱心に聞き入る姿が見られた。(杉森 直樹:大阪電気通信大学)
『甲南大学上級英語の試み:Content-based Process Writing for Oral Presentation』
中村耕二(甲南大学)
本授業研究は、プロセスライティングとスピーチコミュニケーションの統合というタイトルで、甲南大学国際言語文化センターで提供されている上級英語のクラスを実践報告という形で、授業の様子をビデオを使用しながら、質疑応答を含め全て英語でなされた。紹介された授業は、センテンス・レベルから脱却した自己表現を英作文とオーラルの両面を統合したものであった。なお、同センターの上級クラスは通年4単位で提供されており、1クラスの履修者の上限は25名である。
中村氏が報告した授業の流れは、要約すると以下のようになる。(1)パラグラフの書き方及びスピーチの仕方等の講義を行う。(2)トピック(グローバルな社会問題)に関わる書きものを受講生に読ませる。(3)トピックに関するビデオを教室で見せる。(4)受講生は自らが書くそして話す話題を絞り込むために、他の受講生にインタビューをしたり、あるいは一緒にブレーン・ストーミングを行う。(5)受講生はインターネットあるいは図書館等でさらに情報を収集する。(6)英語でペーパー(1~3枚)を書く。(7)添削を受ける(教師のコメントは全て英語)。(8)書き直す。(9)ここで述べた7と8を繰り返す。(10)受講生はスピーチを行う。なお、発表者は原稿をそのまま読むのではなく、他の受講背にに語りかけることが求められていた。また、黒板を使用しながらの発表も容認されていた。(11)最終版の作文を提出する。
スピーチの際には、発表者が一方的に話すのではなく、他の受講生達も積極的に英語で意見が出し、発表者と双方向のやり取りを行っている様子を授業中に録画されたビデオから伺うことができた。また、本研究大会当日に中村氏が配布した資料の6ページにも述べられているように、中村氏は自分が全面に出るのではなく、受講生にイニシアティブをできるだけ取らせ、受講生が教室においても自己表現を行う環境を提供していた。
中村氏の報告で感銘を受けた参加者は多かったと思う。筆者もまた英語教育の原点について改めて考えさせられた。中村氏の授業の目標ははっきりとしていた。また、シラバスも大変よく練られていた。授業の準備あるいは添削等のことを思うと、中村氏の負担は計り知れないものがある。中村氏は誠心誠意、全力で受講生にぶつかっており、その教育熱心さには深い感銘を受けた。(中迫俊逸:中央大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-1(13:55より):『日本人の英語学習における言語学習ストラテジーの使用と読解能力の関係についての一研究』(池田真生子:摂南大学)
この研究は日本人学生22名の英国への留学生を対象に、滞在が一ヶ月を経過した時点で、英語学習におけるこの学生の言語学習ストラテジーが新しい環境では、どのように変化したかを報告者自身が調査したもの。
英文読解力はReadaing Test (FCE of Cambridge Exam) 40問で計り、先行研究にもとづき報告者が独自に作成したアンケート調査と個人面接により得た結果を分析、考察している。
報告では、留学先で英語を学習する学生達は、単語を「分類して暗記する」「繰り返して覚える」の項目で上位群優位の傾向が見られるほか、英文を「積極的に読む」態度、「英英辞典の使用」が増えるという、新しい環境に刺激を受けた結果が観察される一方で、「予習をする」ことが減少しているが、これは授業形態が異なるため予習の方法が無いからだとしている。
対象となった学生が少ないこと、また調査の時期など、今後の研究の課題になろう。(小畠雅敏:天理大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-2(14:30より):The Effect of Modified Speech Input (石田久実子:立命館大学、杉下恵子:Georgetown Univ.)
第2外国語として英語を学ぶ受講生は、英語を理解しようとするとき、どういうことに留意するのか。どんなことがためになるのか。報告者の関心はこういうことである。学生が英語を理解するとき、普通のスピード(一分間に189語程度)で読むより、少し手を加えた(一分間に129語程度)方が聴き取りやすい、としてPicture identification task などにより実験した。結果は有意差がないものの、むしろ逆の傾向が見られたという。
先行のHae-Young Kim(1995) の研究を立命館大学の学生42名に試みたもので、同じような結果を得たが、実験計画などに改善の余地があるという。
外国語を担当するものならば一度は考慮するスピードの問題だけに、さらなる研究が望まれる。(小畠雅敏:天理大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-1(13:55より):『新しい学習環境としてのサイバーラーニングは今なぜ必要なのか』(倉本充子:関西外国語大学)
「サイバースペースでの学習環境は英語学習に必要とされる良好な動機付けとなり、能力向上にプラス要因となる」という発表者の仮説を、実際にe-mail、インターネットを利用して教育を進めている学校群ネットワーク事例を例にとって検証し、教育分野での電子メデイア利用が社会的にどのような意味を持つかを、1970~80年代からサンタフェ研究所を中心に盛んになってきている複雑系科学、アフォーダンスの視点から観察することを狙いとした発表である。更に、インターネットを利用した英語教育の有為性を示す根拠として、高校生を対象とした「インターネット利用なし」の6カ月の統制期間とその後に続く「インターネット利用あり」の6カ月の実験期間の学習効果の差を測定し統計分析した英検各級の過去問題テスト結果が提示された。
結論として、情報操作のインタラクテイブ性(誰もが随意に情報の発信者となれる可能性)を正しく評価した、時間的空間的制約を越えた電子メデイア利用学習、すなわち新しい学習環境としてのサイバ^ラーニングが、教師と生徒・学生等の相互協力を伴う創造的な外国語学習に、今必要であるという発表要旨であった。
仮説の説明や内外の事例紹介等いずれも時間を要する内容であったため、統計分析結果の説明に十分な時間を割くことが出来なかったことが惜しまれる。非常に興味深い今日的な研究課題であるので、今後の発展的研究が大いに期待される。(弓庭喜和子:関西外国語大学短期大学部)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-2(14:30より):『理工系学生のための教材とその効果』(新田香織:近畿大学)
生物理工学部専門科目の教員が学生に求める英語力と英語教員が必要と考える英語力の接点、及び学生の現実の英語力を考慮して行われた、限られた授業時間内で効果をあげる英語教材開発とその授業効果に関する研究発表である。 語彙不足や英文構造の理解不足等理工系学生の問題点をふまえ、科学英語と一般教養英語との橋渡しになると同時に、学生が新鮮な気持ちで取り組める総合教材(ロボット、人工心臓、臓器移植、喫煙等のトピック)を開発し、一定の授業手順により1年間の授業を行った結果、97年4月のプリテストの成績をもとに分けた上位群・中位群・下位群について、7月の前期テスト、12月のポストテスト、翌年1月の後期テストのそれぞれの結果を各群毎に比較分析したところ、上位群の「読解」を除くすべての点でポストテストの結果がプリテストの結果を上回り、「リスニング」と「読解」では下位群の、「文法」では中位群の伸びが著しく、全体として授業効果があがっていること、また今後の課題として、基礎的な英語の指導に重点を置いたため、上位群の学習意欲の低下が認められるので、能力に応じて読み進めるコンピュータソフトの開発等も必要であることが報告された。
現実に、学生や社会のニーズが多様化しており、それに対応できる高等英語教育の拡充が望まれる時代であるので、これは示唆に富む研究である。今後、English for Specific Purposesの研究としてさらに推進されることを期待している。(弓庭喜和子:関西外国語大学短期大学部)
--------------------------------------------------------------------------------
講演(15:15より)『外国語教育におけるWeb-Server の導入と活用:Hyperwave Information server の魅力』(東淳一:流通科学大学、Hermann Mauerer:グラーツ工科大学)
最近では、コンピュータを利用した教育システムは、スタンドアロン型からネットワーク型へと移行しつつあるが、今回の講演は、そのような流れを反映したもので、外国語教育の分野でのWebサーバの利用をテーマとし、その具体的な方法についての解説がなされた。
講演に先立ち、司会の北村裕先生(関西大学)から、発表者の東先生と指定討論者の安田雅美先生(関西学院大学)の紹介がなされた。東先生は、インターネットを授業で利用する場合においても、これからは、他人が作成したWWW(World Wide Web: 通称Web)上のリソースを利用するだけでなく、教師も自らWeb上で教材を開発して利用していくべきであるとの意見を述べられ、そのための具体的なWebサーバの運用方法などを解説された。先生の場合は、Windows 95 + Microsoft Front Page 98 + Personal Web Serverの3つのソフトウェアを利用してWebサーバを運用されているとのことであり、先生が作成されたWeb教材の紹介なども行われた。先生の場合は、商学部の学生が対象であるということもあり、授業において、インターネットを利用して擬似的に株式の運用をさせる試みなどもさせておられるとのことであった。
次に、Hyperwave Information Serverの紹介が行われた。このサーバソフトは、グラーツ工科大学のHermann Maurer教授らのチームが開発した「第2世代のWebサーバ」とされるもので、その特徴的な機能としては、Webページ上の個々のオブジェクトに対してアクセス権の設定が行えることや、Dynamicなリンク機能を持っていること、ユーザー毎にカスタマイズしたWebページを提示できる機能など、従来のWebサーバとは異なったものを持っているとされる。これらの機能について東先生からデモンストレーションを交えて解説がなされ、共同発表者であるHermann Maurer先生からのビデオメッセージも紹介された。
指定討論者の安田先生からは、システム開発に関しては、その教育面・学習者モデル・学習モデル等を考慮して開発すべきであるとの意見が述べられ、また、教師がシステム開発を行うべきかどうかについても、問題提起がなされた。
今回の講演は内容的に専門性の高いものであったが、最先端の技術に関するものとあって、参加者の熱心に聞き入る姿が見られた。(杉森 直樹:大阪電気通信大学)