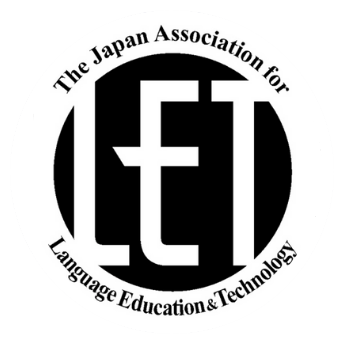大会名
01年度春季研究大会
大会(春・秋・全国)
春季大会
日付
2001年4月28日~29日
会場
京都教育大学
概要
01年度春季大会は、2001年4月28日(土) 、4月29日(日)に京都教育大学でおこなわれました。連休中のにもかかわらず、のべ180余名にものぼる多数のご参加を頂き、誠にありがとうございました。講演には、慶応義塾大学名誉教授の鈴木孝夫先生をお迎えしたほか、授業研究(2件)、ワークショップ(4件)、研究発表(6件)、シンポジアム(1件)、賛助会員展示(5件)など、盛りだくさんの内容でした。なお、28日には支部総会も開催され、予算の報告、決算の報告、活動計画、新研究部会の承認などがなされました。
詳細
講演
「21世紀の外国語教育を考える」
鈴木孝夫先生(慶応義塾大学名誉教授)
鈴木先生のご著者は、近著を含めて5-6冊に目を通していたが、やはりご本人の講演は迫力が違っていた。先生は、「必要もないのに英語を学べるはずがない」、「日本が大国になったこと自体が間違いだ」と刺激的な言葉を次々と繰り出される。しかし、その後には、必ず説得力のある解説を加えられる。言語学、歴史学、社会学などに造詣の深い鈴木先生ならではの「うーん」と唸らせる解説である。
まず、氏は、訳読型の外国語教育が、発展途上の日本にはきわめて効率的で、ふさわしものであったと指摘される。この外国語教育法のおかげで、日本は国の独立を保ちつつ、先進国の仲間入りをしたのだ。しかし、80年代、日本が先進国となった時に、この方法をオーバーホールし、情報発信型に切り替えるべきであった。それをせず、十年(いや百年)一日のごとく、情報吸収型の教育法の延命を図ったために、今、その綻びが頂点に達しているという。
それでは、どのように外国語教育を変えるべきであろうか。氏は、外国語を使って、日本の事情を世界へきちんと説明できるような能力の育成を行うべきであると指摘する。さらに、日本は、米国や欧州、イスラム諸国などのように、世界を説き伏せるような主義主張を持たないが、江戸時代に200年以上にわたり平和な国家を維持した実績を持つ国であり、このノウハウを発信することで、世界を導いていくことができると主張される。加えて、国家戦略として、(時には脅しや、取引もしながら)日本語の国際語化を図るよう、働き掛けていく必要があることも強調された。
一口も水を飲まず、座ることもなく、予定の時間をはるかに超えて熱弁をふるわれる先生の姿を見ていると、なにか仕事をし残した、使命感にかられた鬼神のようなものを見る思いがした。先生は、講演後、求めに応じて「出る杭は打たれる。しかし、出すぎた杭は打たれない。」と書かれたという(いわゆるジップの法則)。日本が「出すぎた杭」になるまでは、鬼神の休む暇はないようである。(竹内 理 関西大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業実践報告(1)
“Welcome to My Classroom”
Andrew Obermeier(京都教育大学)
Andrew Obermeier先生の「Communicative English Ⅲ」の授業風景をビデオで見せていただいた。履修登録した学生は英語専攻の3回生6名で、これまでにオーラル・コミュニケーション関係の科目を2科目単位習得している。使用テクストはNew Headway English Course, Upper-intermediate.(Oxford University Press)で、文法学習と四技能をうまく絡ませながら、全体的なコミュニケーション能力を高めることを授業の目標としている。授業の構成は、文脈を考慮に入れた文法学習のドリル・あるテーマに沿った読みと内容理解の言語活動・そのテーマに即して自分の意見や考えを発表し合う言語活動・他の授業科目について短い要約を書き、お互いに感想を述べ合う言語活動と盛り沢山である。
私が特に感心させられた点は、文法の扱いと先生の懇切丁寧なフィードバックの仕方である。先生は“Communicative ability develops alongside, or even behind grammatical acquisition.”と考えておられ、コミュニケーション重視の風潮下にあっても決して文法の学習を軽んじておられないことである。例えば、Discussing Grammarという言語活動では、以下のような2つの文の意味の違いを動詞の形態に注意させ、英語で話し合わせている(a. You're very kind. Thank you. b. You're being very kind. What do you want? / a. You're annoying me with all your questions. b. I can see you're annoyed. What's the matter?)。先生はある文法項目の形態が選択される理由を多くの例文と豊かな文脈を示しながら、説明しておられる。学生の方にも、使用される文脈やニュアンスの違いをなんとかして英語で説明しようと努力する姿が窺えた。
次にフィードバックの仕方であるが、授業中の文法訂正や発話を誘発するフィードバックはもとより、毎時間の宿題をテープに録音させ、学生が提出したテープに懇切丁寧なフィードバックを心掛けておられる。学生は読みの課題をこなし、内容理解の質問に口答しながら録音する、また文法のドリルに口答したものを録音する。先生は提出された録音テープの文法・発音・抑揚などを入念にチェックされ、コメントを録音して返却されているのである。授業全体として、語学学習の基礎・基本を丁寧におさえながら、学生の口頭活動を保証し、フィードバックの行き届いた、文字通りintensiveな授業であった。(西本有逸 京都教育大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業実践報告(2)
「四技能を伸ばすための授業」
大窪 美祈(京都市立紫野高校)
今春堀川高校から紫野高校に転勤された大窪先生による英語Ⅰの授業(Polestar English Course I Lesson 10 "Without Valleys You Can't Have Mountains")をビデオで見た。前任校(堀川高校人間探求科:男子14名、女子27名)で12月に収録されたものである。前時にリスニングによる大意把握と重要語句の確認が終了していた。 英語係りの生徒が“Stand up.”と号令をかけて授業が始まった。ウォームアップとしてシリーズで行っている「今日の一言」が板書され音読練習を行った。また、月ごとに練習し期間中に歌うと得点となる英語の歌が流された。
次に、ペア同士が新出語を簡単な英語で説明し、該当する単語を当てるMagical Quizを実施した。その後、本文のCD(意味単位でポーズを置き、後で出てくるSight Translationを踏まえたもの)をペースメーカーとした黙読を行った。英検2級2次試験風の2枚のイラストを用いたカードを使用し、ペアがQ&Aを行い、本文の要点を再確認した。ここで宿題となっていたSight Translationの形式の日本語による穴埋めワークシートで細部を確認した。基本的には難解な個所についての生徒からの質問に答える方式をとっていた。
次に、本時でのポイントのunlessを使用した単文を板書で取り上げた。意味確認と音読練習後、決められた時間で音読しながら筆写する多量高速音読筆写を行った。次に、Sight Translationを基盤とし、日本語交じりや穴埋めにしたワークシートを見て、生徒たちは本文を音読再生した。最後に、Faster Writingとして3分を与えた。与えられた題は、本文に則し"Who are you?"であった。1分で構想を練った後で、Fluencyを目標に2分で意見を英語で書いた。その後、生徒たちはその英文を読み上げるのではなく、その内容をもとにペアでスピーキング活動を楽しんだ。
読んで訳すだけの授業でなく、生徒たちは全ての高度な活動を、楽しく生き生きとこなしていた。質疑応答では、フロアーから「Sight Translationの形式を生徒たちが徐々に自立できるように工夫するとよい」とのアドバイスや音読の際の英語らしいリズムを強化する方法が紹介された。四技能のバランスの取れた活動がうまく絡み合い授業者の目標はよく達成されて、「本文の完全学習を音声を有効活用した多彩な活動で行っている」や「ワークシートが緻密に計画されている」など本授業を高く評価する意見が出た。(溝端保之 大阪府立泉南高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(1)
「CALLソフトウェアにおけるFeedback情報の役割-CALLとLLの違い-」
三根 浩(同志社女子大学)、吉田晴世(摂南大学)
一般に、LL(Language Laboratory)と、その発展形として捉えられているCALL(Computer Assisted Language Learning)システムの両者を、背景にある教育理論の基本的理念から比較し、教育デザインの違いを多数のビデオ映像による視覚資料を織りまぜて、詳細に説明された。また、その差異化を図るCALLソフトウェアについて開発中のデザインを紹介された。 LLは、構造主義言語学と行動主義心理学を背景とするAudio-Lingual Habit Approach(ALH)に基づき、刺激-反応(S-R)結合により言語学習が自然に成立するということを前提とし、教材を難易度順に細分し、(i+1)を連鎖させていく直線型のプログラム学習(Skinner, 1957)を推進した。しかし、1970年代に生成文法と認知心理学に基礎をおくCognitive Code Learning Approachが盛んとなり、言語獲得に際してインプットの量に対してはるかに多くの言語産出の可能性が指摘された。ところが、この手法も言語獲得装置(LAD)を活用できない大学生レベルの実践では行き詰まりを示した。1980年代からのCommunicative Approachでは、個別学習からグループ学習へ移行し、外国語によるタスクを解決させることで、より認知的な語学学習を目指すものとなった。
言語学習では、言語活動におけるKnowledge BaseとしてのMental Lexiconを獲得する認知的な学習が必要であるが、LLによる学習では認知的学習を阻害する要因がある。LLでは、基本的設計がS-R理論に基づいているため、学習の初期に外発的動機づけを行い、学習者に試行錯誤に基づく単純な学習ストラテジーを使用させ、単なる条件づけによる学習を誘発してしまう。試行錯誤とはTrial & Errorで、Errorにつながるすべての反応を制止させることで学習への動機づけを低下させてしまう結果を伴う。
認知的学習を成立させるには、反応の制止につながる試行錯誤を排除した内発的動機づけが必要である。反応の増強、認知的興味を促す適正なフィードバック情報(KR: Knowledge of Results)をリアルタイムに提供し、認知地図の形成を促し、潜在記憶の形成ストラテジーを促進させることが重要である。そのためには、①インタラクティブ ②マルチ・プロセス ③ハイパー・メディアという特徴をもつマルチメディアの活用が適している。
最後に、従来の直線型プログラム学習やドリル学習を排し、インタラクティブに情報を取り出せ、誤解答に対して即時にKR情報を与え、記憶のストラテジーを促進させる、現在開発中のマルチメディア型CALLソフトウェアを紹介された。句動詞によるコアイメージ学習を簡易な4コマ・アニメにより形成するためのシステムを提示され、上述の理論に応じた認知地図形成を促す上でのフィードバック情報の重要性を示された。(倉本充子 近畿大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(2)
「英語の音声指導」
有本 純(関西国際大学)
有本氏は実践的な観点から発音指導について話をされた。有本氏によると、発音指導が困難な理由として、クラスサイズ、時間の制約、指導項目の優先順位、モデルと目標、教師の役割の5つがあるという。学習者が1人ずつ異なった問題を抱えており、指導が原則として個別にしか対応できないという理由から理想的なクラスサイズは10名以内であり、時間的制約については1回の授業時間の中で発音指導に使える時間、またその内1人にかけられる時間が非常に限られている。その結果、現状の英語教育では発音指導は後回しか、放置される傾向にある。モデルと目標については、実際の現場は完全なイギリス英語やアメリカ英語を教えているわけではないので、日本語訛りの英語であってもよい。教師の役割として、日本語音声との違いを知り、英語音声学の知識を持ち、わかりやすく説明できる、自分で発音のモデルを示すことが出来る、発音が自学自習できないものであることから、学習者の発音を正しく判断し、指導できる存在になることだと述べられた。
また、有本氏は日本人学習者がアメリカ英語を学び、アメリカ英語の話し手になるのをモデル1とし、ニホン英語の話し手になるのをモデル2とされた。両者の比較として、モデル1では学習者は無力感と劣等感に悩み、英語運用に消極的になること等が挙げられ、モデル2では役に立つ英語は使える英語でなければならない等の意識的特徴がある。
さらに、有本氏は指導に用いる記号、発音の間違いとその原因、発音指導の留意点についても話をされた。具体的発音指導について、母音ではイメージを与えることを強調され、区別の必要な母音を重点的に指導すること、二重母音は日本語には存在しないことを認識しておくこと、子音の指導では、破裂音は語頭と語末に注意すること、摩擦音は息の強さで決まること、日本語近似音で代用できない子音は重点的に指導することについて話をされた。さらに音の連続、ポーズの入れ方、イントネーションの指導、強勢の指導など多岐にわたり詳しく述べられた。
今からできることとして、発音練習は楽しく、大きな声を出しても恥ずかしくないという雰囲気作りをすること、常に発音に注意を向けさせる努力をし、毎時間少しでも発音練習をする時間を入れることを挙げられた。教師の態度としては親しみやすく、リラックスした雰囲気、生徒との信頼関係の構築などに心がけ、暗唱やシャドウイングなど教科書の音読も利用してみる等の工夫を挙げられた。(杉本智昭 大阪電気通信大学高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(3)
「外国語としての英語の語彙学習を考える」
門田 修平(関西学院大学)
中西 義子(大阪国際女子短期大学)
横川 博一(京都外国語大学)
3人の講師の方々は、順にLET関西支部の基礎理論研究部会の部会長、副部会長、事務局長を務められている。本研究部会では、中心的な目標を「外国語としての英語における語彙獲得過程の解明」と定め、共同研究などを進めており、本ワークショップはその成果を報告し、語彙学習に対してどのような示唆が得られるかを考えようと企画された。
まず、中西講師が、大学生が入学時にどれくらいの英語の語彙サイズを持っているかを把握するための調査結果を報告した。入学直後の大学生に対し、単語の意味が分かるかどうかをYes/Noで答えさせ、さらに日本語の意味を書かせる2段階の調査を通し、大学入学時の平均的な受容語彙サイズは約2100~2600語、発表語彙サイズは約1900~2300語程度と推量した。読解における必要語彙数は3000語であるらしく、それには達していないと推定された。次に門田講師が、単語認知の2重アクセスモデルを説明した後、これまで行われたメンタルレキシコンの語彙のネットワーク構造に関する調査とメンタルレキシコンの語彙上へのアクセスに関する調査の結果を報告した。一連の実験から、“意味を知っている単語の場合は反対・対語関係など意味的ネットワークが緊密だが、意味の把握が不十分な場合は、音韻的な語彙ネットワークが活性化する”や、“正書法処理よりも音韻処理の方が時間がかかり、かつ正答率も低い”などの結果が報告された。最後に横川講師が、The evidence examined by the judge turned out to be unreliable. のような難解な文の理解に語彙情報がどのように利用されているかについて考察した。一連の実験の結果、文の理解では早い段階から語の持つ統語的・意味的情報をできるだけ利用していることが分かり、英語学習者に対しても、語彙情報を利用した直読直解を指導することが有効であると提案された。
このワークシップに参加して、英語学習者の語彙の構造に対する関心が高まり、英語学習における語彙の重要性が改めて認識されたように思う。今後、基礎理論研究部会を中心にさらに実証的な研究が積まれ、その成果をまたご報告いただけることを楽しみにしている。(石川圭一 京都女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(4)
「ビデオ教材の効果的な利用法-理論と実践」
山根 繁(甲南女子大学)
金星堂のビデオ教材ABC Newsの著者のお一人の山根繁氏のワークショップである。まずニュース英語の一般的な特徴が述べられた。文の語数は5~9から15~19語のものが多い。このような語数から単文が全体の48.6%を占め、続いて複文が26.9%を占めることは容易に受け入れられる。スピードは177~161語/分で、時制は44.3%が現在形、40.2%が過去形となる。スピード以外は学生にとって負担が大きいとも思えない。
なぜ英語ニュースは記録者櫻井が高校/大学生時代に、いつも圧倒されていたのだろうか。語彙?スピード、息の区切りのポーズが短すぎた?発音と単語が一致しない、叉は語と語の間で起こる音声変化についていけなかった?一体どれだったんだろうか?ニュースが終わった後に数語が記憶に残るだけであったのはどうしてなんだろうと山根氏の話しを聴きながら昔を振り返りはじめた。大学生の時聴いていたVoice of Americaのspecial Englishとregular Englishで同じニュースでも理解度が違った。限られた語彙でゆっくりと読まれる短い文からなるニュースは理解出来た。しかし、その前に聴くregular English Newsはただ胃が熱くなるだけだった。special Englishの後のregular Englishでのニュースはさすがに理解出来たが。
映像と理解度の問題、映像があれば理解に助けになるのは分かるが、あのVoice of Americaのregular Englishに映像があれば、special English程に理解出来たのだろうか。映像の助けを受けての理解度はL2を発展させるのに、つまり語学習得の究極的な促進剤になるのだろうか。NHK第2放送の英語ニュースや短波放送で英語を聴いていた私には、映像の力に疑問が残る。記録者自身がマルチメディアと常に言いながら、山根氏のお話を伺いながら不遜にも自分の今までのプロセスを分析しメモし続けてしまった。
ビデオ教材の一般的なお話の後に、山根氏の著書“ABC News”の紹介があった。この本についてはよく知られているし、本を一見すれば内容が分かる。そこで、この教材を今年度の授業に採用している私が工夫していることを2点最後に付け加えておきたい。
1.教材の一つのaudio tape のsummeryのoral repetition用のtapeを私は作成している。学生は何度も練習して、最後に本なしでoral repetitionをして提出している。音読がどれ程記憶に効果的かを「週間朝日」に予備校の先生が書いておられたのに感化されて、自分でもやってみて納得したので、学生への課題にした。
2.本文で習得して欲しい表現や、文型は「同時通訳ゲーム」と称して練習している。つまり私が日本語で言ったのを、学生が同時通訳していく訳である。このゲームは本文を簡単に応用して出来るものだから、faked 同時通訳となっているが、習得して欲しい表現が各ユニットにあるので、有効利用することにした。
ただ、1, 2の為のtapeのeditが少々時間を要するので、市販の教材tapeにあらかじめ含まれていたら非常に助かる。ワークショップに参加しながら、学習者としての自分自身の体験の分析と、今直面しているListeningの授業内容を考え続けたので、以上のような客観性に欠ける報告書となってしまったことをお許し頂きたい。しかし、体験分析から内容理解/語学習得と映像の相関について再び考えさせられる機会が与えられ、意味のある時を過ごせた。(櫻井敏子 神戸松蔭女子学院大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(1)
「TOEFL-CBT対応を考慮したCALL教材の可能性 Academic Lecture・Discussion・Presentationをも含めて」
松田 憲(立命館大学)、津熊 良政(立命館大学)
立命館大学文学部2回生を対象に、同大学で開発されたCNNニュース番組を中心としたLAN対応のマルチメディア教材を使用した結果について発表された。
TOEFL-CBT対応を考慮に入れ、クラス内でのグループワークやペアワーク、ディスカッション、プレゼンテーションなどを取り入れた授業を行った。授業用プログラムにはCBTのインターフェースと出題形式を採用し、問題作成に当たっては、当該教材のリスニングとリーディング部分を利用した。また、小テスト用プログラムとして別途問題を作成した。プログラムの利用形態は、学生端末からサーバーへアクセスして教材を利用し、学習履歴や練習問題の成績がサーバーに保存された。
発表の最後で、学生へのアンケートの結果が紹介され、この教材に対して満足度の高いことが報告された。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(2)
「字幕形式を用いた中国語教材提示の試み」
中西 正樹(摂南大学)
中国語中級以上のLLクラスにおいて、シャドウイングに文字を加えたパラレルリーディング用の教材を使用した結果について発表された。
この教材は、1つの句または文で構成される比較的短い中国語の表現と、それに対応する音声表示、及び意味(+語注)に音声が付加されたものである。今回の発表では、この教材のデモンストレーションが行われ、更に、学生がLL教室で教材を映し出したモニター画面を見、流れてくる音声を聞いて、実際にパラレルリーディングを行っている様子がビデオで紹介された。
最後に、この指導方法を3年に亘って試した結果、音声処理能力と意味理解の向上に有用であることが分かり、中国語以外の外国語への応用も可能ではないかと述べられた。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(3)
「ESPとしての大学英語教育の可能性について」
東 淳一(流通科学大学)
英語を専門としない学部・学科におけるESPを意識した英語教育の可能性について発表された。
学部・学科で学ぶ事柄を英語の授業で補強することは意義のあることで、例えば、経済・経営関係の学部や学科の学生にとって、現在の為替相場で1米ドル・1ユーロが日本円でほぼいくらかを知ることは極めて重要な意味を持つ。また、ESPクラスで利用するテキストについて、学生の語学力の向上と知的欲求を満たす上で、商学部や経営学部を例にとると、MarketingやManagementに関する海外のテキストを使用することを推奨する。
発表の最後に、流通科学大学の外国語の新カリキュラムが紹介され、その中でのESP的な科目の位置づけについて触れられた。(以上文責:井狩幸男 大阪市立大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(4)
「英語とコンピュータを使った教際教育-実践的な英語力を伸ばす授業例」
船越 貴美(神戸学院大学付属高等学校)
本研究発表は、船越氏が最近まで勤務されていた桜丘女子中学高等学校(東京都北区)におけるネットワークシステムを活用した授業実践に関するものである。同校のコンピュータ環境施設(SMARTⅠ、SMARTⅡ、CALL、MRC)を利用して、英語科、情報科、国語科(古典)、社会科(日本史)がそれぞれ教科の枠を越えて協力しあい、生徒の実践的な英語力を伸ばす英語授業を構築し継続的に実践されたという、まさに「教際的な」英語教育の実践報告である。
英語教科書学習への動機付けとして、教材に関するサイトの調べ学習のほか、特に1年では「日本昔話」の英語版紙芝居の作成と日本文化の紹介を情報科・古典・日本史の協力で教際化。2年では、教科書のレッスンに関係したサイトを検索・閲覧させた後、作成した英文レポートをe-mailで提出させ、添削・返却する等。3年では、日本と西洋の迷信を調査・比較考察・英訳/和訳・参考文献の作成などの作業のほか、Nice Spot Projectと題して地元北区にある銭湯や東京大仏などを紹介する英文Webページの作成。さらに3年では自分の好きな洋楽・歌手を紹介するサイトを英語/日本語の両方で製作し、自分の作品紹介を各自英語でプレゼンテーションする、製作したWebページの評価もオンライン評価表を使って行う等の授業活動が、授業風景の映像も含めて紹介された。
本発表で注目されるのは、まず第1に、このような教際教育を実現できる教育環境のすばらしさである。ある教科での教育目標達成のために、複数の他教科が教科の枠を越えて協力・支援しあうことは、各教科のカリキュラムの特性やそれぞれの進度等の面から困難が多いものである。それ故に一層、将来の可能性を示唆する実践例であるといえよう。第2は、幸い他教科の支援が得られても、授業の主担当者である英語科教員の負担も相当なものであろうと推察されるにもかかわらず、4年前からこれを実践されている英語科の先生方の熱意と実行力である。リアルタイムでの情報検索や閲覧、得られた情報を消化・活用する活動、それをもとに新たに自分自身の情報を造り出して発信する活動は、授業のダイナミズムを的確に実現したものであり、生徒がそれらの段階的な諸活動を通じて、単なる動機付け学習を越えて、本研究が究極的に目指している「実践的な英語力を伸ばす」方向で授業に浸る様子が目に浮かぶようである。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(5)
「英語学習者のリスニングにおけるポーズの影響について」
菅井 康祐(大阪電気通信大学・非常勤)
本研究は、英語学習者の聴解を助けるためには学習者に提示する音声教材の速度を落とすよりも発話の中にポーズを挿入したり、ポーズを長くしたりすることの方が有効である、という先行的研究成果を踏まえ、発話文中のポーズが学習者の聴解に与える影響を、ポーズの長さと被験者のレベルの2点から分析することを目的としている。
ポーズの長さは、コンピュータ上に取り込んだ英検準2級のリスニング問題の、音声波形上明らかに視認されるポーズ(接続詞やカンマの前等)を100msec.ずつ、および文末のポーズを200msec.ずつ長くした4種類の問題に、元の問題を加えて、ポーズの短い順にA,B,C,D,Eの5種類の長さで調査が行われた。被験者のレベルは、予備調査として大学1年生165人に対し本調査と同様の問題をもとに作成したテスト結果により上位(35名)、中位(31名)、下位(37名)の3グループに分けられた。本調査のテストは選択問題形式で、DATに記録され、教室備え付けのスピーカーから1回提示。調査結果は、横軸がポーズの長さの異なる5種類のテストタイプを表し、縦軸がテストスコアを表す4つのグラフにより、被験者全体、および被験者のレベルグループ別に示された。
菅井氏の調査結果の分析と結論は、ポーズの長さの影響は被験者全体としてほとんど見られず、レベル別のデータでも、テストEの得点が若干他よりも良いという程度で、ポーズの長さとテストスコアの間の相関は見られない、つまり、ポーズの長さは被験者のリスニングに、正の影響は及ぼしていない、という結果が得られたというものであった。本研究の問題点として菅井氏は、グループ間のレベル差があまり大きくない点や被験者数が十分とは言い切れない点等を挙げられた。また、今後の課題として、効果的なポーズについて考える際には、単にその長さを変えるだけでは不十分で、効果的なポーズの挿入法も考える必要があると指摘された。
本研究は2つの可能性を示唆しているように思われる。第1は、菅井氏の分析通りポーズを長くするだけでは聴解を増進できない学習者やリスニング教材も確かに存在するという可能性である。第2は、第1の場合が生じるのはどのような場合か、またそのようなケースで、効果的なポーズの挿入法と組み合わせた時にはどうなるか、ポーズの長さは変えずにポーズの挿入法のみ変えた場合はどうか、教材や学習者のvarietyによってどのような変化が見られるか等、ポーズの長さに関連して様々な可能性を探り得る可能性である。どちらの意味においても、本研究は興味深い示唆に富んでいる。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(6)
「認知言語学的アプローチを基盤とした文法授業-名詞と知覚動詞の場合」
松本 知子(同志社女子大学・非常勤)
本研究は、従来英語教育の中で日本人学習者には指導が困難とされてきた冠詞等の多くの文法問題を解決する有効な指導法として、先行的研究の “bounded-unbounded schema(BUS)”池上(2000)という認知言語学的アプローチを基盤とした文法の授業を提案する内容である。
BUSでは、モノを認識する際に境界が存在する (bounded)ならば可算名詞、境界が存在しない (unbounded)ならば不可算名詞として扱う。BUSの考え方に従えば、従来明らかに可算名詞と考えられてきたものが不可算名詞となる場合の説明が容易となる。例えば、
(1)Add more apple to the salad.
(2)After we ran over the cat with our car, there was cat all over the driveway.
のように、スライスしたりんごや轢かれてグシャグシャになった猫には境界がなくなるので、不可算となる、という具合に、人間の外界認識により可算名詞が不可算名詞になることが可能となる。
BUSの有界性の捉え方(construal)を知覚動詞にあてはめると、補文構造におけるthat節と原形不定詞・現在分詞の区別も相同的に捉えられる。つまり、主語の知覚の枠内において、原形不定詞が示す事態はboundedとして捉えられ、現在分詞が示す事態はunboundedとして捉えられる。I saw her drown, but I rescued.という英文がなぜ非文になるかということも、BUSを用いれば容易に説明できる。
認知言語学的アプローチでは、形式的な構造と文法の意味的諸相との間のギャップを、共通の認知的基盤であるBUSにより、双方を関連づけ結びつけることができる。
以上のような観点から松本氏は、BUSを用いれば、異なるカテゴリーに属している名詞の可算・不可算の区別と知覚動詞の補文構造の区別とを関連づけて教えることが可能になる、また学校文法ではほとんど教えられることのない、言語の形式や構造が「なぜそうなっているのか?」という認知的な問いかけに答えを提供できるようになる、として認知言語学的アプローチを基盤とした文法の授業を提案された。明解で興味深い提案である。松本氏によればBUSの考え方は他の文法カテゴリーにも広く応用できる可能性があるということなので、今後の発展的研究が期待される。(以上文責: 弓庭喜和子 大阪外国語大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジアム
「21世紀に求められる日本の英語教育について」
総合司会:杉森 幹彦(立命館大学教授)
パネリスト:杉本 義美(京都府教育委員会指導主事)
原田 高好(大阪城南女子短期大学教授)
松田 憲(立命館大学教授)
青木 幹生(神戸海星女子学院大学非常勤講師)
このシンポジウムでは、「21世紀に求められる日本の英語教育」をテーマとして、上記4名のパネリストによって、それぞれの立場から長年の教育実践を踏まえて、現状分析と問題点が指摘され、将来への展望と提案が述べられた。まず最初に、中学校における英語教育と教育行政の立場から、杉本義美氏が、中学・高校における英語の授業について具体的な事例を紹介しながら、その現状と課題を指摘された。さらに、平成13年1月に文部科学省から出された「英語指導方法等改善の推進に関する懇談会」報告書と照らし合わせながら、中学・高校における今後の英語教育の方向性について示唆に富んだ提案が行われた。
次に、高等学校における英語教育と社会人の立場から、原田高好氏が、21世紀の日本の社会を予見し、多くの関連データを提示しながら、日本における英語教育のあり方について提言された。情報化・国際化の進展と教育の自由化が一段と普及する21世紀の日本において、「誰が、何の目的で、どのような英語を、いつ、どこで学ぶのか、そしてそれを誰が教えるのか」について再検討が必要であり、全地球規模の交流が一層現実化する新世紀において、国際補助語としての英語を、主として「交流言語」として学ぶことの必要性が力説された。
続いて大学英語教育の立場から、松田 憲氏が、文部科学省・大学審議会の各種答申や、「英語指導方法等改善の推進に関する懇談会」報告、「21世紀日本の構想懇談会」報告書などに見られる最近の議論を紹介しながら、主として大学など高等教育における外国語教育、特に英語教育のあり方について、多面的な視点から導かれた課題と問題提起がパワーポイントによって明確に指摘された。外国語によるコミュニケーション能力の養成については、単に知識や情報を吸収する能力だけではなく、情報を発信し、プレゼンテーションや討論を行うための基本的な能力の習得が社会から強く求められており、情報通信技術を活用した教育方法や教育内容、および設備の改善が必要であることが力説された。
最後に、JTB海外支店や神戸ベイシェラトンホテル国際業務担当部勤務の時代に、国際的な実業界の第一線で活躍してこられた青木幹生氏が、ビジネスマンの立場から、企業における英語の重要性と企業内研修,企業とTOEIC、さらに企業が大学の英語教育に望むもの、生涯学習の重要性とイマージョン・プログラムの効果などについて、データや仕事上の体験エピソードを交えながら語られた。従来は企業で必要な英語といえば主に貿易英語であり、英語に強い「英語屋」が一手に仕事を引き受けていたが、これからは管理・営業・研究などあらゆる部門で英語が必要となり、社員の採用人事・担当業種の決定・海外出張や昇進の審査などにもTOEICのスコアが重要な条件になるとのことである。例えば、ある外資系の会社では、課長担当職は500点以上、次長担当職は730点以上、長期海外出張にも730点以上が要求されているようである。
以上4名のパネリストの提言から、21世紀に求められる日本の英語教育の方向性を探ってみよう。21世紀はIT革命とグローバリゼイションが一段と進み、多くの分野における活動が、全地球規模で行われるボーダレス時代になるであろう。このような時代において、国際レベルで活躍できる有能な人材の育成が社会から強く求められている。将来学生がどのような分野に進み、どれだけの学生がどのレベルの英語運用力を必要とするかは明言できないが、どの道に進もうとも、英語の基本的な学習を徹底的に行い、基礎的なレベルであれば、必要なコミュニケーションが確実にできるところまで指導し、運用能力を習得させることが不可欠である。
中学校では、言語材料の指導が理解のレベルで終わっている授業が多いようであるが、基礎的な言語材料を反復して段階的に積み上げ、日常の生活環境の中で、英語によるコミュニケーションができるところまで徹底した指導が必要である。そのためには、学習者のレベルとニーズに適した教材を選び、到達目標を確立し、相対評価ではなく絶対評価を導入すべきである。ITによるメディアの利用などにより、学習意欲を高め維持できるような指導法を工夫し、将来必要な場合には、国際社会でコミュニケーションの手段として通用する能力を養成するための基礎を確立しておかなければならない。ここで重要なことは、英語教師自身の英語運用力と優れた指導力、そしてこれからの英語教育に対する確かなビジョンである。日本の社会構造や経済・文化・生活スタイルと、言語コミュニケーションとの関係を歴史的に振り返ると同時に、新世紀の日本の社会を予測しても、すべての日本人に高いレベルの英語運用力が必要になるとは断言できないであろう。英語の運用力としては、日常生活や海外旅行などに最低限必要なレベルを目標としながら、将来さらに高度なレベルの運用力が必要な場合には、自発的に学習できるだけの基礎学力をミニマムなものとして、すべての高校生・大学生に習得させることを目指さなければならない。さらに、英語を通して異なった民族の文化や生活スタイルを理解し、日本人とは異なった価値観や倫理観、発想や表現方の違いなどを理解することによって、地球市民の平和と多元的共存に貢献する自覚と行動力を養成することが必要である。
一方、グローバルな規模で国際的に活躍することを目標とする学生、例えば政治・経済・ビジネス・海外留学・研究・文化交流・スポーツ・マスコミなどの多様な分野で活躍する人材を育成する場合は、国際社会の場で十分通用する高いレベルの運用力を確実に習得することを到達目標として、その品質保証ができた学生を社会に送り出すことが社会の強い要求であり、私たちの使命である。そのためには、個々の学生が自分のニーズとレベルに合ったクラスを自由に選択履修できるカリキュラムのシステムが構築されなければならない。そしてIT革命による高度なテクノロジーを学習メディアとして活用し、学習者のニーズとレベルに合った個別の自発的学習と遠隔教育がさらに広く導入され、言語教育が一層効率的に行われなければならない。この段階では、英語を一つの科目として言語そのものについて学習するだけではなく、学習者の専門分野や将来取り組む職種に関連した分野の内容を、英語によって学習するcontent based方式の指導と学習が必要である。
言語はコミュニケーションのツールとして用いられているが、人間の学習・思考・感情・想像・表現などを生み出す源でもあることを忘れてはならない。人間の言語行動はコンピュターによってコントロールされたロボットの言葉ではないのであるから、どのような時代においても、人間と人間の関係、人間同士の心の繋がりと相互の人権を尊重した教育が根底になければならない。
このシンポジウムのパネリスト、および質問やご意見を頂いたフロアーの方々に感謝の意を表します。ご協力有り難うございました。(杉森幹彦 立命館大学)
--------------------------------------------------------------------------------
「会場校を引き受けて」
鈴木 寿一(京都教育大学)
支部長の杉森幹彦先生から春季大会の会場校の引き受けを打診されたのは、昨年の秋のFLEATⅣの反省会のあとの打ち上げ会の席上でした。反省会前に、「支部三役会議で、来年の春季大会は京都教育大学にお願いしては。」という案が出たことを事務局長の吉田晴世先生から伺いました。最初は、設備不十分を理由にお断りしようと思いましたが、反省会の間にいろいろ考えました。
私がLETの存在を知ったのは、神戸外大3回生の時に受講した、前支部長河野守夫先生ご担当の「英語教育工学」の授業を通じてでした。卒業直前に元支部長の田島博先生から入会を勧められた時、「仕事に慣れてから入会します。」とお答えしたところ、田島先生は「慣れてからでは遅すぎるよ。この春から支部の研究会に来なさい。」とおっしゃって、入会手続きをしてくださったのが、入会のきっかけです。今から29年前のことです。入会後は、河野先生からいろいろとご指導いただき、全国大会や支部大会での発表の機会を与えていただきました。また、役員の先生方、支部大会の会場を提供してくださった先生方、研究発表や実践発表をしてくださった先生方のおかげで、私はたくさんのことを学ぶことができました。このようなことが私の頭の中に蘇ってきて、春季大会の会場校をお引き受けする決心をした次第です。
冷房設備がない勤務校で春季大会を実施するには、例年の5月末から6月中旬では参会者の方々に不快な思いをしていただかねばならないため、4月28日と29日に開催することにしました。通常この時期は学会は行なわれない時期ですので、どのくらいの方が参加してくださるか自信はありませんでしたが、2日間参加された方と1日参加された方を合わせると、実数で100名以上の方が足をお運び下さいました。ただ、使用教室の座席の配置、施設、昼食などで、役員の先生方はじめ、発表者の先生方や参会の皆様にも大変ご不便をおかけいたしましたこと、また、電気容量不足と使用教室付近のスペ-スの関係で、賛助会員には会場教室とは異なる階で展示していただかねばならなかったことなど、お詫び申し上げます。
最後に、支部春季大会を開催するに当たり、会場の下見から終了までご尽力下さいました支部事務局の吉田晴世先生、小山敏子先生、そして、準備から後片づけまでご協力下さった同僚の西本有逸先生に、この場をお借りしてお礼申し上げます。
「21世紀の外国語教育を考える」
鈴木孝夫先生(慶応義塾大学名誉教授)
鈴木先生のご著者は、近著を含めて5-6冊に目を通していたが、やはりご本人の講演は迫力が違っていた。先生は、「必要もないのに英語を学べるはずがない」、「日本が大国になったこと自体が間違いだ」と刺激的な言葉を次々と繰り出される。しかし、その後には、必ず説得力のある解説を加えられる。言語学、歴史学、社会学などに造詣の深い鈴木先生ならではの「うーん」と唸らせる解説である。
まず、氏は、訳読型の外国語教育が、発展途上の日本にはきわめて効率的で、ふさわしものであったと指摘される。この外国語教育法のおかげで、日本は国の独立を保ちつつ、先進国の仲間入りをしたのだ。しかし、80年代、日本が先進国となった時に、この方法をオーバーホールし、情報発信型に切り替えるべきであった。それをせず、十年(いや百年)一日のごとく、情報吸収型の教育法の延命を図ったために、今、その綻びが頂点に達しているという。
それでは、どのように外国語教育を変えるべきであろうか。氏は、外国語を使って、日本の事情を世界へきちんと説明できるような能力の育成を行うべきであると指摘する。さらに、日本は、米国や欧州、イスラム諸国などのように、世界を説き伏せるような主義主張を持たないが、江戸時代に200年以上にわたり平和な国家を維持した実績を持つ国であり、このノウハウを発信することで、世界を導いていくことができると主張される。加えて、国家戦略として、(時には脅しや、取引もしながら)日本語の国際語化を図るよう、働き掛けていく必要があることも強調された。
一口も水を飲まず、座ることもなく、予定の時間をはるかに超えて熱弁をふるわれる先生の姿を見ていると、なにか仕事をし残した、使命感にかられた鬼神のようなものを見る思いがした。先生は、講演後、求めに応じて「出る杭は打たれる。しかし、出すぎた杭は打たれない。」と書かれたという(いわゆるジップの法則)。日本が「出すぎた杭」になるまでは、鬼神の休む暇はないようである。(竹内 理 関西大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業実践報告(1)
“Welcome to My Classroom”
Andrew Obermeier(京都教育大学)
Andrew Obermeier先生の「Communicative English Ⅲ」の授業風景をビデオで見せていただいた。履修登録した学生は英語専攻の3回生6名で、これまでにオーラル・コミュニケーション関係の科目を2科目単位習得している。使用テクストはNew Headway English Course, Upper-intermediate.(Oxford University Press)で、文法学習と四技能をうまく絡ませながら、全体的なコミュニケーション能力を高めることを授業の目標としている。授業の構成は、文脈を考慮に入れた文法学習のドリル・あるテーマに沿った読みと内容理解の言語活動・そのテーマに即して自分の意見や考えを発表し合う言語活動・他の授業科目について短い要約を書き、お互いに感想を述べ合う言語活動と盛り沢山である。
私が特に感心させられた点は、文法の扱いと先生の懇切丁寧なフィードバックの仕方である。先生は“Communicative ability develops alongside, or even behind grammatical acquisition.”と考えておられ、コミュニケーション重視の風潮下にあっても決して文法の学習を軽んじておられないことである。例えば、Discussing Grammarという言語活動では、以下のような2つの文の意味の違いを動詞の形態に注意させ、英語で話し合わせている(a. You're very kind. Thank you. b. You're being very kind. What do you want? / a. You're annoying me with all your questions. b. I can see you're annoyed. What's the matter?)。先生はある文法項目の形態が選択される理由を多くの例文と豊かな文脈を示しながら、説明しておられる。学生の方にも、使用される文脈やニュアンスの違いをなんとかして英語で説明しようと努力する姿が窺えた。
次にフィードバックの仕方であるが、授業中の文法訂正や発話を誘発するフィードバックはもとより、毎時間の宿題をテープに録音させ、学生が提出したテープに懇切丁寧なフィードバックを心掛けておられる。学生は読みの課題をこなし、内容理解の質問に口答しながら録音する、また文法のドリルに口答したものを録音する。先生は提出された録音テープの文法・発音・抑揚などを入念にチェックされ、コメントを録音して返却されているのである。授業全体として、語学学習の基礎・基本を丁寧におさえながら、学生の口頭活動を保証し、フィードバックの行き届いた、文字通りintensiveな授業であった。(西本有逸 京都教育大学)
--------------------------------------------------------------------------------
授業実践報告(2)
「四技能を伸ばすための授業」
大窪 美祈(京都市立紫野高校)
今春堀川高校から紫野高校に転勤された大窪先生による英語Ⅰの授業(Polestar English Course I Lesson 10 "Without Valleys You Can't Have Mountains")をビデオで見た。前任校(堀川高校人間探求科:男子14名、女子27名)で12月に収録されたものである。前時にリスニングによる大意把握と重要語句の確認が終了していた。 英語係りの生徒が“Stand up.”と号令をかけて授業が始まった。ウォームアップとしてシリーズで行っている「今日の一言」が板書され音読練習を行った。また、月ごとに練習し期間中に歌うと得点となる英語の歌が流された。
次に、ペア同士が新出語を簡単な英語で説明し、該当する単語を当てるMagical Quizを実施した。その後、本文のCD(意味単位でポーズを置き、後で出てくるSight Translationを踏まえたもの)をペースメーカーとした黙読を行った。英検2級2次試験風の2枚のイラストを用いたカードを使用し、ペアがQ&Aを行い、本文の要点を再確認した。ここで宿題となっていたSight Translationの形式の日本語による穴埋めワークシートで細部を確認した。基本的には難解な個所についての生徒からの質問に答える方式をとっていた。
次に、本時でのポイントのunlessを使用した単文を板書で取り上げた。意味確認と音読練習後、決められた時間で音読しながら筆写する多量高速音読筆写を行った。次に、Sight Translationを基盤とし、日本語交じりや穴埋めにしたワークシートを見て、生徒たちは本文を音読再生した。最後に、Faster Writingとして3分を与えた。与えられた題は、本文に則し"Who are you?"であった。1分で構想を練った後で、Fluencyを目標に2分で意見を英語で書いた。その後、生徒たちはその英文を読み上げるのではなく、その内容をもとにペアでスピーキング活動を楽しんだ。
読んで訳すだけの授業でなく、生徒たちは全ての高度な活動を、楽しく生き生きとこなしていた。質疑応答では、フロアーから「Sight Translationの形式を生徒たちが徐々に自立できるように工夫するとよい」とのアドバイスや音読の際の英語らしいリズムを強化する方法が紹介された。四技能のバランスの取れた活動がうまく絡み合い授業者の目標はよく達成されて、「本文の完全学習を音声を有効活用した多彩な活動で行っている」や「ワークシートが緻密に計画されている」など本授業を高く評価する意見が出た。(溝端保之 大阪府立泉南高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(1)
「CALLソフトウェアにおけるFeedback情報の役割-CALLとLLの違い-」
三根 浩(同志社女子大学)、吉田晴世(摂南大学)
一般に、LL(Language Laboratory)と、その発展形として捉えられているCALL(Computer Assisted Language Learning)システムの両者を、背景にある教育理論の基本的理念から比較し、教育デザインの違いを多数のビデオ映像による視覚資料を織りまぜて、詳細に説明された。また、その差異化を図るCALLソフトウェアについて開発中のデザインを紹介された。 LLは、構造主義言語学と行動主義心理学を背景とするAudio-Lingual Habit Approach(ALH)に基づき、刺激-反応(S-R)結合により言語学習が自然に成立するということを前提とし、教材を難易度順に細分し、(i+1)を連鎖させていく直線型のプログラム学習(Skinner, 1957)を推進した。しかし、1970年代に生成文法と認知心理学に基礎をおくCognitive Code Learning Approachが盛んとなり、言語獲得に際してインプットの量に対してはるかに多くの言語産出の可能性が指摘された。ところが、この手法も言語獲得装置(LAD)を活用できない大学生レベルの実践では行き詰まりを示した。1980年代からのCommunicative Approachでは、個別学習からグループ学習へ移行し、外国語によるタスクを解決させることで、より認知的な語学学習を目指すものとなった。
言語学習では、言語活動におけるKnowledge BaseとしてのMental Lexiconを獲得する認知的な学習が必要であるが、LLによる学習では認知的学習を阻害する要因がある。LLでは、基本的設計がS-R理論に基づいているため、学習の初期に外発的動機づけを行い、学習者に試行錯誤に基づく単純な学習ストラテジーを使用させ、単なる条件づけによる学習を誘発してしまう。試行錯誤とはTrial & Errorで、Errorにつながるすべての反応を制止させることで学習への動機づけを低下させてしまう結果を伴う。
認知的学習を成立させるには、反応の制止につながる試行錯誤を排除した内発的動機づけが必要である。反応の増強、認知的興味を促す適正なフィードバック情報(KR: Knowledge of Results)をリアルタイムに提供し、認知地図の形成を促し、潜在記憶の形成ストラテジーを促進させることが重要である。そのためには、①インタラクティブ ②マルチ・プロセス ③ハイパー・メディアという特徴をもつマルチメディアの活用が適している。
最後に、従来の直線型プログラム学習やドリル学習を排し、インタラクティブに情報を取り出せ、誤解答に対して即時にKR情報を与え、記憶のストラテジーを促進させる、現在開発中のマルチメディア型CALLソフトウェアを紹介された。句動詞によるコアイメージ学習を簡易な4コマ・アニメにより形成するためのシステムを提示され、上述の理論に応じた認知地図形成を促す上でのフィードバック情報の重要性を示された。(倉本充子 近畿大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(2)
「英語の音声指導」
有本 純(関西国際大学)
有本氏は実践的な観点から発音指導について話をされた。有本氏によると、発音指導が困難な理由として、クラスサイズ、時間の制約、指導項目の優先順位、モデルと目標、教師の役割の5つがあるという。学習者が1人ずつ異なった問題を抱えており、指導が原則として個別にしか対応できないという理由から理想的なクラスサイズは10名以内であり、時間的制約については1回の授業時間の中で発音指導に使える時間、またその内1人にかけられる時間が非常に限られている。その結果、現状の英語教育では発音指導は後回しか、放置される傾向にある。モデルと目標については、実際の現場は完全なイギリス英語やアメリカ英語を教えているわけではないので、日本語訛りの英語であってもよい。教師の役割として、日本語音声との違いを知り、英語音声学の知識を持ち、わかりやすく説明できる、自分で発音のモデルを示すことが出来る、発音が自学自習できないものであることから、学習者の発音を正しく判断し、指導できる存在になることだと述べられた。
また、有本氏は日本人学習者がアメリカ英語を学び、アメリカ英語の話し手になるのをモデル1とし、ニホン英語の話し手になるのをモデル2とされた。両者の比較として、モデル1では学習者は無力感と劣等感に悩み、英語運用に消極的になること等が挙げられ、モデル2では役に立つ英語は使える英語でなければならない等の意識的特徴がある。
さらに、有本氏は指導に用いる記号、発音の間違いとその原因、発音指導の留意点についても話をされた。具体的発音指導について、母音ではイメージを与えることを強調され、区別の必要な母音を重点的に指導すること、二重母音は日本語には存在しないことを認識しておくこと、子音の指導では、破裂音は語頭と語末に注意すること、摩擦音は息の強さで決まること、日本語近似音で代用できない子音は重点的に指導することについて話をされた。さらに音の連続、ポーズの入れ方、イントネーションの指導、強勢の指導など多岐にわたり詳しく述べられた。
今からできることとして、発音練習は楽しく、大きな声を出しても恥ずかしくないという雰囲気作りをすること、常に発音に注意を向けさせる努力をし、毎時間少しでも発音練習をする時間を入れることを挙げられた。教師の態度としては親しみやすく、リラックスした雰囲気、生徒との信頼関係の構築などに心がけ、暗唱やシャドウイングなど教科書の音読も利用してみる等の工夫を挙げられた。(杉本智昭 大阪電気通信大学高等学校)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(3)
「外国語としての英語の語彙学習を考える」
門田 修平(関西学院大学)
中西 義子(大阪国際女子短期大学)
横川 博一(京都外国語大学)
3人の講師の方々は、順にLET関西支部の基礎理論研究部会の部会長、副部会長、事務局長を務められている。本研究部会では、中心的な目標を「外国語としての英語における語彙獲得過程の解明」と定め、共同研究などを進めており、本ワークショップはその成果を報告し、語彙学習に対してどのような示唆が得られるかを考えようと企画された。
まず、中西講師が、大学生が入学時にどれくらいの英語の語彙サイズを持っているかを把握するための調査結果を報告した。入学直後の大学生に対し、単語の意味が分かるかどうかをYes/Noで答えさせ、さらに日本語の意味を書かせる2段階の調査を通し、大学入学時の平均的な受容語彙サイズは約2100~2600語、発表語彙サイズは約1900~2300語程度と推量した。読解における必要語彙数は3000語であるらしく、それには達していないと推定された。次に門田講師が、単語認知の2重アクセスモデルを説明した後、これまで行われたメンタルレキシコンの語彙のネットワーク構造に関する調査とメンタルレキシコンの語彙上へのアクセスに関する調査の結果を報告した。一連の実験から、“意味を知っている単語の場合は反対・対語関係など意味的ネットワークが緊密だが、意味の把握が不十分な場合は、音韻的な語彙ネットワークが活性化する”や、“正書法処理よりも音韻処理の方が時間がかかり、かつ正答率も低い”などの結果が報告された。最後に横川講師が、The evidence examined by the judge turned out to be unreliable. のような難解な文の理解に語彙情報がどのように利用されているかについて考察した。一連の実験の結果、文の理解では早い段階から語の持つ統語的・意味的情報をできるだけ利用していることが分かり、英語学習者に対しても、語彙情報を利用した直読直解を指導することが有効であると提案された。
このワークシップに参加して、英語学習者の語彙の構造に対する関心が高まり、英語学習における語彙の重要性が改めて認識されたように思う。今後、基礎理論研究部会を中心にさらに実証的な研究が積まれ、その成果をまたご報告いただけることを楽しみにしている。(石川圭一 京都女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
ワークショップ(4)
「ビデオ教材の効果的な利用法-理論と実践」
山根 繁(甲南女子大学)
金星堂のビデオ教材ABC Newsの著者のお一人の山根繁氏のワークショップである。まずニュース英語の一般的な特徴が述べられた。文の語数は5~9から15~19語のものが多い。このような語数から単文が全体の48.6%を占め、続いて複文が26.9%を占めることは容易に受け入れられる。スピードは177~161語/分で、時制は44.3%が現在形、40.2%が過去形となる。スピード以外は学生にとって負担が大きいとも思えない。
なぜ英語ニュースは記録者櫻井が高校/大学生時代に、いつも圧倒されていたのだろうか。語彙?スピード、息の区切りのポーズが短すぎた?発音と単語が一致しない、叉は語と語の間で起こる音声変化についていけなかった?一体どれだったんだろうか?ニュースが終わった後に数語が記憶に残るだけであったのはどうしてなんだろうと山根氏の話しを聴きながら昔を振り返りはじめた。大学生の時聴いていたVoice of Americaのspecial Englishとregular Englishで同じニュースでも理解度が違った。限られた語彙でゆっくりと読まれる短い文からなるニュースは理解出来た。しかし、その前に聴くregular English Newsはただ胃が熱くなるだけだった。special Englishの後のregular Englishでのニュースはさすがに理解出来たが。
映像と理解度の問題、映像があれば理解に助けになるのは分かるが、あのVoice of Americaのregular Englishに映像があれば、special English程に理解出来たのだろうか。映像の助けを受けての理解度はL2を発展させるのに、つまり語学習得の究極的な促進剤になるのだろうか。NHK第2放送の英語ニュースや短波放送で英語を聴いていた私には、映像の力に疑問が残る。記録者自身がマルチメディアと常に言いながら、山根氏のお話を伺いながら不遜にも自分の今までのプロセスを分析しメモし続けてしまった。
ビデオ教材の一般的なお話の後に、山根氏の著書“ABC News”の紹介があった。この本についてはよく知られているし、本を一見すれば内容が分かる。そこで、この教材を今年度の授業に採用している私が工夫していることを2点最後に付け加えておきたい。
1.教材の一つのaudio tape のsummeryのoral repetition用のtapeを私は作成している。学生は何度も練習して、最後に本なしでoral repetitionをして提出している。音読がどれ程記憶に効果的かを「週間朝日」に予備校の先生が書いておられたのに感化されて、自分でもやってみて納得したので、学生への課題にした。
2.本文で習得して欲しい表現や、文型は「同時通訳ゲーム」と称して練習している。つまり私が日本語で言ったのを、学生が同時通訳していく訳である。このゲームは本文を簡単に応用して出来るものだから、faked 同時通訳となっているが、習得して欲しい表現が各ユニットにあるので、有効利用することにした。
ただ、1, 2の為のtapeのeditが少々時間を要するので、市販の教材tapeにあらかじめ含まれていたら非常に助かる。ワークショップに参加しながら、学習者としての自分自身の体験の分析と、今直面しているListeningの授業内容を考え続けたので、以上のような客観性に欠ける報告書となってしまったことをお許し頂きたい。しかし、体験分析から内容理解/語学習得と映像の相関について再び考えさせられる機会が与えられ、意味のある時を過ごせた。(櫻井敏子 神戸松蔭女子学院大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(1)
「TOEFL-CBT対応を考慮したCALL教材の可能性 Academic Lecture・Discussion・Presentationをも含めて」
松田 憲(立命館大学)、津熊 良政(立命館大学)
立命館大学文学部2回生を対象に、同大学で開発されたCNNニュース番組を中心としたLAN対応のマルチメディア教材を使用した結果について発表された。
TOEFL-CBT対応を考慮に入れ、クラス内でのグループワークやペアワーク、ディスカッション、プレゼンテーションなどを取り入れた授業を行った。授業用プログラムにはCBTのインターフェースと出題形式を採用し、問題作成に当たっては、当該教材のリスニングとリーディング部分を利用した。また、小テスト用プログラムとして別途問題を作成した。プログラムの利用形態は、学生端末からサーバーへアクセスして教材を利用し、学習履歴や練習問題の成績がサーバーに保存された。
発表の最後で、学生へのアンケートの結果が紹介され、この教材に対して満足度の高いことが報告された。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(2)
「字幕形式を用いた中国語教材提示の試み」
中西 正樹(摂南大学)
中国語中級以上のLLクラスにおいて、シャドウイングに文字を加えたパラレルリーディング用の教材を使用した結果について発表された。
この教材は、1つの句または文で構成される比較的短い中国語の表現と、それに対応する音声表示、及び意味(+語注)に音声が付加されたものである。今回の発表では、この教材のデモンストレーションが行われ、更に、学生がLL教室で教材を映し出したモニター画面を見、流れてくる音声を聞いて、実際にパラレルリーディングを行っている様子がビデオで紹介された。
最後に、この指導方法を3年に亘って試した結果、音声処理能力と意味理解の向上に有用であることが分かり、中国語以外の外国語への応用も可能ではないかと述べられた。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(3)
「ESPとしての大学英語教育の可能性について」
東 淳一(流通科学大学)
英語を専門としない学部・学科におけるESPを意識した英語教育の可能性について発表された。
学部・学科で学ぶ事柄を英語の授業で補強することは意義のあることで、例えば、経済・経営関係の学部や学科の学生にとって、現在の為替相場で1米ドル・1ユーロが日本円でほぼいくらかを知ることは極めて重要な意味を持つ。また、ESPクラスで利用するテキストについて、学生の語学力の向上と知的欲求を満たす上で、商学部や経営学部を例にとると、MarketingやManagementに関する海外のテキストを使用することを推奨する。
発表の最後に、流通科学大学の外国語の新カリキュラムが紹介され、その中でのESP的な科目の位置づけについて触れられた。(以上文責:井狩幸男 大阪市立大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(4)
「英語とコンピュータを使った教際教育-実践的な英語力を伸ばす授業例」
船越 貴美(神戸学院大学付属高等学校)
本研究発表は、船越氏が最近まで勤務されていた桜丘女子中学高等学校(東京都北区)におけるネットワークシステムを活用した授業実践に関するものである。同校のコンピュータ環境施設(SMARTⅠ、SMARTⅡ、CALL、MRC)を利用して、英語科、情報科、国語科(古典)、社会科(日本史)がそれぞれ教科の枠を越えて協力しあい、生徒の実践的な英語力を伸ばす英語授業を構築し継続的に実践されたという、まさに「教際的な」英語教育の実践報告である。
英語教科書学習への動機付けとして、教材に関するサイトの調べ学習のほか、特に1年では「日本昔話」の英語版紙芝居の作成と日本文化の紹介を情報科・古典・日本史の協力で教際化。2年では、教科書のレッスンに関係したサイトを検索・閲覧させた後、作成した英文レポートをe-mailで提出させ、添削・返却する等。3年では、日本と西洋の迷信を調査・比較考察・英訳/和訳・参考文献の作成などの作業のほか、Nice Spot Projectと題して地元北区にある銭湯や東京大仏などを紹介する英文Webページの作成。さらに3年では自分の好きな洋楽・歌手を紹介するサイトを英語/日本語の両方で製作し、自分の作品紹介を各自英語でプレゼンテーションする、製作したWebページの評価もオンライン評価表を使って行う等の授業活動が、授業風景の映像も含めて紹介された。
本発表で注目されるのは、まず第1に、このような教際教育を実現できる教育環境のすばらしさである。ある教科での教育目標達成のために、複数の他教科が教科の枠を越えて協力・支援しあうことは、各教科のカリキュラムの特性やそれぞれの進度等の面から困難が多いものである。それ故に一層、将来の可能性を示唆する実践例であるといえよう。第2は、幸い他教科の支援が得られても、授業の主担当者である英語科教員の負担も相当なものであろうと推察されるにもかかわらず、4年前からこれを実践されている英語科の先生方の熱意と実行力である。リアルタイムでの情報検索や閲覧、得られた情報を消化・活用する活動、それをもとに新たに自分自身の情報を造り出して発信する活動は、授業のダイナミズムを的確に実現したものであり、生徒がそれらの段階的な諸活動を通じて、単なる動機付け学習を越えて、本研究が究極的に目指している「実践的な英語力を伸ばす」方向で授業に浸る様子が目に浮かぶようである。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(5)
「英語学習者のリスニングにおけるポーズの影響について」
菅井 康祐(大阪電気通信大学・非常勤)
本研究は、英語学習者の聴解を助けるためには学習者に提示する音声教材の速度を落とすよりも発話の中にポーズを挿入したり、ポーズを長くしたりすることの方が有効である、という先行的研究成果を踏まえ、発話文中のポーズが学習者の聴解に与える影響を、ポーズの長さと被験者のレベルの2点から分析することを目的としている。
ポーズの長さは、コンピュータ上に取り込んだ英検準2級のリスニング問題の、音声波形上明らかに視認されるポーズ(接続詞やカンマの前等)を100msec.ずつ、および文末のポーズを200msec.ずつ長くした4種類の問題に、元の問題を加えて、ポーズの短い順にA,B,C,D,Eの5種類の長さで調査が行われた。被験者のレベルは、予備調査として大学1年生165人に対し本調査と同様の問題をもとに作成したテスト結果により上位(35名)、中位(31名)、下位(37名)の3グループに分けられた。本調査のテストは選択問題形式で、DATに記録され、教室備え付けのスピーカーから1回提示。調査結果は、横軸がポーズの長さの異なる5種類のテストタイプを表し、縦軸がテストスコアを表す4つのグラフにより、被験者全体、および被験者のレベルグループ別に示された。
菅井氏の調査結果の分析と結論は、ポーズの長さの影響は被験者全体としてほとんど見られず、レベル別のデータでも、テストEの得点が若干他よりも良いという程度で、ポーズの長さとテストスコアの間の相関は見られない、つまり、ポーズの長さは被験者のリスニングに、正の影響は及ぼしていない、という結果が得られたというものであった。本研究の問題点として菅井氏は、グループ間のレベル差があまり大きくない点や被験者数が十分とは言い切れない点等を挙げられた。また、今後の課題として、効果的なポーズについて考える際には、単にその長さを変えるだけでは不十分で、効果的なポーズの挿入法も考える必要があると指摘された。
本研究は2つの可能性を示唆しているように思われる。第1は、菅井氏の分析通りポーズを長くするだけでは聴解を増進できない学習者やリスニング教材も確かに存在するという可能性である。第2は、第1の場合が生じるのはどのような場合か、またそのようなケースで、効果的なポーズの挿入法と組み合わせた時にはどうなるか、ポーズの長さは変えずにポーズの挿入法のみ変えた場合はどうか、教材や学習者のvarietyによってどのような変化が見られるか等、ポーズの長さに関連して様々な可能性を探り得る可能性である。どちらの意味においても、本研究は興味深い示唆に富んでいる。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表・実践報告(6)
「認知言語学的アプローチを基盤とした文法授業-名詞と知覚動詞の場合」
松本 知子(同志社女子大学・非常勤)
本研究は、従来英語教育の中で日本人学習者には指導が困難とされてきた冠詞等の多くの文法問題を解決する有効な指導法として、先行的研究の “bounded-unbounded schema(BUS)”池上(2000)という認知言語学的アプローチを基盤とした文法の授業を提案する内容である。
BUSでは、モノを認識する際に境界が存在する (bounded)ならば可算名詞、境界が存在しない (unbounded)ならば不可算名詞として扱う。BUSの考え方に従えば、従来明らかに可算名詞と考えられてきたものが不可算名詞となる場合の説明が容易となる。例えば、
(1)Add more apple to the salad.
(2)After we ran over the cat with our car, there was cat all over the driveway.
のように、スライスしたりんごや轢かれてグシャグシャになった猫には境界がなくなるので、不可算となる、という具合に、人間の外界認識により可算名詞が不可算名詞になることが可能となる。
BUSの有界性の捉え方(construal)を知覚動詞にあてはめると、補文構造におけるthat節と原形不定詞・現在分詞の区別も相同的に捉えられる。つまり、主語の知覚の枠内において、原形不定詞が示す事態はboundedとして捉えられ、現在分詞が示す事態はunboundedとして捉えられる。I saw her drown, but I rescued.という英文がなぜ非文になるかということも、BUSを用いれば容易に説明できる。
認知言語学的アプローチでは、形式的な構造と文法の意味的諸相との間のギャップを、共通の認知的基盤であるBUSにより、双方を関連づけ結びつけることができる。
以上のような観点から松本氏は、BUSを用いれば、異なるカテゴリーに属している名詞の可算・不可算の区別と知覚動詞の補文構造の区別とを関連づけて教えることが可能になる、また学校文法ではほとんど教えられることのない、言語の形式や構造が「なぜそうなっているのか?」という認知的な問いかけに答えを提供できるようになる、として認知言語学的アプローチを基盤とした文法の授業を提案された。明解で興味深い提案である。松本氏によればBUSの考え方は他の文法カテゴリーにも広く応用できる可能性があるということなので、今後の発展的研究が期待される。(以上文責: 弓庭喜和子 大阪外国語大学非常勤)
--------------------------------------------------------------------------------
シンポジアム
「21世紀に求められる日本の英語教育について」
総合司会:杉森 幹彦(立命館大学教授)
パネリスト:杉本 義美(京都府教育委員会指導主事)
原田 高好(大阪城南女子短期大学教授)
松田 憲(立命館大学教授)
青木 幹生(神戸海星女子学院大学非常勤講師)
このシンポジウムでは、「21世紀に求められる日本の英語教育」をテーマとして、上記4名のパネリストによって、それぞれの立場から長年の教育実践を踏まえて、現状分析と問題点が指摘され、将来への展望と提案が述べられた。まず最初に、中学校における英語教育と教育行政の立場から、杉本義美氏が、中学・高校における英語の授業について具体的な事例を紹介しながら、その現状と課題を指摘された。さらに、平成13年1月に文部科学省から出された「英語指導方法等改善の推進に関する懇談会」報告書と照らし合わせながら、中学・高校における今後の英語教育の方向性について示唆に富んだ提案が行われた。
次に、高等学校における英語教育と社会人の立場から、原田高好氏が、21世紀の日本の社会を予見し、多くの関連データを提示しながら、日本における英語教育のあり方について提言された。情報化・国際化の進展と教育の自由化が一段と普及する21世紀の日本において、「誰が、何の目的で、どのような英語を、いつ、どこで学ぶのか、そしてそれを誰が教えるのか」について再検討が必要であり、全地球規模の交流が一層現実化する新世紀において、国際補助語としての英語を、主として「交流言語」として学ぶことの必要性が力説された。
続いて大学英語教育の立場から、松田 憲氏が、文部科学省・大学審議会の各種答申や、「英語指導方法等改善の推進に関する懇談会」報告、「21世紀日本の構想懇談会」報告書などに見られる最近の議論を紹介しながら、主として大学など高等教育における外国語教育、特に英語教育のあり方について、多面的な視点から導かれた課題と問題提起がパワーポイントによって明確に指摘された。外国語によるコミュニケーション能力の養成については、単に知識や情報を吸収する能力だけではなく、情報を発信し、プレゼンテーションや討論を行うための基本的な能力の習得が社会から強く求められており、情報通信技術を活用した教育方法や教育内容、および設備の改善が必要であることが力説された。
最後に、JTB海外支店や神戸ベイシェラトンホテル国際業務担当部勤務の時代に、国際的な実業界の第一線で活躍してこられた青木幹生氏が、ビジネスマンの立場から、企業における英語の重要性と企業内研修,企業とTOEIC、さらに企業が大学の英語教育に望むもの、生涯学習の重要性とイマージョン・プログラムの効果などについて、データや仕事上の体験エピソードを交えながら語られた。従来は企業で必要な英語といえば主に貿易英語であり、英語に強い「英語屋」が一手に仕事を引き受けていたが、これからは管理・営業・研究などあらゆる部門で英語が必要となり、社員の採用人事・担当業種の決定・海外出張や昇進の審査などにもTOEICのスコアが重要な条件になるとのことである。例えば、ある外資系の会社では、課長担当職は500点以上、次長担当職は730点以上、長期海外出張にも730点以上が要求されているようである。
以上4名のパネリストの提言から、21世紀に求められる日本の英語教育の方向性を探ってみよう。21世紀はIT革命とグローバリゼイションが一段と進み、多くの分野における活動が、全地球規模で行われるボーダレス時代になるであろう。このような時代において、国際レベルで活躍できる有能な人材の育成が社会から強く求められている。将来学生がどのような分野に進み、どれだけの学生がどのレベルの英語運用力を必要とするかは明言できないが、どの道に進もうとも、英語の基本的な学習を徹底的に行い、基礎的なレベルであれば、必要なコミュニケーションが確実にできるところまで指導し、運用能力を習得させることが不可欠である。
中学校では、言語材料の指導が理解のレベルで終わっている授業が多いようであるが、基礎的な言語材料を反復して段階的に積み上げ、日常の生活環境の中で、英語によるコミュニケーションができるところまで徹底した指導が必要である。そのためには、学習者のレベルとニーズに適した教材を選び、到達目標を確立し、相対評価ではなく絶対評価を導入すべきである。ITによるメディアの利用などにより、学習意欲を高め維持できるような指導法を工夫し、将来必要な場合には、国際社会でコミュニケーションの手段として通用する能力を養成するための基礎を確立しておかなければならない。ここで重要なことは、英語教師自身の英語運用力と優れた指導力、そしてこれからの英語教育に対する確かなビジョンである。日本の社会構造や経済・文化・生活スタイルと、言語コミュニケーションとの関係を歴史的に振り返ると同時に、新世紀の日本の社会を予測しても、すべての日本人に高いレベルの英語運用力が必要になるとは断言できないであろう。英語の運用力としては、日常生活や海外旅行などに最低限必要なレベルを目標としながら、将来さらに高度なレベルの運用力が必要な場合には、自発的に学習できるだけの基礎学力をミニマムなものとして、すべての高校生・大学生に習得させることを目指さなければならない。さらに、英語を通して異なった民族の文化や生活スタイルを理解し、日本人とは異なった価値観や倫理観、発想や表現方の違いなどを理解することによって、地球市民の平和と多元的共存に貢献する自覚と行動力を養成することが必要である。
一方、グローバルな規模で国際的に活躍することを目標とする学生、例えば政治・経済・ビジネス・海外留学・研究・文化交流・スポーツ・マスコミなどの多様な分野で活躍する人材を育成する場合は、国際社会の場で十分通用する高いレベルの運用力を確実に習得することを到達目標として、その品質保証ができた学生を社会に送り出すことが社会の強い要求であり、私たちの使命である。そのためには、個々の学生が自分のニーズとレベルに合ったクラスを自由に選択履修できるカリキュラムのシステムが構築されなければならない。そしてIT革命による高度なテクノロジーを学習メディアとして活用し、学習者のニーズとレベルに合った個別の自発的学習と遠隔教育がさらに広く導入され、言語教育が一層効率的に行われなければならない。この段階では、英語を一つの科目として言語そのものについて学習するだけではなく、学習者の専門分野や将来取り組む職種に関連した分野の内容を、英語によって学習するcontent based方式の指導と学習が必要である。
言語はコミュニケーションのツールとして用いられているが、人間の学習・思考・感情・想像・表現などを生み出す源でもあることを忘れてはならない。人間の言語行動はコンピュターによってコントロールされたロボットの言葉ではないのであるから、どのような時代においても、人間と人間の関係、人間同士の心の繋がりと相互の人権を尊重した教育が根底になければならない。
このシンポジウムのパネリスト、および質問やご意見を頂いたフロアーの方々に感謝の意を表します。ご協力有り難うございました。(杉森幹彦 立命館大学)
--------------------------------------------------------------------------------
「会場校を引き受けて」
鈴木 寿一(京都教育大学)
支部長の杉森幹彦先生から春季大会の会場校の引き受けを打診されたのは、昨年の秋のFLEATⅣの反省会のあとの打ち上げ会の席上でした。反省会前に、「支部三役会議で、来年の春季大会は京都教育大学にお願いしては。」という案が出たことを事務局長の吉田晴世先生から伺いました。最初は、設備不十分を理由にお断りしようと思いましたが、反省会の間にいろいろ考えました。
私がLETの存在を知ったのは、神戸外大3回生の時に受講した、前支部長河野守夫先生ご担当の「英語教育工学」の授業を通じてでした。卒業直前に元支部長の田島博先生から入会を勧められた時、「仕事に慣れてから入会します。」とお答えしたところ、田島先生は「慣れてからでは遅すぎるよ。この春から支部の研究会に来なさい。」とおっしゃって、入会手続きをしてくださったのが、入会のきっかけです。今から29年前のことです。入会後は、河野先生からいろいろとご指導いただき、全国大会や支部大会での発表の機会を与えていただきました。また、役員の先生方、支部大会の会場を提供してくださった先生方、研究発表や実践発表をしてくださった先生方のおかげで、私はたくさんのことを学ぶことができました。このようなことが私の頭の中に蘇ってきて、春季大会の会場校をお引き受けする決心をした次第です。
冷房設備がない勤務校で春季大会を実施するには、例年の5月末から6月中旬では参会者の方々に不快な思いをしていただかねばならないため、4月28日と29日に開催することにしました。通常この時期は学会は行なわれない時期ですので、どのくらいの方が参加してくださるか自信はありませんでしたが、2日間参加された方と1日参加された方を合わせると、実数で100名以上の方が足をお運び下さいました。ただ、使用教室の座席の配置、施設、昼食などで、役員の先生方はじめ、発表者の先生方や参会の皆様にも大変ご不便をおかけいたしましたこと、また、電気容量不足と使用教室付近のスペ-スの関係で、賛助会員には会場教室とは異なる階で展示していただかねばならなかったことなど、お詫び申し上げます。
最後に、支部春季大会を開催するに当たり、会場の下見から終了までご尽力下さいました支部事務局の吉田晴世先生、小山敏子先生、そして、準備から後片づけまでご協力下さった同僚の西本有逸先生に、この場をお借りしてお礼申し上げます。