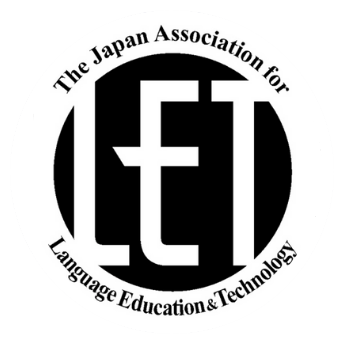大会名
99年度秋季研究大会
大会(春・秋・全国)
秋季大会
日付
1999年10月23日
会場
広島市立大学
概要
秋季大会は10月23日(土)10:30より広島市立大学(広島市安佐区大塚東)にて行われました。CALLに関するシンポジアム、学習方略、評価論などに関する研究発表7件、安田女子大学でのCALL授業の取り組み、広島市立大学のCALL施設見学など盛りだくさんな内容でした。講演には、心理言語学の分野で世界的に著名な、山田純先生(広島大学総合科学部)をお迎えして、『脳と記憶とことば』についてたいへん刺激的なお話いただきました。詳しくは、下記の報告をご覧ください。なお、支部総会では学会名称の変更(外国語教育メディア学会:LET)および理事数変更に伴う役員の改選選挙の実施が承認されました。
詳細
「会場校を引き受けて」
青木信之(広島市立大学国際学部)
平成11年10月23日土曜日にLLA関西支部秋季研究大会を広島市立大学で開催した。幸いなことに快晴で90名ほど、先生方のご参加をいただいた。
会場校の依頼があったとき、二つ心配な点があった。それは最寄り駅からのアクセスの問題と、昼食、懇親会などの食事の問題である。前者については、事務局の協力を得て、マイクロバスを借り上げることにより、円滑に参加者を輸送することができた。後者の食事については、学内の食堂に依頼した。昼食時は他学部の大きな学会と重なったこともあり、混み合ってしまい不便をおかけしてしまった。しかし、懇親会についは、ご参加くださった先生方から比較的好い評価をいただいたのでほっとした。学会の印象は、実は研究発表以上に、そこでの食事に左右されると言われるので、それだけに好印象をもっていただいて安心した。
学会会場としたのは、語学センターのCALL、LL教室4室であった。これらのいくつかはちょうど機器リース期間の満了に伴い、新しく更新されたばかりであった。それだけに学会にご参加くださった先生方に、新CALL教室をお披露目したいという気持ちと、うまく稼働してくれるだろうかという不安があった。幸い、事務や業者の方々の協力で、CALL 関係の発表も無事滞りなく行われた。
研究発表も、英作文自動添削システムといったものから、リーディング能力測定システムまで幅広く、また講演会も広島大学の山田純先生に挑発的なお話をしていただいた。広島では初めての支部大会であったが、内容的にかなり充実していたのではないかと思う。 最後になったが、学会を開催するにあたって、関西支部事務局の先生方、安田女子大学の松岡博信先生、同僚の岩井千秋、横山知幸、渡辺智恵先生、また、お手伝いしてくださった広島市立大学の事務職員の方や学生のみなさんにも大変お世話になった。この場をお借りしてお礼を申し上げたい。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-1
「談話構造とプロソディ」
藪内 智(大阪大学大学院言語文化研究科)
この研究は発話生成のプロセスにおけるプロソディ(韻律)の役割を明らかにするという目的で行われている。プロソディと談話構造の間には密接な関係があるという仮説のもと、英語母語話者による音声資料を用いて、プロソディと談話構造がどのように関係しているのかについて研究がなされている。英語教育への展望として、プロソディをもとに、日本人英語学習者が音読した音声資料と英語母語話者のものと比較し、パラグラフの効果的な読み方等の音声指導のあり方について考察をしようとされている。
当研究により、プロソディと談話構造の構造との間の関係が明らかになった際には、聞き手の理解を促進するような発話の指導への一助となるものと思われる。(広島大学大学院生藤谷丈雄)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-2
「英語教育における語用論的能力の構築と指導」
岡本芳和(関西外国語大学大学院)
この研究は、外国語で適切なコミュニケーションを図るにはその外国語の語用論的能力の習得が不可欠であるという仮説のもと、その語用論的能力の指導法の提案を目標とした研究であると思われる。
本発表では、1.現行の中学校と高等学校の学習指導要領にある「言語活動の取り扱い」と発表者が行った学習者対象のアンケート調査をもとに語用論的能力の指導の重要性を指摘し、2.語用論的能力の習得の過程を説明し、そして、3.その指導への提言がなされた。 第1点目に関して、学習指導要領の「言語の働き」の箇所では、言語行為に関する指導が要求されており、学習者の語用論的能力の習得が目標とされていることが指摘された。また、アンケート調査より、学習者も適切に英語を使用できる能力の習得を望んでいることが判明した。よって、語用論的能力の指導が重要であることがうかがわれた。
第2点目に関して、語用論的能力の習得は3段階からなることが指摘された。つまり、発話された内容を正確に理解する能力を習得し、その発話のなされている状況を理解する能力を習得し、実際の運用に至ることである。更に、発話の内容を正確に理解ができなくては、実際の語用論的能力の運用に至らないことが指摘された。
第3点目に関して、まず第1に、発話の内容が正確に理解できるよう指導すること、次に、発話内の力という概念を理解できるように指導することが提言された。実際の指導例は、発表者により、教科書のサンプルを用いた説明がなされた。この部分に関しては省略させていただく。
私はこの分野に関して詳しくはないのだが、この発表について感じた疑問点は、語用論的能力の指導への提言の「発話内の力という概念の指導」に関して、果たして教師が教科書を用いて説明することのみで学習者はその概念を理解できるのか、ということである。母語や第2言語においては、その概念を実際の言語使用という何らかの文脈において習得すると考えられる。逆に考えた場合、その実際の使用の場面における何らかの文脈がない限り、その概念の習得は困難なのではと思われる。つまり、教師による説明のみで実際の言語使用に匹敵する文脈を学習者に与えることができるのか、でなければその概念の習得は困難ではないか、という疑問が私には生じた。(広島大学大学院生 藤谷丈雄)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-3
"Combining Reading Speed and Number Correct in a Computer-Based Sentence Comprehension Test: For Better Assessment of Proficiency"
静 哲人(関西大学)
この研究では、コンピュータを用いた読解能力の測定に関して、読解の早さと内容理解を問う質問の正答数を組み合わせることにより、その測定の妥当性が高まるのかどうか、またどのように組み合わせるのが最良であるのかについて調査がなされた。この調査には、実験的手法が採られた。具体的には、2被験者群に、読解力を測定する標準テストと文の理解テストが被験者に行われた。標準テストは2被験者群双方に対して行われ、それぞれの被験者群で平均正答率が計算された。文の理解テストにおいて、2被験者群のうち、一方の被験者群では1語ずつコンピュータのスクリーンに提示され、他方の被験者群では1文全体が提示された。それぞれの条件下で、1分あたりに平均何語処理できるかの速さと平均正答率が計算された。そして、被験者群別で、標準テストの平均正答率と文理解テストの平均語処理速度と平均正答率の間での相関が調べられた。
その結果、両被験者群において、平均語処理速度と平均正答率を掛け合わせた数値が、それぞれ個々の数値より、標準テストの平均正答率との相関が高いことが明らかになった。また、回帰分析を行った場合でも、平均語処理速度と平均正答率を組み合わせた方が標準テストにおける平均正答率の説明により多く寄与することが判明した。ただし、どのように組み合わせるのが最良であるかは判明しなかった。あと、平均語処理速度は1語ずつ提示された被験者群の方が1文全体を提示された被験者群より大きいことが判明した。
この発表について感じた疑問点は、一方の被験者群に対して行われた1語ずつコンピュータのスクリーンに提示されたことが読解のモデルとして適しているのか、ということである。つまり、私たちは読解をするときに1語ずつ意味情報を処理しているのかということに関して疑問を感じた。例えば、reading speed という2語を読む際に、まずreading と いう語の意味情報を処理して、次にspeed という語の意味情報を処理するのであろうか。それともreading speedのように2語を1個の意味情報として処理するのであろうか。この点に関して、私は興味を感じた。(広島大学大学院生 藤谷丈雄)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-1
「自動添削システム「サッと英作!」による英作文指導」
西村則久(岩国市役所)
「サッと英作!」とは「佐藤栄作!」ではなく、和文英訳の自動添削を行うソフトである。開発者である発表者の西村則久さんは、99年3月まで慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの大学院生であった。現在は岩国市役所に勤務されている公務員である。
発表では氏はまず、「サッと英作!」がこれまでの英作文添削ソフトといかなる点で根本的に異なるかをパワーポイントを使って分かりやすく説明し、BUD(この命名の由来は氏のニックネームである)という高級言語を新たに開発されたこと、そしてその言語を用いた正解例の記述の仕方について詳述された。
BUD言語による記述の特徴は、わずか数行のもので何万例もの正解を表すことができる点にある。添削のために学習者が表出する可能性のある正解のほとんど全部をコンピュータにあらかじめ覚えさせることが、ほんの数種類の括弧や記号などを用いてできるのである。発表の後半にモニターの一斉送出でその添削のすばらしさが紹介された。画面上の黒板で「∧」など用いて的確に英文が添削される有様は、学生時代への切ない郷愁をすら覚えさせる。
「サッと英作!」は現在もまだ進化中で、最新のヴァージョンは、発表の際のものよりも更に使いやすく別解も提示してくれるものに改良されている。氏の研究の更なる進展を祈りたい。(松岡博信 安田女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-2
「自己表現型 presentation 活動の教育効果の検証の一考察」
皆川春雄(京都市立紫野高等学校)
発表者は現職の高校教員でかつ京都教育大学大学院に在学中の学生である。この発表は Oral Communication A の授業の中で実践された speech-making 活動を取り上げて、その教育効果の検証を行ったものである。
具体的には、まず speech-making に対するアンケート調査を生徒に対して行い、特に「音読練習」と「speech の rehearsal 活動」に対する評価が高かったことを踏まえて実験群を設定し、「rehearsal 活動である自作 speech の音読練習」を一定期間集中して行った。そして行わなかった時期との speaking performance の伸びの差異を2種類の英語による口頭発表テストによって観察し、その効果を立証したものである。
これからの英語教育には氏のような public speech 力の育成を目指す指導が大切であることは言うまでもないが、それを実践している英語教師が現在に至っても少ないことは非常に残念であり、その意味でも大変貴重な発表である。
時間的な関係で実験と結果の紹介が多すぎてやや考察が物足りなかった点と、speech- making などの日頃の実践をもっと具体的に紹介して頂きたかったという感想を抱いたが、熱心に生徒を指導され、研究の方も非常に努力されている発表者の真摯な態度が伺われる発表であった。(松岡博信 安田女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-3
「外国語学習方略(Language Learning Strategy)習得の一実践:スピーキング及びリスニングを中心として」
川崎浩志(広島国泰寺高等学校)
この発表では、高等学校の授業において、英語学習者にスピーキング及びリスニングの学習方略を習得させ訓練することで、学習方略の使用状況がどのように変わるか、また学習方略の有効性に関して学習者がどのような認識を持つか、さらに学習者が英語学習に対して示す態度、積極性がどのように変わるのかについて、実践および調査結果を提示したものである。
実践前後でスピーキング、リスニングとも学習方略の使用状況は全体的に上昇するものの、有効性についてはそれぞれの学習方略で、学習者が有効であると認識するものとそうでないものあることが明らかにされた。また学習方略習得を中心に据えた授業に対して、全体的には学習者の好意的な態度が得られたが、一方で学習方略を使用することの難しさやストレスを感じる学習者があったことが報告された。
肯定否定の両方の結果が提示されたが、特に国外のEFLやESLで提案されているさまざまな学習方略の全てが、日本の学習者に適しているとは限らないという点が非常に興味深く思われた。
また、高等学校という、多忙な職場の中での実践研究に対して敬意を表したい。(平尾祟志 広島市立大学大学院生)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-4
「マルチメディア教室での英語授業:自己教育力育成の試み」
奥田久子(広島修道大学)
この発表は、海外セミナーとその出発前の準備英語クラスの模様について紹介したものである。
実施されたプログラムでは「学生が英語圏で現地の人々に働きかけ、コミュニケーションを図ろうとする積極的な姿勢を十分に身につける」ことが目的とされ、出発前の準備クラスではマルチメディア教材を活用し、学生自身の自律的な学習態度を育成するために、さまざまな工夫が施されている。
海外セミナーの授業では、日頃馴れ親しんでいる「受信型の授業」とは異なり、学生に積極的な参加が求められ、また活発な活動を促すために文化、時事問題、ビジネスなどのさまざま内容を授業で扱い、その日のうちにあるいは週末に学習した内容を実際の場で実践、確認する「実地検証学習」が行われる。
国内、国外にわたって実施されるこれらの授業では、学習者の自主性、自己教育力を養うためのさまざまな工夫がなされており、学習者の動機づけや個人差に対しても細やかに気配りされている点がおおいに参考になった。
また、この発表において紹介されたプログラムは学習者に海外セミナーという機会を与え、同時にマルチメディア教材という機器を用いて、これらの機会と機器を組み合わせたという点でも興味深い発表であったと思う。(広島市立大学大学院 平尾 崇志)
--------------------------------------------------------------------------------
講演
「脳と記憶とことば」
山田 純(広島大学総合科学部)
学会の締めくくりに、心理言語学者の山田純先生による講演が行われた。国内外で幅広くご活躍の先生のお話は、参加者に強烈なインパクトを与えたはずである。とりわけ、LLAが教育工学的色彩の強い学会であるにも関わらず、「このようなおもちゃ(CALL機器)で言語習得などできるはずがない」と断言された、冗談とも思われる過激な発言は参加者の脳裏に強く刻み込まれたはずである。
講演は、transmission、すなわち「移る」をキーワードに3部構成で行われた。まず、脳生理学のイントロに続き、脳の中では情報が同じように処理されるのではないことを実例によって説明された。そのひとつが、inner screen (心の映像)と実際の視覚情報の違いである。修正を加えた「モナリザの絵」に違和感を持つのは、脳に記憶された心の目によっても視覚情報が処理されているからだそうである。
第二幕は、人間の動作や言語が相手に「移る」という現象についてであった。例えば、母親の刺激が赤ちゃんに移る現象が挙げられた。これとは逆に、第二言語学習者の場合には「移らない」ことが多いのだそうである。同じように真似て発音しても、実はそうなっていないことは外国語学習でよく体験することである。50センチ以内でインタラクションが行われない限り「移らない」という指摘と、言語学習に cognitive awareness は必要 ないとする結論もセンセーショナルであった。
第三幕では性差による脳構造の違いや、脳の中でどのようなカテゴリー化が行われ、言語知識が記憶されるかについて、最新の研究結果が紹介された。脳の中にはいくつかの意味的カテゴリーが点在しているということが近年の研究から明らかにされつつあるとのことであった。
刺激的な講演であっただけに、参加者からも熱のこもった質問が行われた。その極めが、関西支部長の河野先生による、「はっきり答えていただいて構わないが、こんな機械(LL機器)を使って教育してもダメということですか」という質問であった。必ずしも断定的な回答はされなかったが、少なくとも人間にバイオロジカル的に何が備わっているかを追求する必要があることを強調されていたように記憶している。
脳という、素人には近寄りがたい領域の最新研究の内容が盛りだくさんで、興味は尽きなかった。脳の構造が、と言われれば納得せざるを得ないが、言語習得を脳生理学的方法以外で研究する多くの応用言語学研究の役割は、ではいったい何であるのかという疑問を持ったのは私だけであろうか。(岩井千秋 広島市立大学国際学部)
青木信之(広島市立大学国際学部)
平成11年10月23日土曜日にLLA関西支部秋季研究大会を広島市立大学で開催した。幸いなことに快晴で90名ほど、先生方のご参加をいただいた。
会場校の依頼があったとき、二つ心配な点があった。それは最寄り駅からのアクセスの問題と、昼食、懇親会などの食事の問題である。前者については、事務局の協力を得て、マイクロバスを借り上げることにより、円滑に参加者を輸送することができた。後者の食事については、学内の食堂に依頼した。昼食時は他学部の大きな学会と重なったこともあり、混み合ってしまい不便をおかけしてしまった。しかし、懇親会についは、ご参加くださった先生方から比較的好い評価をいただいたのでほっとした。学会の印象は、実は研究発表以上に、そこでの食事に左右されると言われるので、それだけに好印象をもっていただいて安心した。
学会会場としたのは、語学センターのCALL、LL教室4室であった。これらのいくつかはちょうど機器リース期間の満了に伴い、新しく更新されたばかりであった。それだけに学会にご参加くださった先生方に、新CALL教室をお披露目したいという気持ちと、うまく稼働してくれるだろうかという不安があった。幸い、事務や業者の方々の協力で、CALL 関係の発表も無事滞りなく行われた。
研究発表も、英作文自動添削システムといったものから、リーディング能力測定システムまで幅広く、また講演会も広島大学の山田純先生に挑発的なお話をしていただいた。広島では初めての支部大会であったが、内容的にかなり充実していたのではないかと思う。 最後になったが、学会を開催するにあたって、関西支部事務局の先生方、安田女子大学の松岡博信先生、同僚の岩井千秋、横山知幸、渡辺智恵先生、また、お手伝いしてくださった広島市立大学の事務職員の方や学生のみなさんにも大変お世話になった。この場をお借りしてお礼を申し上げたい。
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-1
「談話構造とプロソディ」
藪内 智(大阪大学大学院言語文化研究科)
この研究は発話生成のプロセスにおけるプロソディ(韻律)の役割を明らかにするという目的で行われている。プロソディと談話構造の間には密接な関係があるという仮説のもと、英語母語話者による音声資料を用いて、プロソディと談話構造がどのように関係しているのかについて研究がなされている。英語教育への展望として、プロソディをもとに、日本人英語学習者が音読した音声資料と英語母語話者のものと比較し、パラグラフの効果的な読み方等の音声指導のあり方について考察をしようとされている。
当研究により、プロソディと談話構造の構造との間の関係が明らかになった際には、聞き手の理解を促進するような発話の指導への一助となるものと思われる。(広島大学大学院生藤谷丈雄)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-2
「英語教育における語用論的能力の構築と指導」
岡本芳和(関西外国語大学大学院)
この研究は、外国語で適切なコミュニケーションを図るにはその外国語の語用論的能力の習得が不可欠であるという仮説のもと、その語用論的能力の指導法の提案を目標とした研究であると思われる。
本発表では、1.現行の中学校と高等学校の学習指導要領にある「言語活動の取り扱い」と発表者が行った学習者対象のアンケート調査をもとに語用論的能力の指導の重要性を指摘し、2.語用論的能力の習得の過程を説明し、そして、3.その指導への提言がなされた。 第1点目に関して、学習指導要領の「言語の働き」の箇所では、言語行為に関する指導が要求されており、学習者の語用論的能力の習得が目標とされていることが指摘された。また、アンケート調査より、学習者も適切に英語を使用できる能力の習得を望んでいることが判明した。よって、語用論的能力の指導が重要であることがうかがわれた。
第2点目に関して、語用論的能力の習得は3段階からなることが指摘された。つまり、発話された内容を正確に理解する能力を習得し、その発話のなされている状況を理解する能力を習得し、実際の運用に至ることである。更に、発話の内容を正確に理解ができなくては、実際の語用論的能力の運用に至らないことが指摘された。
第3点目に関して、まず第1に、発話の内容が正確に理解できるよう指導すること、次に、発話内の力という概念を理解できるように指導することが提言された。実際の指導例は、発表者により、教科書のサンプルを用いた説明がなされた。この部分に関しては省略させていただく。
私はこの分野に関して詳しくはないのだが、この発表について感じた疑問点は、語用論的能力の指導への提言の「発話内の力という概念の指導」に関して、果たして教師が教科書を用いて説明することのみで学習者はその概念を理解できるのか、ということである。母語や第2言語においては、その概念を実際の言語使用という何らかの文脈において習得すると考えられる。逆に考えた場合、その実際の使用の場面における何らかの文脈がない限り、その概念の習得は困難なのではと思われる。つまり、教師による説明のみで実際の言語使用に匹敵する文脈を学習者に与えることができるのか、でなければその概念の習得は困難ではないか、という疑問が私には生じた。(広島大学大学院生 藤谷丈雄)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表1-3
"Combining Reading Speed and Number Correct in a Computer-Based Sentence Comprehension Test: For Better Assessment of Proficiency"
静 哲人(関西大学)
この研究では、コンピュータを用いた読解能力の測定に関して、読解の早さと内容理解を問う質問の正答数を組み合わせることにより、その測定の妥当性が高まるのかどうか、またどのように組み合わせるのが最良であるのかについて調査がなされた。この調査には、実験的手法が採られた。具体的には、2被験者群に、読解力を測定する標準テストと文の理解テストが被験者に行われた。標準テストは2被験者群双方に対して行われ、それぞれの被験者群で平均正答率が計算された。文の理解テストにおいて、2被験者群のうち、一方の被験者群では1語ずつコンピュータのスクリーンに提示され、他方の被験者群では1文全体が提示された。それぞれの条件下で、1分あたりに平均何語処理できるかの速さと平均正答率が計算された。そして、被験者群別で、標準テストの平均正答率と文理解テストの平均語処理速度と平均正答率の間での相関が調べられた。
その結果、両被験者群において、平均語処理速度と平均正答率を掛け合わせた数値が、それぞれ個々の数値より、標準テストの平均正答率との相関が高いことが明らかになった。また、回帰分析を行った場合でも、平均語処理速度と平均正答率を組み合わせた方が標準テストにおける平均正答率の説明により多く寄与することが判明した。ただし、どのように組み合わせるのが最良であるかは判明しなかった。あと、平均語処理速度は1語ずつ提示された被験者群の方が1文全体を提示された被験者群より大きいことが判明した。
この発表について感じた疑問点は、一方の被験者群に対して行われた1語ずつコンピュータのスクリーンに提示されたことが読解のモデルとして適しているのか、ということである。つまり、私たちは読解をするときに1語ずつ意味情報を処理しているのかということに関して疑問を感じた。例えば、reading speed という2語を読む際に、まずreading と いう語の意味情報を処理して、次にspeed という語の意味情報を処理するのであろうか。それともreading speedのように2語を1個の意味情報として処理するのであろうか。この点に関して、私は興味を感じた。(広島大学大学院生 藤谷丈雄)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-1
「自動添削システム「サッと英作!」による英作文指導」
西村則久(岩国市役所)
「サッと英作!」とは「佐藤栄作!」ではなく、和文英訳の自動添削を行うソフトである。開発者である発表者の西村則久さんは、99年3月まで慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの大学院生であった。現在は岩国市役所に勤務されている公務員である。
発表では氏はまず、「サッと英作!」がこれまでの英作文添削ソフトといかなる点で根本的に異なるかをパワーポイントを使って分かりやすく説明し、BUD(この命名の由来は氏のニックネームである)という高級言語を新たに開発されたこと、そしてその言語を用いた正解例の記述の仕方について詳述された。
BUD言語による記述の特徴は、わずか数行のもので何万例もの正解を表すことができる点にある。添削のために学習者が表出する可能性のある正解のほとんど全部をコンピュータにあらかじめ覚えさせることが、ほんの数種類の括弧や記号などを用いてできるのである。発表の後半にモニターの一斉送出でその添削のすばらしさが紹介された。画面上の黒板で「∧」など用いて的確に英文が添削される有様は、学生時代への切ない郷愁をすら覚えさせる。
「サッと英作!」は現在もまだ進化中で、最新のヴァージョンは、発表の際のものよりも更に使いやすく別解も提示してくれるものに改良されている。氏の研究の更なる進展を祈りたい。(松岡博信 安田女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-2
「自己表現型 presentation 活動の教育効果の検証の一考察」
皆川春雄(京都市立紫野高等学校)
発表者は現職の高校教員でかつ京都教育大学大学院に在学中の学生である。この発表は Oral Communication A の授業の中で実践された speech-making 活動を取り上げて、その教育効果の検証を行ったものである。
具体的には、まず speech-making に対するアンケート調査を生徒に対して行い、特に「音読練習」と「speech の rehearsal 活動」に対する評価が高かったことを踏まえて実験群を設定し、「rehearsal 活動である自作 speech の音読練習」を一定期間集中して行った。そして行わなかった時期との speaking performance の伸びの差異を2種類の英語による口頭発表テストによって観察し、その効果を立証したものである。
これからの英語教育には氏のような public speech 力の育成を目指す指導が大切であることは言うまでもないが、それを実践している英語教師が現在に至っても少ないことは非常に残念であり、その意味でも大変貴重な発表である。
時間的な関係で実験と結果の紹介が多すぎてやや考察が物足りなかった点と、speech- making などの日頃の実践をもっと具体的に紹介して頂きたかったという感想を抱いたが、熱心に生徒を指導され、研究の方も非常に努力されている発表者の真摯な態度が伺われる発表であった。(松岡博信 安田女子大学)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-3
「外国語学習方略(Language Learning Strategy)習得の一実践:スピーキング及びリスニングを中心として」
川崎浩志(広島国泰寺高等学校)
この発表では、高等学校の授業において、英語学習者にスピーキング及びリスニングの学習方略を習得させ訓練することで、学習方略の使用状況がどのように変わるか、また学習方略の有効性に関して学習者がどのような認識を持つか、さらに学習者が英語学習に対して示す態度、積極性がどのように変わるのかについて、実践および調査結果を提示したものである。
実践前後でスピーキング、リスニングとも学習方略の使用状況は全体的に上昇するものの、有効性についてはそれぞれの学習方略で、学習者が有効であると認識するものとそうでないものあることが明らかにされた。また学習方略習得を中心に据えた授業に対して、全体的には学習者の好意的な態度が得られたが、一方で学習方略を使用することの難しさやストレスを感じる学習者があったことが報告された。
肯定否定の両方の結果が提示されたが、特に国外のEFLやESLで提案されているさまざまな学習方略の全てが、日本の学習者に適しているとは限らないという点が非常に興味深く思われた。
また、高等学校という、多忙な職場の中での実践研究に対して敬意を表したい。(平尾祟志 広島市立大学大学院生)
--------------------------------------------------------------------------------
研究発表2-4
「マルチメディア教室での英語授業:自己教育力育成の試み」
奥田久子(広島修道大学)
この発表は、海外セミナーとその出発前の準備英語クラスの模様について紹介したものである。
実施されたプログラムでは「学生が英語圏で現地の人々に働きかけ、コミュニケーションを図ろうとする積極的な姿勢を十分に身につける」ことが目的とされ、出発前の準備クラスではマルチメディア教材を活用し、学生自身の自律的な学習態度を育成するために、さまざまな工夫が施されている。
海外セミナーの授業では、日頃馴れ親しんでいる「受信型の授業」とは異なり、学生に積極的な参加が求められ、また活発な活動を促すために文化、時事問題、ビジネスなどのさまざま内容を授業で扱い、その日のうちにあるいは週末に学習した内容を実際の場で実践、確認する「実地検証学習」が行われる。
国内、国外にわたって実施されるこれらの授業では、学習者の自主性、自己教育力を養うためのさまざまな工夫がなされており、学習者の動機づけや個人差に対しても細やかに気配りされている点がおおいに参考になった。
また、この発表において紹介されたプログラムは学習者に海外セミナーという機会を与え、同時にマルチメディア教材という機器を用いて、これらの機会と機器を組み合わせたという点でも興味深い発表であったと思う。(広島市立大学大学院 平尾 崇志)
--------------------------------------------------------------------------------
講演
「脳と記憶とことば」
山田 純(広島大学総合科学部)
学会の締めくくりに、心理言語学者の山田純先生による講演が行われた。国内外で幅広くご活躍の先生のお話は、参加者に強烈なインパクトを与えたはずである。とりわけ、LLAが教育工学的色彩の強い学会であるにも関わらず、「このようなおもちゃ(CALL機器)で言語習得などできるはずがない」と断言された、冗談とも思われる過激な発言は参加者の脳裏に強く刻み込まれたはずである。
講演は、transmission、すなわち「移る」をキーワードに3部構成で行われた。まず、脳生理学のイントロに続き、脳の中では情報が同じように処理されるのではないことを実例によって説明された。そのひとつが、inner screen (心の映像)と実際の視覚情報の違いである。修正を加えた「モナリザの絵」に違和感を持つのは、脳に記憶された心の目によっても視覚情報が処理されているからだそうである。
第二幕は、人間の動作や言語が相手に「移る」という現象についてであった。例えば、母親の刺激が赤ちゃんに移る現象が挙げられた。これとは逆に、第二言語学習者の場合には「移らない」ことが多いのだそうである。同じように真似て発音しても、実はそうなっていないことは外国語学習でよく体験することである。50センチ以内でインタラクションが行われない限り「移らない」という指摘と、言語学習に cognitive awareness は必要 ないとする結論もセンセーショナルであった。
第三幕では性差による脳構造の違いや、脳の中でどのようなカテゴリー化が行われ、言語知識が記憶されるかについて、最新の研究結果が紹介された。脳の中にはいくつかの意味的カテゴリーが点在しているということが近年の研究から明らかにされつつあるとのことであった。
刺激的な講演であっただけに、参加者からも熱のこもった質問が行われた。その極めが、関西支部長の河野先生による、「はっきり答えていただいて構わないが、こんな機械(LL機器)を使って教育してもダメということですか」という質問であった。必ずしも断定的な回答はされなかったが、少なくとも人間にバイオロジカル的に何が備わっているかを追求する必要があることを強調されていたように記憶している。
脳という、素人には近寄りがたい領域の最新研究の内容が盛りだくさんで、興味は尽きなかった。脳の構造が、と言われれば納得せざるを得ないが、言語習得を脳生理学的方法以外で研究する多くの応用言語学研究の役割は、ではいったい何であるのかという疑問を持ったのは私だけであろうか。(岩井千秋 広島市立大学国際学部)